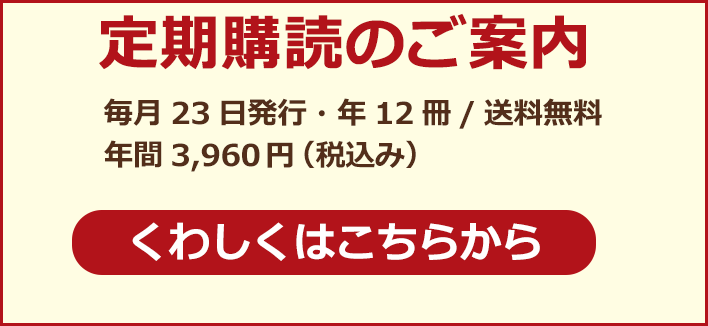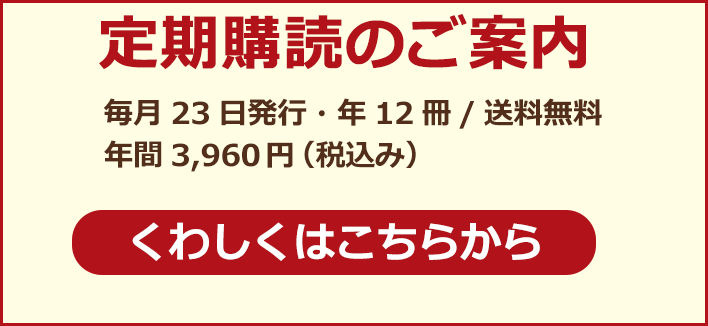太平洋戦争末期、米軍による空襲で当時国宝だった六つの天守が焼失・倒壊した。城はどのような戦災を受けたのか。市民は炎に包まれた天守をどんな思いで見つめていたのか。空襲史料をひもとき、記憶をたどる「城が燃えた」を西日本出版社から上梓した。戦後、いずれも鉄筋コンクリートで外観復元された6城は戦禍の記憶を伝える「無言の証人」でもある。
1945年3月10日の東京大空襲を皮切りに始まった5大都市への無差別焼夷弾爆撃は、6月15日の第4次大阪大空襲をもって完了。米軍は次の攻撃目標を全国の中小都市と各地の軍需工場に移した。日本の40年の国勢調査の結果を参考にして人口の多い順に180都市を選び、1番目の東京市(当時)から180番目の熱海市までの攻撃リストを作っていた。
日本の近代都市のほとんどは、江戸時代に藩の政庁が置かれた城下町。その中心部には城があった。
最初に焼失したのは名古屋城天守。5月14日、名古屋上空に472機のB29爆撃機が来襲。2500㌧を超える焼夷弾が投下されて市街地は焼け野原となり、大天守も2時間余りで焼け落ちた。
6月29日未明には、岡山城天守が炎上した。外壁が黒塗りの下見板で覆われ、市民から「烏城(うじょう)」と呼ばれていたが、激しい炎に包まれた。
7月9日深夜からの和歌山大空襲で、御三家紀州徳川家の居城だった和歌山城天守が、29日深夜には岐阜県大垣市の空襲で大垣城天守が灰燼に帰した。
8月6日午前8時15分、原子爆弾が広島市にさく裂。広島城天守は炎上こそしなかったが、爆発直後の衝撃波と爆風を受けて天守台の上で崩落。敗戦1週間前の8日には、広島県福山市が空襲に見舞われ、五重五階の福山城天守が焼け落ちた。
いずれも旧国宝に指定され、終戦前の3カ月で失われた。
地方都市への空襲の惨状を語り継ぐため、焼けた六つの天守のほかに、市街地が空爆されながらも焼失を免れて天守が現存する姫路城、高知城、松山城。模擬天守ながら再建から90年を超えた大阪城の三代目天守も取り上げた。
また、旧国宝に指定され被災した徳島城の鷲の門、高松城の桜御門の戦後復興の歩みにも光を当てた。
西日本の12の都市で戦禍を生き抜いた体験者の記憶に耳を傾けるとともに、戦後、外観復元されて惨状を今に伝える「燃えた城」にも注目していただきたい。
定価1980円。ご希望の方は書店か、うずみ火事務所(送料込み2000円)でお買い求めください。