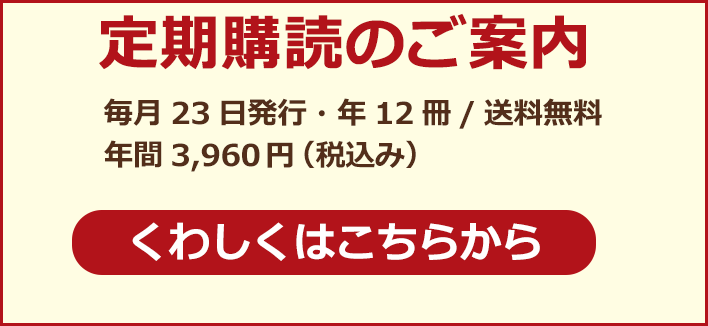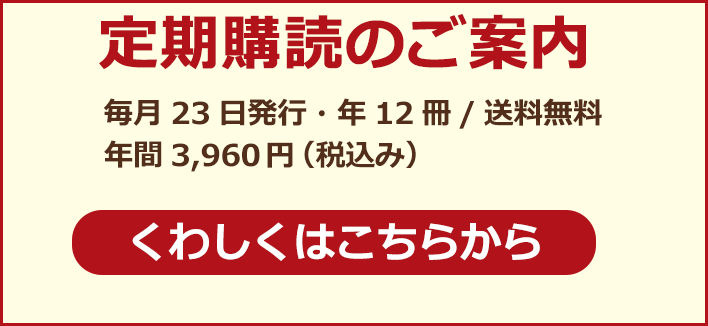「むのたけじ賞」実行委員会の共同代表に寄稿してもらうことにした。トップバッターは、ルポライターの鎌田慧さん。タイトルは「ジャーナリズムの抵抗精神脈々と」。

鎌田慧さん
縁は不思議、というけれど、「むのたけじ賞」の選考委員、というのをやっていた縁で、大阪で発行されている「新聞うずみ火」の存在を知ることができた。「埋み火」は雪国育ちのわたしにとって、郷愁誘う言葉だ。朝になって、囲炉裏の灰のなかから、貴重な火種を掘り起こす生活は身近なものだった。雌伏10年と言うべきか、春を待つこころ、と言うか。
暗闇に光を放ちつづける松明は、敗戦後、朝日新聞を決然として退社、故郷秋田・横手町に帰って、日刊紙「たいまつ」を発刊した、むのたけじの決意と苦闘を表して、いまも輝いている。
あるいは、灰の中の種火は、ポーランドの民主化闘争に伴走した、アンジェイ・ワイダ監督の「灰とダイヤモンド」や「地下水道」を思わせる、未来を賭けた抵抗の精神である。
わたしは「新聞うずみ火」が、右傾化する読売新聞を退社して、月刊「窓友新聞」を発刊した黒田清さんの意思を継いでいる、と知って感嘆した。
戦前の軍部に抵抗した桐生悠々、戦争協力の朝日新聞を去ったむのたけじ、反動の読売新聞を舞台に闘った黒田清。そしていま、「新聞うずみ火」。ジャーナリズムの抵抗の精神は、脈々とつづき、不滅なのだ。
読売新聞の大阪本社版は、いまでは信じられないが、社会部長の名前をとった「黒田軍団」が、戦争反対キャンペーンをつづけて気を吐いていた。権力の走狗と成り果てた、東京本社の渡辺恒雄社長の、眼の上のたんこぶだった。
黒田さんは、読売が大阪進出したとき採用された、新卒第一号だった。そのときの東京本社社長は、元警察官僚の正力松太郎。戦後の読売争議を鎮圧した社長だった。読売は大阪進出にあたって、各紙ではみ出していた「豪傑」を集めていた。
「窓友新聞」は、朝刊社会面の名物コラム「窓」の精神をタイトルにした。キャッチフレーズは「小さな全国紙」。意気盛んである。サスペンダーで吊った、太めのジーンズに白いワイシャツをたくしこんだ黒田主筆は、大阪駅に近い読売本社のそばに事務所を構え、アメリカの新聞人のような、自由な雰囲気を醸しだしていた。

「第3回むのたけじ賞」受賞式であいさつする鎌田さん
「窓友新聞」は、残念ながら、黒田さんが亡くなって廃刊になった。編集部にいた矢野宏さんが、その伝統を継いで「新聞うずみ火」を発刊、上毛新聞から駆けつけた栗原佳子さんと「小さな全国紙」を維持している。
たいまつは燎原の火のようにはひろがらなかったが、うずみ火が次の時代を準備していることが心強い。
4月号のトップ記事は、「福島楢葉町に『原発悔恨の碑』」。福島第二原発をめぐる特報だが、起工されたころ取材にいったことのあるわたしにとって、貴重な記事だった。