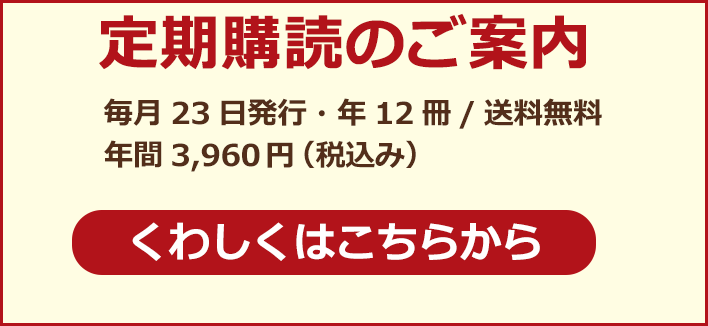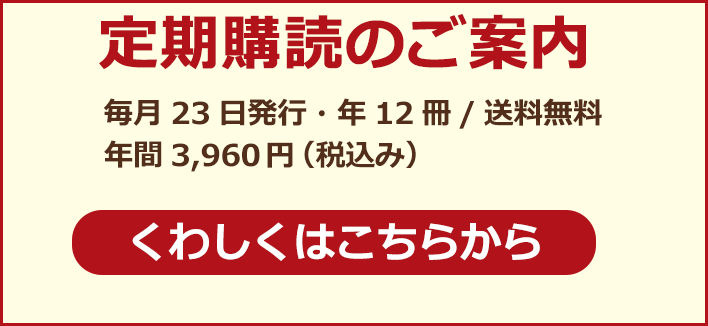新聞うずみ火 最新号

2026年1月号(NO.243)
-
1面~4面 スパイ冤罪 受難の歴史 在日元政治犯と共に ソウルで集い(栗原佳子)
韓国の軍事政権時代、母国留学中の在日韓国人の若者らが「北朝鮮のスパイ」にでっち上げられる事件が相次いだ。1975年11月22日に韓国の情報機関が「在日同胞スパイ団事件」と発表した事件では、21人が逮捕され、死刑を含む重刑を宣告された。日付から「11・22事件」と呼ばれる事件から半世紀。ソウルで「分断と暴力の時代を超え、平和と人権の時代へ」をテーマに記念集会が開かれ、一連の「在日韓国人スパイ事件」の被害者や家族、救援運動を担った日本の市民が集った。(栗原佳子)
「無実の罪によって、私たちの若き夢と理想は根こそぎ引き抜かれ、奪われ、私たちは悪夢のような長い獄中生活を送らざるを得ませんでした。私たちの青春は獄中で終焉を迎え、死刑執行を待つだけの死刑囚たちと、いつ出られるかわからない重い刑を宣告された20代の青年たちはいま、ご覧の通り、こうして白髪の老人となりました」
11月21日、ソウル市の香隣(ヒャンリン)教会礼拝堂。元政治犯でつくる「在日韓国良心囚同友会(以下同友会)」代表の李哲(イチョル)さん(77)があいさつに立った。背後の横断幕には韓国語と日本語で「国家暴力被害者と共に 癒しと平和のハンマダン(ひとつの広場)」とある。
同友会は、1990年の結成。毎年「11・22」に合わせ大阪で記念集会を開いているが、今年は事件50年の節目。韓国側から、ぜひソウルでもと提案された。 同友会が取り組む再審請求裁判の弁護団や「11・22事件」をはじめとする在日関連事件の関係者、民主化運動を闘った市民や団体などが21、22日の2日間、50周年記念の集いを企画。21日は「対話ハンマダン」としてシンポジウム、22日は「文化ハンマダン」と題し、コンサートが行われた。
75年11・22日、KCIAが大々的に発表した「11・22事件」。反共法、国家保安法違反などで21人が摘発され、うち13人が在日韓国人だった。朴正煕(パクチョンヒ)政権は半年前、「緊急措置9号」を発動、民主化運動への弾圧が激しさを増していた。
1970~80年代、朴正煕、全斗煥(チョンドファン)大統領らによる軍事独裁政権は事あるごとに「在日韓国人スパイ事件」を捏造し、北朝鮮の脅威をあおった。その「実績」を、大統領直属のKCIA、国軍内の防諜機関「保安司令部(保安司)」、警察庁の治安本部「南営洞対共分室」が競い合ったという。
…… -
5面 外国人医療費訴訟初弁論 国籍理由に3倍請求(栗原佳子) ※全文紹介
日本で暮らす長女(60代)を訪ねて滞在中、重篤な症状で救急搬送され治療を受けた中国人女性が、無保険の外国人であることを理由に、かかった医療費全体の3倍の額を請求された。これに対し、女性の長女が「国籍を理由にした差別的な取り扱い」だとして、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)に、差額分約450万円の支払い免除を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12月9日、大阪地裁で開かれた。センター側は争う姿勢を示した。
訴状などによると、女性は2019年11月、長女に会うため、短期滞在(3カ月)の在留資格で来日。その後、新型コロナウィルスの感染拡大で帰国できなくなった。短期滞在の在留資格更新を繰り返す中、22年1月半ば、左半身などに運動障害を生じ、救急搬送された。搬送先のセンターに緊急入院。脳腫瘍と診断され、手術が必要になった。1カ月半後、退院し、帰国。長女が付き添い介護したが、翌23年2月に死亡した。
女性は短期滞在のため日本の公的医療保険に加入できなかった。自由診療の場合、医療機関が金額を自由に決められる。センターの請求額は約675万円。同じ無保険の日本人の3倍だった。
長女は無保険の日本人の全額(100%)にあたる約225万円を支払った。そのうえで、残り200%分、約450万円の支払い義務がないことを確認するため提訴した。
長女は結婚し、日本国籍を取得。女性は夫に先立たれ一人暮らしで、互いに行き来していたという。意見陳述で長女は、「緊急搬送され、医療費の説明を受けたが、わずかな希望があれば生きてほしいし、できる限り治療をしてほしくて、拒む理由はなかった。母は私に迷惑をかけられないからと退院した。高額な医療費のため治療を受けさせることができず、いまも後悔している。国籍だけで差別する合理的な理由はない。裁判所には公正な判断をお願いしたい」と訴えた。いまは看護学校に入学し、学んでいるという。
報告集会で原告弁護団は、「日本国籍ではないという属性により3倍もの医療費を請求することが許されるのかどうかが最大の争点。医師は正当な理由がなければ診療を拒否できない応召義務がある」と説明した。無保険の外国人に対する法外な請求が常態化する現状をただす、社会的意義の大きい裁判と位置付ける。
提訴前の交渉で、センター側は「外国人は未払いで逃げるかもしれない」「ほかもやっている」などと述べたという。裁判を支援するNPO法人多民族共生人権教育センターの文公輝(ムンゴンフィ)事務局長は「厚労省の昨年度の医療機関全体の未払金についての調査では、『未払いで逃げた』98・6%が日本人。外国人は1・4%だった。事実に基づかず、『外国人は逃げる』という偏見をベースに、法外な額を外国人に請求するのは差別に他ならない」と話した。
第2回期日は来年2月24日午後1時半から807号法廷で開かれる。
-
6面~7面 赤旗記者の名刺公開続く 維新とは徹底的に対決(矢野宏)
日本維新の会の藤田文武共同代表側が、約2000万円の公金還流疑惑をスクープした「しんぶん赤旗」日曜版記者の名刺画像をネット上に無断掲載したことで嫌がらせメールが大量に送られ、業務に支障が出ているという。藤田氏に対し、赤旗編集局長と日曜版編集長が削除と謝罪を求めたが、やがて2カ月になる今も名刺画像はさらされたままだ。
しんぶん赤旗日曜版が「身内への税金還流」と疑惑を報じたのは11月2日号(電子版は10月29日配信)。公設第1秘書が代表を務める兵庫県内の会社に、ビラやポスター印刷などを発注し、2017年から24年までに計約2000万円を支出していた。9割以上が公金を原資とする調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)などで、この秘書は国からの給料だけでなく、同社から年間約720万円の報酬をもらっていたという。
自民党と連立与党を組む維新の代表に浮上した「政治とカネ」をめぐる疑惑。藤田氏は「実態のある正当な取引」で「適法」だと強調するが、維新の吉村洋文代表(大阪府知事)はこの問題を受け、議員や秘書が代表に就く企業への公金支出を禁止する内規を設けた。適当ではないと認めたからだ。
看過できないのが、疑惑を報じられた直後、藤田氏が取材記者の名刺画像をⅩ(旧ツイッター)に投稿したこと。携帯番号やメールアドレスの一部はぼかしているものの、記者の名前や編集部の電話番号などはそのまま載せている。
「大阪のメディアが維新に対してなぜ、物が言えないのか。わかった気がします」
東京都渋谷区千駄ヶ谷の赤旗日曜版編集部で、取材に応じた山本豊彦編集長はそう切り出した。
「維新は、逆らうメディアに対して徹底的に攻撃し、メディアを分断していく。『赤旗は共産党のプロパガンダ紙』『報道ではなく政治的主張』だと。政権与党幹部による取材活動への重大な妨害だ。東京でもやれると思っているのでしょう」
赤旗日曜版は、安倍晋三首相(当時)による公的行事の私物化として「桜を見る会」、自民党派閥の政治資金パーティーの裏金をめぐる疑惑をスクープしてきた。それでも、「自民党は取材記者の名刺をさらすようなことはしなかった」と山本さんは振り返る。
「自民党には、権力の行使は抑制的であるべきだと理解している人もいる。一方、与党となった維新は権力を行使する側になりながら、歯止めがない。ここまで卑劣なことをやる。表現の自由とか、憲法精神を理解していないからかもしれません」
…… -
8面~9面 迷走続く万博跡地活用 売却案に財界「待った」(木下功)
大阪府と大阪市が進める2025年大阪・関西万博の会場跡地の活用方法を巡り、経済界や市議会、府民などから異論が相次いでいる。本誌12月号でも、25年10月に公表された会場跡地のまちづくりの方針「夢洲第2期区域マスタープランVer・2・0」の内容や策定の経緯、寄せられた意見について伝えたが、事態は収まる気配がない。マスタープランについて様々な疑問や指摘がある中で、今回は夢洲内の隣接地にもかかわらず、IR用地は貸付で万博跡地は売却となった理由についてみていく。
万博跡地が売却と決まったのは25年6月6日の大阪市戦略会議。IR用地と万博跡地の違いについて問われた大阪港湾局長は、埋立地の処分は「売却が大前提」とした上で、次のように説明した。
IRについては「IR整備法に基づき、国の認定を得て実施される公益性の高い事業として、長期間にわたる安定的・継続的な事業実施の確保が重要であり、事業期間の満了時や、事業継続が困難となるような事態となった場合にも、まずはIR区域の継続を目指すことが必要であり、土地所有権を市に留保し、府市が主導的に区域のあり方を決定できるよう貸付とされたものである」
一方の万博跡地については「マスタープランの範囲内で事業者が事業計画を自由に検討し、事業を実施するものであることや優秀提案の提案事業者からの意見も踏まえ、埋立地の一般的な処分方法である売却と考えている」と答弁している。
質問した高橋徹副市長は「IRは事業の特殊性から貸付としていて、今回の2期については優秀提案者からの要望もあり、また従来からの処分方法であるため売却という理解でよいか」と引き取り、大阪港湾局長は肯定している。
つまり、IR事業は「公益性の高い」特殊な事業であるため、事業継続が困難になった場合でもIR区域の継続を目指すことが必要なため、市が土地を所有するということで、夢洲の土地処分方法としては異例の対応ということになる。では「事業継続が困難」とはどういった場合なのか。
…… -
10面~11面 「軍転法」施行から75年 呉の戦後復興の礎に(湯谷邦彦)
先の大戦で壊滅した広島県呉市。「東洋一の軍港」だった呉港は敗戦後、平和産業港湾都市としての復興を誓った。だが撤退した日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区(日鉄呉)の跡地には兵站機能を持った軍事産業が復活しようとしている。いま「複合防衛拠点」として発展を求めているのはなぜか。そこには国策に翻弄される地方自治体の実体が浮かび上がる。
1950年4月、「旧軍港市転換法」(軍転法)が特別法として国会で可決した。
法律の制定は通常、国会の議決で成立するのが原則だ。だが、憲法95条にこう規定されている。
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない」
つまり、地方特別法は、憲法の規定により、可決後にその法律が適用される自治体で住民投票などを実施し、住民の承認(賛成多数)を得なければ法の成立ができない。
憲法が「地方公共団体の個性の尊重」「地方公共団体の平等」「自治権の侵害防止」などを決めているからだ。
憲法95条の規定に則り、これまでに「広島平和記念都市建設法」や「長崎国際文化都市建設法」「首都建設法」など16の地方特別法が、国会で可決した後に住民投票が行われた。
米軍による空爆で壊滅的な被害を受けた呉市は、旧海軍の鎮守府が置かれた横須賀市(神奈川県)や佐世保市(長崎県)、舞鶴市(京都府)とともに、旧軍用財産の転用を促す地方特別法制定を国会に働きかけた。
軍転法の第1条には、この法律の目的が定められている。
「この法律は、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に起用すること」
市の復興のためには、これまでのような軍と共生する都市から平和産業港湾都市への転換を図るしかない。そのための「事業の援助」(第3条)と「特別の措置」(第4条)、「国有財産の無償譲渡」(第5条)が必要だったのだ。
呉市を含む旧軍港4市で50年6月4日、軍転法の是非を問う住民投票が行われた。
呉市では「軍港から商港へ切り替えて文化都市を建設しよう。全市民が賛成に投票を!」と、当時の市長や市議会議長らが宣伝カーで呼びかけるなど、強力なキャンペーンを繰り広げた。
一方で、港湾施設のほとんどがGHQに接収されており、「軍港から商港へ」の転換ができるかどうか、疑問を持つ議員らもいたが、当時は意に介されなかった。
投票率は82・2%。賛成95・8%(8万1355票)で、反対はわずか4・2%(3523票)だった。市民の圧倒的支持を受け、軍転法の適用が決まった。
ところが、住民投票から3週間後の6月25日、朝鮮戦争が勃発し、日本経済は戦争特需の恩恵を受ける。と同時に、再軍備へ舵を切ることになる。
…… -
12面~13面 福間六冠 将棋連盟に訴え 「おめでた不戦敗」削除(粟野仁雄)
12月10日の大阪弁護士会館に報道陣多数が詰めかけた。喉の調子が最悪だったそうで痛々しかったが「決意の記者会見」で女流棋士トップは懸命に苦境を訴えた。
現在、女流将棋の全8タイトル中、女流名人、女王、女流王座、倉敷藤花、女流王位、清麗の六つを保持する福間香奈六冠(33)が「(現在の規定では)タイトルか出産か選ばなければならず、将棋界の未来に強い不安がある」などと、日本将棋連盟に対して出産時のタイトル戦への配慮などを訴えた。
2023年に元奨励会三段の福間健太さんと結婚し、昨年12月に長男を出産した。その際、出産2カ月前のタイトル戦では重いつわりや胎盤異常の恐れなどで遠距離移動ができなかった。連盟に延期や対局場の変更を求めたが受け入れられず、女流王将戦と白玲戦は不戦敗になった。
福間さんは妊娠、出産を抱えた女流棋士が「タイトルか子どもか」の二者択一に陥る現状について、「体調や医師の意見に応じて、タイトル戦の出場や日程・場所の調整ができる」「タイトル保持者は産休中にその地位から降格しないようにする」などの連盟宛ての要望書を会見前日に提出していた。
会見で福間さんは「将棋は私にとってすべて。妊娠を喜べず苦しかった」と振り返り、「今の規定ではもう一人子どもを欲しいと思ってもあきらめざるを得ない」と訴えた。
福間六冠は島根県出身で、6歳から始めた将棋で異能ぶりを発揮し、12歳で女流プロデビューした。20歳の頃に体調不良で対局から離れたが、復帰すると 強敵を次々と倒し、19年には史上初の「女流六冠」を達成する。今年4月にも、筆者が取材に赴いた高槻市の将棋会館で西山朋佳五段を五番勝負の最終局で破り、女流名人位を防衛した。
現在では少数派の「振り飛車党」で、序盤に飛車を5筋に据える「中飛車」を得意とする。鋭い攻めから「出雲のイナヅマ」の異名がある。森雞二九段門下。
…… -
14面~15面 ヤマケンのどないなっとんねん 遅れてきた「軍国少女」(山本健治)
高市自民維新連立内閣発足2カ月、トランプ大統領への気持ち悪いまでのベタベタ、台湾問題でとんでもない答弁をやらかし、厳しい状況に追い込まれているが、威勢だけはよく、「物価を下げ、経済を強くする」と叫んで臨時国会を召集、補正予算を提出した。
周知のとおり自民党は少数与党に転落、いつ細川内閣時代のような状態に追いやられるかわからなかったが、立憲は野党をまとめられず政局で存在感を発揮できず、突如の自民維新連立成立で傍観を余儀なくされ、党首討論では高市首相に「そんなことより議員定数削減を」とたたみかけられても反応できず、完全に有権者から見限られ、審議でも存在感を示せず、終わった状態になった。
前号で高市首相が高い支持率を背景に解散、総選挙に打って出ても負けると書いたが、あの党首討論、国会審議で状況は変わって、解散はしないようだが、選挙になれば立憲はボロ負け、前回、自民党が経験したような解党的敗北に追い込まれるのではないか。「年収の壁」で議席を増やし、うまくいけば首相の座が転がりこんでくるかもとニヤけていた国民民主も「維新に油揚げ」で外野に追いやられ、おこぼれ頂戴状態でわずかなニンジンでも補正賛成にまわらざるをえない状態になった。何かあれば連立参加に動くのではないか。
こんな中、自民党の海千山千の古狸たちは裏藪を動き回って無所属議員を一本釣り、自民単独でも過半数以上を確保しようとしているのではないか、ターゲットは元維新の連中で、そのうち入党させて過半数確保するのではないかと思っていたが、そのとおりになった。こうした工作もあわせ11日、コロナ感染拡大以降最大規模の18兆3000億円強の補正予算が衆院通過、17日の会期末までには参院でも通過した。
維新が「一丁目一番地」と言い、成立しなければ連立から離脱すると息巻いていた議員定数削減は先送りされたが、維新は不祥事連発などで党勢が落ちるばかりの現状では、屁理屈つけて連立離脱しないだろう。
…… -
16面~17面 世界で平和を考える ルワンダ大虐殺㊦(西谷文和) ※全文紹介
前号ではアフリカ・ルワンダ大虐殺が起きる直前までの経過を述べた。大虐殺は1994年4月から7月のわずか100日間で約100万人が殺されるという悲惨な事件で、主に多数派で人口の約85%を占めるフツ族の民兵組織が、少数派で14%のツチ族と、「ツチをかばおうとした裏切り者のフツ」を棍棒で殴り、山刀(マチューテ)で斬り殺すという民族浄化であった。
ではフツ族とは、ツチ族とはどんな人々なのか?
現地の「ルワンダ虐殺記念館」に詳しい資料が展示されていた。結論から言えば「もともと同じ人々」だった。第1次世界大戦後、この国を支配したベルギーが人々の鼻の高さを測っていき「鼻が高くて、比較的色白の人」をツチに、「鼻が低くて色の黒い人」をフツに、無理やり二分した。ベルギーは少数派のツチに政治を任せ、多数派のフツが虐げられていた。国民を分断し、争わせることで宗主国ベルギーは安泰となり、この国を支配することができていたのだ。
やがて第2次世界大戦が勃発。戦争が終わると帝国主義、植民地主義を「形だけ反省」した世界は、民族自決の時代に入る。ルワンダも61年に独立を果たし、支配者ベルギーが本国に帰っていく。そして普通選挙が実施されると多数派のフツが勝利し、権力を掌握する。今まで虐げられてきたフツが少数派のツチに報復する。この構図があったので、ルワンダは独立当初から、フツによるツチの虐殺事件が頻発した。フツ政権が学校で強烈なツチへの差別教育を進めた結果、若者たちの間に「インテラハムエ」という民兵組織が誕生する。そしてこのインテラハムエこそが、大虐殺事件の実行犯に育っていったのだ。
90年代初頭、ルワンダの緊張を高めたのはヘイト新聞とヘイトラジオだった。「カングラ新聞」はツチへのヘイト記事を連載する。その内容は「ツチはゴキブリだ。進め、進め」と、フツの軍隊がツチの棺桶の上を行進するイラストや、「病気になりました」「症状は?」「ツチ、ツチ、ツチ」というマンガなどとんでもないものだったが、影響力絶大だったのがラジオ「ミルコリンズ」。これらの記事をヘイトスピーチで拡散していったのだ。
ちなみにこのラジオ局は政府から多額の寄付を受けている、いわば国営ラジオだった。フツ極右政権の意向を汲んだラジオが恐怖をあおり始める。「今、ツチを殺さないと今度は俺たちフツが殺されてしまうぞ!」。首都キガリは憎悪のるつぼとなる。政府とインテラハムエは密かに「虐殺名簿」を用意する。そう、虐殺は突然起こったのではない。フツ第一主義の極右政権と、政府に洗脳された若者の民兵組織が「じっとその時を待っていた」のであった。
この時、インテラハムエの内部から国連PKO部隊に告発文書が届く。「国連が今、動かないと大虐殺が起きてしまう」。内部告発を受けたロメオPKO司令官がニューヨークに情報を打電。しかし、国連は動かない。あくまで「停戦を監視」する、つまり見ているだけでインテラハムエを止めなかったのだ。そして運命の4月6日を迎えてしまう。
大統領を乗せた飛行機がキガリ空港に着陸寸前、何者かのロケット弾を浴びて撃墜されてしまうのだ。ラジオ・ミルコリンズは何の根拠もなく「これはツチの仕業だ。ツチを始末しろ」と騒ぎ立てる。
翌日から大虐殺が始まった。山刀を持ったインテラハムエが次々とツチの一般市民を切り殺していく。逃げ惑う人々、追いかける殺戮者。虐殺は「捕まったら殺される鬼ごっこ」の様相を呈し、身を隠す者、川に飛び込む者、ひたすら平原を走って逃げる者……。やがて日没、そこで身を潜めた人々は、夜明けとともにまた走って逃げ出し、インテラハムエが追いかける。こうして1日1万人、1時間で400人、1分間に7人が延々と殺されていったのだ。
「虐殺記念館」には遺族の証言が多数残されていた。その中に父親を殺された娘のものがあった。「インテラハムエの民兵が父を殺した後、遺体を二つに切り裂きました。『ツチの体にはミルクが流れている』というプロパガンダを信じた兵士が、本当かどうか確かめたのです」。
虐殺されたのはツチだけではなかった。ツチを匿うフツも殺された。かつての支配者ベルギー人も殺された。実は極右政権の中にも「穏健派のフツ」がいて、この穏健派フツの政治家を警護するためにベルギー兵士がPKO部隊に派兵されていた。インテラハムエはこのベルギー兵士10名を殺害している。この事態を受けてロメオ司令官はニューヨークの国連本部に電話する。「5000人の兵士を追加派兵してほしい。そうすれば虐殺を止めることができる」。しかし、国連本部は「ルワンダは危険」と兵士を引き上げる。その結果、隣国ウガンダに逃げていた難民たちで組織された「ルワンダ愛国戦線」がキガリに来るまで、100日間も虐殺が続いてしまったのだ。
この苦い教訓から国連はPKO部隊の任務を「停戦の監視」から「積極的な住民保護」に変化させた。日本ではあまり知られていない。「憲法9条を持つ日本では、自衛隊は武器を使用しない。だから参加しない」のか「憲法9条を変えて積極的に参加する」のか、どちらか。私は平和ブランドを活かして、日本はPKOに参加せず、外交に特化すべきで、例えばA国とB国の間に入り、国連和平会議の議長になる、などが日本の本当の役割だろうと考えている。
ルワンダ大虐殺から30年が経過した。今、日本では「日本人ファースト」を主張する政党が伸長している。当時はラジオからのヘイトだったが、SNSが発達した今ではもっと簡単に、巧妙にヘイトが広がってしまう。「外国人が鹿を蹴っている」と平気でデマを飛ばす人物がトップになった。冷静になろう。デマやヘイトは想像以上に感染力がある。私たちはもっと現代史を学ばねばならない。
-
18面~19面 フクシマ後の原子力 再稼働認めた新潟知事(高橋宏)
12月10日、北海道の鈴木直道知事が北海道電力の泊原発3号機を再稼働させることへの同意を正式に表明した。これによって、早ければ2027年にも同原発は再稼働する見通しとなった。同意する理由について、鈴木知事は再稼働後の電気料金の値下げ、「脱炭素電源」の確保による道内経済の成長、温室効果ガスの削減などを挙げている。同原発は、7月に新規制基準を満たしているとして、原子力規制委員会(規制委)の安全審査に合格していた。
早速その翌月、政府は道と立地・周辺4町村に同意を要請している。10月には北海道電力が再稼働後の電気料金値下げの見通しを公表した。これを受けて、立地自治体である泊村の高橋鉄徳村長が同意を表明し、周辺3町村長も次々と同意した。鈴木知事も同時期に「原発の活用は当面取り得る現実的な選択だ」として、再稼働を容認する意向を示していた。
泊原発の再稼働容認に先立つ11月21日、新潟県の花角英世知事が東京電力の柏崎刈羽原発について、再稼働を容認する考えを表明した。同原発が再稼働されれば、福島第一原発事故を起こした当事者である東京電力が所有する原発では初めてということになる。花角知事は、12月2日の定例県議会で自身の信任を経た上で、政府と東京電力に対して正式に地元同意を伝達する。
新潟県議会は知事の与党会派である自民党が過半数を占めており、容認はほぼ確実で、閉会日の12月22日以降、政府に再稼働容認が伝えられる見通しだ。同原発6、7号機は2017年12月、規制委の安全審査に合格している。テロ対策の不備で規制委から運転禁止命令を受けたが、23年12月に命令は解除されていた。6号機はすでに燃料が装着されており、規制委の確認作業が順調に進めば、来年1月中にも再稼働が可能である。花角知事は再稼働の判断に当たっては「県民の意思を見極めてリーダーとして判断し、その判断について県民の意思を確認する」としてきた。
岸田文雄政権が大きく「原発回帰」に舵を切った後、政府は原発立地自治体に再三、再稼働を要請していた。そのような中、24年10月の衆院選では新潟県内五つの小選挙区で、再稼働に慎重な立憲民主党の候補者が議席を獲得した。また3月、「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」が、県内有権者の12人に1人に当たる14万3196人分の有効署名を集め、県民投票条例の制定を請求している。
しかし、条例制定案は4月の臨時県議会で、反対多数で否決された。その一方で、花角知事が県民の意思を「見極める」ために取った手段が、9月に実施された「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査」だった。その結果は、再稼働の是非をめぐって賛否がほぼ拮抗していた。それだけでなく、再稼働の条件が現状では「整っていない」という回答が6割に及んでいた。
現時点では再稼働を容認できない、という民意は明確だった。それでも再稼働を認めた花角知事は「どちらかの答えを取れば、反発が残るのは避けられない。反発を小さくしたいと、多くの人の声を時間をかけて伺うというプロセスを大事にしたつもりだ」と述べている。それならば、なおさら再稼働を認めた根拠が見えなくなってしまう。
…… -
20面 こちらうずみ火編集部 深沢潮さんが講演(栗原佳子) ※全文紹介
小説家の深沢潮さんが12月18日、大阪市内で講演、戦争と性暴力を女性の視点で取り上げた『翡翠(ひすい)色の海へうたう』(KADOKAWA)に込めた思いを語った。日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワークが主催した。
深沢さんは2012年、「女による女のためのR‐18文学賞」大賞を受賞し、デビュー。自らのルーツである在日コリアンの問題や生きづらさに向き合う数多くの作品を世に出
してきた。深沢さん自身が「週刊新潮」に掲載されたコラムで名指しのヘイト攻撃を受けた問題は記憶に新しい。
『翡翠色の海へうたう』は21年の作品。戦時下の沖縄で「慰安婦」とされた朝鮮人女性と、そのテーマで小説を書こうとする作家志望の日本人女性の2人が主人公だ。
深沢さんは「声をあげ、声を聴く」と題し、作品が生まれた経緯を振り返った。
韓国で別の作品の取材中、元「慰安婦」のハルモニ(おばあさん)たちが共同生活を送る「ナヌムの家」を訪ねる機会があった。「ぽっと行って話してくれるわけがない。当然だと反省した」。帰国後、何十冊もの関連書籍を読んだ。沖縄戦についても、旅行中、戦跡などを訪ね、自身があまりに知らないことを痛感。多数の書籍や資料を手に取った。
沖縄戦において、日本軍は145カ所を超す「慰安所」を設けた。作品の舞台は慶良間諸島の阿嘉島。44年11月に連れてこられた女性たちは、米軍上陸前の45年2月、沖縄本島に移り、その後、地上戦に巻き込まれた。
取材で阿嘉島を訪ねると、女性たちの食事の世話などをした90代のキクエさんらが健在だった。深沢さんは、キクエさんが女性たちとの交流を鮮明な記憶でたどったり、当時覚えた「アリラン」を歌ったりする姿も映像で紹介した。
研究者ら専門家に監修を依頼、連載中も毎回チェックを受けた。「間違いやミスリードがあってはならない。沖縄の人たちの気持ち、慰安婦にされた女性たちの状況。知れば知るほど、いかに自分が知らないかを知った」という。
書籍化の際、懸念したバッシングはなかった。深沢さんは「きちんしたエビデンスは伝わるのだと強く思った」と話した。
-
20面 こちらうずみ火編集部 足尾銅山鉱毒事件 2026年版正造カレンダー(栗原佳子) ※全文紹介
NPO法人「足尾鉱毒事件田中正造記念館」(群馬県館林市)が、田中正造の2026年版カレンダーを製作した。
中央には正造直筆の言葉「農民ハ愚でも 百年の計を思ふ 知識ある官吏ハ一日の計のみ」。正造研究者の赤上剛さんによると「田畑・山川とともに生きる農民には百年の計を思う『経験知』があるが、知識豊かな高級官僚や議員たちは一年の計どころか自分の地位・出世しか頭にない」の意味で、農民から強制的に土地を引き離す政府への批判が込められているという。
500円。問合わせは記念館(0276・75・8000)
-
21面 経済ニュースの裏側 株高の背景(羽世田鉱四郎)
あふれるマネー 世界の公的債務(借金)は324兆㌦(2025年末、IMF調査)。世界の運用資産規模は、運用会社500社の資産残高が、22年時点で131兆㌦。上位10社は、トップを含めて米国が8社を占め、ドイツ、フランスが入ります。首位のブラック・ドッグ(米)の預かり資産は10兆米㌦(22年10月)。
遍在する世界の富 21年の上位富裕層1%は、世界の個人資産の37・8%を占め、うち0・1%の層で19・4%。一方、世界不平等研究所によれば、下位の貧困層50%は、世界の個人資産のわずか2%を占めるにすぎません。日本の富裕層は、野村総研(21年)によると資産1億円は世帯数の2・7%(139・5万世帯)で、資産の15・9%を保有。さらに資産5億円以上は、90万世帯(0・2%)で、全体の6・4%を占めるとのこと。日本の長者番付(25年)では、①柳井正(ファストリ会長)7兆円②孫正義(ソフトバンク会長)4兆930億円③瀧崎武光(キーエンス創業者)3兆円④佐治信忠(サントリーH)1兆5200億円⑤重田康光(光通信創業者)1兆円の各氏です。
タックスヘイブン(租税回避地) 日銀の資料(資金循環表25年6月)によれば、日本は世界一の純資産516兆円を持ち、かつ家計の金融資産は2239兆円とのこと。ただし、これは表に出た数字であり、法人や富裕層は、海外のタックスヘイブンを利用し、税金逃れや隠れた財産などを保有しています。実態は不明ですが、15年にパナマの法律事務所(世界4位の規模)から「南ドイツ新聞」に機密文書がもれた「パナマ文書」事件で、その一部が明らかに。世界のあらゆる指導者の名前が記載されて大騒ぎに。プーチン、習近平、盧泰愚の一族などの名前も。日本では、伊藤忠、丸紅、電通などや富裕層の一部の名前が明るみに。なお「プーチン大統領は、現在でも一族24人が巨額の利権をむさぼっている」とか(雑誌「選択」12月号)。
株高の背景 あふれ返る投機資金の一部が、日本の株式市場に流入。株式の持ち合いが減少し、資本効率の改善(増配、自社株の増加、不採算事業の売却など)が進展し、「日本株への投資は大儲け、25年のリターンは、世界平均の1・7倍」(11月14日付日経新聞)とのこと。短期利益の急増を目指すアクティビスト(ものいう株主)も含めたファンドが増え、企業の社会性はそっちのけで、短期の収益増、資本収益の増加を目指す傾向にあります。また、超高速売買や仮想売買の相場操縦なども、株高に拍車をかけています。日本の株式市場は、米国市場のコピーと称されます。反面、「人工知能ブームでAI・半導体関連の銘柄が中心で、特にアドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクGの3社が、日経平均4万円から5万円への上昇分の半分以上(55%)を占める」(11月12日付朝日新聞)といった危うい構造も見逃せません。
…… -
22面 会えてよかった 比嘉博さん⑬(上田康平) ※全文紹介
爆音被害について比嘉さんも――
夜の7時、8時は平穏を求めたい
時間なのに、ヘリが飛行する。10時越しても飛んでくる。日常的にイライラ……。
2017年、米軍ヘリの窓が落下してきたこともあり、子どもは運動場で遊びながら、危険を感じている。授業の中断があるし、集中できない。
普天間基地は世界の紛争と直結した基地。訓練が頻発している。
第3次訴訟原告は5875名 普天間基地爆音訴訟は02年、住民404名が第1次訴訟を起こし、12年には3417名が第2次訴訟を起こした。しかしいずれの訴訟でも、爆音は違法として賠償金が支払われたが、裁判所は米軍機の飛行を日本政府はコントロールすることはできない(第三者行為論)として、違法な爆音の差止めを棄却し続けている。
そのため第3次訴訟が20年に提訴され、原告は23年5月現在、5875名となり、裁判所が認める違法な爆音(原告になれる)地域に居住す る市民約5万人の1割 を超えている。
主な請求内容は①夜7時から翌朝7時までの飛行及びエンジン調整の禁止。②朝7時から夜7時までの爆音を65デシベル以下に制限すること。③過去及び差止めが認められるまでの損害賠償。
沖縄タイムスは、21年7月の第1回口頭弁論で、原告代理人は、「第三者行為論」などによって爆音の差止めを退けることは「憲法に違反する」と主張したと報じている。
比嘉さんも――
人間として人権、憲法を守ってほしい。しかし、今の司法の現状を見ると勝訴できるか、楽観はできない。
22年5月、嘉手納と普天間の訴訟
団代表が合同で行政訴訟を起す
飛行差止めを米国に請求できる地位にあることの確認や米軍機に管制権限を発動し、爆音を一定レベル以上出させないようにすることなどを国に求めるという。
※※※
比嘉さんに取材させていただき、「沖縄『平和の礎』はいかにして創られたか」(共著)を読んだ。あらためて「平和の礎」を訪ねたいと思う。▼療養所で戦没したハンセン病患者の生きた証を礎に刻みたいと愛楽園・南静園両自治会が取り組まれたことを少しだけ書かせていただいた。▼米軍ヘリ墜落20年を振り返るパネルディスカッションでの比嘉さんの発言で、地位協定の問題をあらためて確認し、改定の必要性を思った。記録保存の大切さも納得した。▼比嘉さんのお話を聞き、普天間基地爆音訴訟団のホームページなどを読んで、米軍機の危険性や爆音被害のことに少しふれることができた。それは人権侵害であり、許せない。
比嘉さん、これからもお付き合いください。よろしくお願いします。
-
23面 日本映画興亡史 初監督作にアラカン呆然(三谷俊之)
山上伊太郎が宮川町の娼妓を足抜きし、行方をくらまして2年、この国は転がる石のようだった。1936(昭和11)年、二・二六事件が起こり、翌年には中国と戦争に突入した。映画界は最後のきらめきで、溝口健二『浪華悲歌』『祇園の姉妹』、内田叶夢『人生劇場』、伊丹万作は『赤西蠣太』、そして山中貞雄『人情紙風船』などの秀作が送り出された。
一方、満州映画協会の設立、吉川英治ら文人の特派員従軍、映画各社の合併など負の状況も続く。そして38年9月、山中貞雄大陸に死す。28歳だった。国家と国民全体が、時代の激流に投げ込まれたのだ。
山上は脚本家としての名声は高かったが、映画人としてはすでに破綻していた。34年、嵐寛寿郎プロで山上は第1回監督作品『兵学往来髯大名』の撮影に3カ月かけ、ようやく完成した映画を見て皆驚いた。主演のアラカンは呆然とした。
「ワテも驚いた。ヒゲつけて出ますやろ、はいな次のカット、ヒゲあらしません。ほてからにまた次のカット、ヒゲついてますねん。(中略)ヒヤーッこらどういうこっちゃ、話が繋がらんのならまだよろしい、ぜんぜん絵がつながっとらんやないか」(竹中労「聞書アラカン一代『鞍馬天狗のおじさんは』」)
山上の編集でフィルムはズタズタに切られ、復活不可能。マキノ正博によれば、「みんなの尊敬の的でしたからね。一コマづつ切るのも、なにか意味があるんだろうと、最初は思うとったらしい。どうも変だと気がついたときは、もうバラバラ事件ですわな」(竹中労『日本映画縦断3』)。試写会には山中貞雄も稲垣浩もいたが、皆唖然とした。灯りがつくと、山上は姿を消していた。
…… -
24面 坂崎優子がつぶやく エルシーなきAIの進化
「Soraアプリ」が物議をかもしています。これはオープンAIの動画生成AIを使って作った動画を共有するSNSです。9月30日に米国とカナダで先行リリースされるやいなや、ポケモンやドラゴンボールなど日本のアニメに酷似した動画が氾濫しました。
この状況に、日本のコンテンツ会社やメディアなどが加盟する、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)がオープンAIに対し要望書を提出しました。「無許諾で学習対象としない」「著作権侵害に真摯に対応する」というごく当たり前の要求です。
リリース当初、日本で利用するにはユーザーからの招待が必要でしたが、現在は招待なしで利用でき、日本でも広まっています。このSNSで最も懸念するのがキャラクターカメオ機能です。ドラマや映画で有名人が少しだけ出演することをカメオ出演といいますが、「Sora」でも自分を動画に出演させることができます。自分の声や顔を登録することで、そっくりなキャラクターを作ることができるからです。自分のカメオの使用を許可すると、他人が自由に使うこともできます。
オープンAIのサム・アルトマンCEOも自らのカメオを自由に使うことを許可していて、彼の動画も氾濫しています。動画には「Sora」の透かしが入っているとはいえ、これらを消す技術もあります。フェイク動画が一人歩きする危険性もあるだけに、この企業のトップの振る舞いには嫌悪感を抱きます。
…… -
25面~30面 読者からのお手紙&メール(文責 矢野宏)
先発医薬品選ぶと
差額徴収あるとは
熊本県 横林政美
私たち夫婦も高齢となり、日々の生活に医薬品が欠かせません。毎月の受診のたびに処方箋を出してもらい、調剤薬局から薬を受け取る生活が続いています。以前、「お薬手帳」の処方薬記録を見た時、薬の下に「患者希望」と書いてありました。
そのままにしていましたが、後日、どうしても気になり、医療機関に勤務する知人に尋ねると、「同一成分で、ジェネリック医薬品と先発医薬品がある場合、先発医薬品を選んだ時、『選定療養対象医薬品』『患者希望』と処方箋に記入。先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の4分の1は患者が負担しなければならない。医療機関、薬局の収入になるわけではない」と教えてくれました。
私の「お薬手帳」を見ると、昨年10月から約5割の薬が「患者希望」と記入がありました。私が先発品を希望したのは、知人が「ジェネリック品を私は勧めない。健康のことを思うのなら先発品が良い」と言っていた記憶があったので、医師から尋ねられた時、「先発品」と言ったようです。差額代金の徴収があるとは思いませんでした。
私の処方箋を見ると、薬局でも販売の類似薬品が3割あります。類似薬品は約7000品目あるとのこと。今後、薬局から類似薬品の購入となると、保険外れの価格で購入することになるのでは。生活と健康を守り、維持するために、今の政権と決別が来年の課題と思っています。
(先発医薬品とは、最初に開発・承認・発売された医薬品、新薬のこと。特許満了後、他の医薬品メーカーが製造・販売する同一の有効成分の医薬品が「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」。効き目は同等と言われているようです。だとしたら、もったいないですよね)
国民と憲法尊重
田中正造たどる
東大阪市 多田一夫
「新聞うずみ火」12月号で「田中正造研究50年誌」が出版されたことが紹介されていました。私も職場の仲間たちと11月、栃木県佐野市にある田中正造さんの生家などを訪ね、その思想と行動を勉強してきました。正造さんは足尾銅山鉱毒事件の解決に生涯をささげ、明治天皇に直訴しようとしたことで知られる、反骨精神(反権力)の人物だと思います。
1890年、渡良瀬川の大洪水により、上流の足尾銅山から鉱毒が流れ込み、多くの住民が苦しみました。同年に衆院議員になった正造さんは国会でもこの問題を取り上げましたが、政府側は取り合おうとしません。96年には渡良瀬川沿岸が再び洪水被害に見舞われ、鉱毒被害に耐えかねた被害民は大挙して上京し請願を行います。正造さんは1901年10月に議員辞職し、12月に明治天皇の馬車へ近づき、直訴状を手渡そうとしましたが、警備の警官に取り押さえられました。当時、天皇への直訴は死刑になってもおかしくない重大な行為。この直訴状は、後に大逆事件で死刑になる幸徳秋水に依頼し書いてもらい、正造さんが補筆捺印したものだったそうです。
直訴に出た意図は、天皇の仁慈にすがるだけでなく、世論を喚起することにあったと言われています。実際、全国的な反響を呼び、被害地へ視察や住民救済の支援が続出しました。世論の高まりを受け、政府は正造さんが求めた足尾鉱山の鉱業停止ではなく、下流の谷中村(やなかむら)を廃村にし、遊水池にする治水案でした。
当時と変わらぬ現代の社会状況が重なります。高市政権は防衛費「GDP比2%」を2年前倒しで実現しようとしています。憲法9条に基づく「平和国家」を蔑ろにし、税金のむしり取りは許されません。ましてや、「防衛国債」の発行も取り沙汰され、防衛費増額に前のめりです。
正造さんは、「国益が優先される状況であっても、国民の権利と国の基本原則の憲法や法律が軽視されてはいけない」と主張しました。また、「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」という言葉を残しています。その思想・行動を学び、平和な世の中、人権が優先される社会の実現を目指し、これからも声を上げ続けようと思います。
(来年の「田中正造カレンダー」の言葉は「農民ハ愚でも 百年の計を思ふ 知識ある官吏ハ一日の計のみ」。官吏は自分の地位しか頭にないとは、今も変わりませんね)
……
-
26面 車いすから思う事 東京忘年会に参加して(佐藤京子) ※全文紹介
朝夕の冷え込みが強くなってきた。もう年の暮れ。世の中は忙しくなり、街には人があふれている。混んでいる歩道を電動車いすで自走していると、自転車や電動スケートボードが遠慮なく向かってくる。衝突だけは避けたいものだ。
新聞うずみ火の忘年会が12月13日、新宿御苑に近い中華料理の店「隨縁別館」で開かれ、今年も参加した。アルコールは飲めないが、もう10年以上になる。この店が電動車いすでの入店もOKで、介助犬も快く受け入れてくれるからありがたい。
ただ当初、トイレの心配があり、近くにある公共施設や病院、コンビニエンスストアに当たった。運が良く隨縁別館の並びにあるコンビニのトイレが車イスでも利用できることがわかり、ホッとしたのを覚えている。ここ数年、コンビニの新店舗が開店する際、車イスでも利用できるタイプが推奨されているようだ。
確かに、街の中のバリアフリー化は思っていたよりも進んでいる。電車の乗降時に必要な渡し板のシステムも、かつては1時間以上も待たされることがあったが、今ではスムーズに渡ることができる。都営地下鉄の改装されたホームは段差がないように設計されている。バスもまたしかり。どのバスも車体が左側に傾斜してスロープ出してくれる。2004年アテネパラリンピックでギリシャを訪れた際、車いすの人でも乗りやすくするため、バスが傾斜することに感激していたが、この20年ほどで、日本でもそうなった。ただ、バスの中は広くないので、混んでいると次のバスを待つしかないが……。
さて、今年の忘年会。残念ながら読者の参加が減ってきている感じがする。忘年会そのものが一般よりも少し早い開催だからかもしれないが、それでも初めて会う人もおり、輪の広がりを感じる。矢野さんと栗原さんとも1年ぶりの再会。元気な姿に安心した。まずは、新聞うずみ火創刊20周年に乾杯。今年も1年無事に過ごせました。
それでは、お体に気をつけてよいお年をお迎えください。
-
28面 絵本の扉「たべて うんこして ねる」(遠田博美) ※全文紹介
ユニークで衝撃的なタイトルですが、生物が生き続けるためには絶対に必要不可欠な事柄です。
表紙と裏表紙を広げると、テーブルにお皿が3枚。そこにはおいしそうな手作りハンバーグ。フライドポテトとニンジンとブロッコリーものっています。箸でつまんでいるお皿が一つ、もう一皿は小さめのフォークとスプーンでハンバーグが半分食べてあります。みそ汁やご飯茶碗もあり、3人家族の食卓か? とお腹がなりそうになりながら読み始めます。
見開きは俯瞰で見た夜の街。次のページは、ズームアップされた団地の窓から家族の様子が。さらにページをめくると、ハンバーグを食べている男の子と両親の3人家族です。
「たべて」とひと言だけ書いています。この家族は、表紙の食卓の家族でしょう。次のページに「うんこして」。こちらを向いて踏ん張る男の子。次は「ねる」ふーん。そうなりますか……の描写です。次々とページをめくるたびに、「たべて」うんこして」「ねる」のくり返しです。
ページのそこここに次のヒントや結果が見られるのに気づくと、ページを戻って確認して次へ行きたくなります。子どもたちが集う公園にはあの家族もいます。そして学校の様子から放課後へと続きます。
団地にいた男の子には妹と赤ちゃんがいたんだ。この子は1年生かも……。そんな発見が楽しくなってきます。学校のトイレでは本当はうんこしにくいんだよね、わかるよ。 最後のページに近づくと、「さようなら―」とあります。雨の中引っ越しする車で涙する男の子。友達も傘をさしてマフラーして寒いのに見送りに来てくれています。車の後部座席には寄せ書きが……。泣きながらも、サービスエリアでおむすびを「たべて」「うんこして」子どもたちは引っ越し先に到着するまでに「ねる」。引っ越し先で笑顔で出迎えてくれたのは誰と誰だったと思いますか?
翌朝、「たいよう ぴっかーん」。涙の別れから笑顔の朝です。そこで「たべるんだ」になりました。天井から見たような食卓には目玉焼き。お箸を持つ手は何人でしょう? 焼き鮭、納豆、お味噌汁。みんなの笑顔が見えるようです。最後のページは、黄色い菜の花畑を見ながら黄色い帽子を被ったお兄ちゃんと妹の後ろ姿。きっと笑顔ですね。
作者のはらぺこめがねさんは、夫婦のユニットです。2人はデビューから一貫して食と人をテーマに創作活動を続けています。ぜひ、他の作品も「美味しい」ので味わってみて下さい。
-
30面 編集後記(矢野宏) ※全文紹介
2025年は「治安維持法」が制定されて100年。廃止までの20年間は「戦争と弾圧」の時代だった。共産主義者だけでなく、「国体護持」の名のもとに、平和や自由、民主主義を求めた多くの人が弾圧され、命を奪われた。国に謝罪と賠償を求める人権団体「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟」の調べによると、逮捕者数十万人、警察署で虐殺された人93人、拷問・虐待・病気などで獄死した人は1617人を数えたという。
敗戦後もこの悪法は言論弾圧に使われ続ける。「人生論ノート」などの著作で知られる哲学者の三木清も出獄を許されず、1945年9月に獄死した。治安維持法を撤廃したのは日本政府ではなく、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)だった。失効から80年たった今も政府は「当時、適法に制定された」と謝罪はおろか、検証すらしようとしない。
日本で廃止された治安維持法は、韓国で「国家保安法」として継承された。75年11月22日、留学中だった在日韓国人の学生らが「北朝鮮のスパイ」にでっち上げられ、9人が死刑判決を受けた。大統領直属の諜報機関KCIAによる拷問は熾烈を極め、事実ではない自白調書を書かざるを得なかった。執行されなかったのは、日本で結成された「救う会」の救援運動が大きかった。事件から半世紀、ソウルで開かれた集会に李在明大統領から寄せられたメッセージにこんな一文がある。「政府は国家権力が一瞬たりとも国民の上に君臨することがないよう、厳しい責任意識を持って必要な措置と実質的な支援を続けてまいります」
一方、「悪法もまた法なり」と開き直る日本政府は、現代の治安維持法と言われる「スパイ防止法」の制定を目指している。日本版CIAも設置するという。一番リスクにさらされるのはスパイではなく、問答無用でスパイ扱いされる私たち一般市民である。
-
31面 うもれ火日誌(文責 矢野宏)
11月11日(火)
矢野、栗原 午後、新聞うずみ火が制作した大阪空襲証言DVD「パンプキン爆弾を知っていますか」をピースおおさかの森久子館長に手渡す。「学校に無料で貸し出し、平和学習に役立ててもらいます」
13日(木)
矢野 午後、滋賀県立膳所高校2年生360人の人権学習で「空襲とパンプキン」と題して講演。2011年から15年連続。
14日(金)
矢野 午後、元朝日新聞記者の阿久沢悦子さんが来社。創刊20周年を迎えた新聞うずみ火を取り上げたいと、「生活ニュースコモンズ」でインタビュー。
栗原 東京・永田町の参院議員会館へ。「島人の声を聞け!琉球弧の戦場化を許さない」シンポジウムを取材。
15日(土)
午後、創刊20周年記念のコラボイベント「釜ヶ崎歩き&懇親会」。案内人は居酒屋「グランマ号」店主の新井信芳さん。参加者からカンパをいただく。
栗原 午後、横浜市内で歴史学者、笠原十九司さんの講演会へ。
…… -
32面 うずみ火イベント 1月20日(土)講演「城が燃えた」&新年会(矢野宏) ※全文紹介
新年のスタートを飾る「うずみ火講座」は1月10日(土)午後2時半~大阪市北区のPLP会館で開催。「城と空襲」(西日本出版社)を出版した矢野が講師を務めます。
敗戦までの3か月間に当時国宝だった六つの天守閣――名古屋城、岡山城、和歌山城、大垣城、広島城、福山城が空襲で焼失・倒壊しました。難を逃れた姫路城や大阪城、四国の4県都の城のうち4城と空襲について紹介します。
会場まではJR環状線天満駅から南へ徒歩5分。読者1000円。オンライン500円です(希望者にはいつでも視聴できるURLをお伝えします)。
新年会は午後5時からの予定です。
-
32面 うずみ火イベント 1月31日(土)猪飼野歩き&懇親会(矢野宏) ※全文紹介
うずみ火創刊20周年記念のコラボイベント「猪飼野歩き&懇親会」が1月31日(土)に行われます。案内人は「まちの拠り所 Yosuga(よすが)」の足立須香さん。少々の雨であれば決行します。
午後2時、JR環状線「鶴橋駅」中央改札口に集合。街歩きをした後、買い物する自由時間も設けます。
定員15人(要予約)で、定員になり次第、締め切ります。参加費は街歩き1000円、Yosugaでの懇親会3000円(ワンドリンク付き)。
参加を希望する方は足立さんまで。
メール sugapan5889@yahoo.co.jp
-
32面 うずみ火イベント 3月1日(日)水野晶子さんの朗読会(矢野宏) ※全文紹介
フリーアナウンサー水野晶子さんによる朗読会は3月1日(日)午後2時~大阪駅前第3ビル地下2階の「RHYコンサートサロン 大阪梅田」で開きます。
ピアノ演奏付きの朗読で、1部は「田辺聖子 18歳の戦中日記」、2部は「天気予報と戦争~気象学者・増田善信さんの遺言」です。
参加費2000円。定員60人(要予約)で、うずみ火事務所までお申し込みください。
3月7日(土)は午後から「熊取6人組」今中哲司さんによる福島原発についての講演を予定しています。