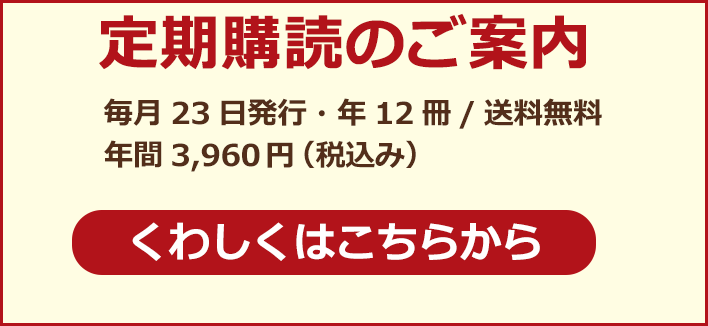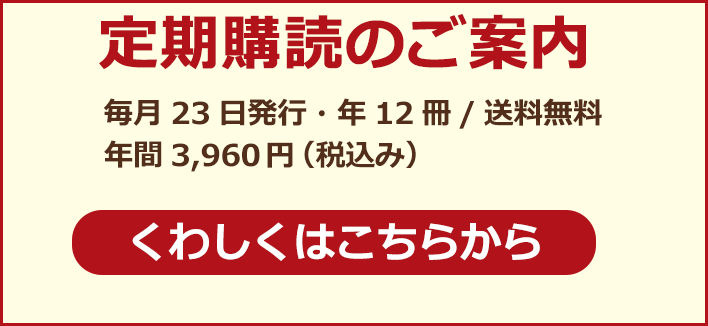新聞うずみ火 最新号

2025年8月号(NO.238)
-
1面~3面 参院選で極右政党台頭 外国人排除は認めない(矢野宏)
参院選は7月20日投開票され、自公両党が過半数維持に必要だった改選50議席に届かなかった。石破首相は続投の意向を示したが、衆参両院で少数与党になり、政権運営はさらに厳しさを増す。選挙戦の争点に急浮上したのが外国人政策。護憲勢力が伸び悩む中で、「日本人ファースト」を掲げた参政党が14議席を獲得した。排外主義や差別を正当化する主張を憂い、心痛めている人も少なくない。
7月17日午後、大阪ミナミでの参政党の街頭演説。オレンジのTシャツを着た陣営関係者、支持する聴衆の後方で「カウンター」と呼ばれる市民がプラカードを掲げている。「ヘイトスピーチするな」「インチキ政党にだまされないで」などと書かれたプラカードを手に抗議の声を上げる。
神谷宗幣代表が「彼らは共産主義者ですから」と言い放つと、拍手と怒号が飛び交い、一時騒然となった。
カウンターと呼ばれる市民による体を張った抗議運動は2010年代、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)による在日コリアンへのヘイトスピーチを封じようとする人たちが用い始めた。
和歌山市の在日コリアン2世、尹敏哲(ユン・ミンチョル)さん(73)は「参政党の『日本人ファースト』は、在特会によるヘイトキャンペーンの引き写し。いずれ『チョーセン人、帰れ』とのヘイトデモになって自分たちに向けられるのではないか」と危惧している。
「ありもしない『在日特権』へのやっかみを利用し、『日本人は苦しい思いをしているのに、外国人が優遇されている』と思い込ませ、諸悪の根源は外国人だと『敵』を作り出して不満を一気に向けさせて支持を得る。関東大震災の朝鮮人虐殺を思い起こさせる」
現在、日本で暮らす在留外国人は約376万8900人(24年末)と、過去最多を更新した。背景には深刻な人手不足がある。15年には1億2709万人だった日本の人口は25年6月の時点で1億2336万人と、10年間で約400万人減少。53年には1億人を切ると言われている。
参政党支持の18歳の女子学生は「日本は移民を受け入れ過ぎ。日本に住んでいる自分たちが大事にされていないように感じる。コンビニへ行っても店員さんが外国人ばかり。外国人による事件や事故も増え、住みにくくて怖くなってきた」と話す。
…… -
4面~5面 ヘイトデモ差し止め提訴 日本での生活 困難に(栗原佳子)
埼玉県南部の川口市や蕨市周辺に多く暮らすトルコ国籍のクルド人たちへのヘイトがここ数年、深刻化している。県外の右翼団体などが、クルド人排斥を訴える街頭宣伝を繰り返し、SNSには無断撮影した写真や動画がデマと共に拡散されている。ヘイト街宣を繰り返す加害者に対し、在日クルド人団体は、差し止めと損害賠償を求める裁判を起こした。
埼玉県蕨市。JR蕨駅にほど近い雑居ビルの一室に支援団体「在日クルド人と共に HEVAL」の事務所がある。
フロアでは母親と小学生2人の女の子が日本語のドリルに取り組んでいた。手助けするのはボランティア。4歳の末娘は学生らの手ほどきを受けながら、折り紙で七夕飾りをつくっている。毎週日曜日に開かれる日本語教室だ。
「きょうはサッカーの練習があるので、参加者が少ないんですよ」と温井まどかさん。
9年前、自宅近くの公園で遊んでいる幼い姉妹に声をかけた。平日の昼間だった。トルコ国籍のクルド人で、学校に通っていないという。就学できるよう学校にかけ合った。
夫の立央さんらと4年前、「在日クルド人と共に」を立ち上げた。略称のHEVALはクルド語で「友達」の意味。社会の一員である在日クルド人と共に未来を築きたいという思いを込めた。
日曜午前と午後に開く日本語教室。クルドの新年の祭り「ネロウズ」開催のお手伝い。医療などの相談など活動は幅広い。在留資格によって国民健康保険に加入できない人も多く、医療費は自己負担。午後の日本語教室に来た40代の男性は娘の入院で、高額の治療費を支払っていた。
…… -
6面~7面 在日女性に「いとこは死刑判決」 「市議投稿はヘイト」訴訟(栗原佳子)
大阪在住の在日コリアンの女性が、SNSの投稿でヘイトスピーチを受けたとして、大阪・泉南市議に対し損害賠償と投降の削除を訴えた裁判が大阪地裁(山本 拓裁判長)で審理されている。政治家が外国籍市民の個人情報をさらし、支持者らに攻撃をあおる「犬笛」型ヘイト。7月10日に本人尋問が行われた。
原告は大阪市のイベント制作会社「TryHard Japan」役員で、元朝鮮学校のオモニ会役員、李香代(イ・ヒャンデ)さん(59)。
大阪・泉南市の添田詩織市議(36)=自民=を相手取り、昨年5月、550万円の損害賠償と投稿の削除を求める訴えを大阪地裁に起こした。添田市議はX(旧ツイッター)上に、朝鮮学校への補助金復活を求め活動する李さんの複数の写真を投稿、「いとこは在日留学生捏造スパイ事件で死刑判決を受けた」などと書き込んだ。李さんのいとこは韓国の軍事独裁政権に「北のスパイ」とでっち上げられ、長い獄中生活を強いられた李哲(イ・チョル)さん。再審で無罪が確定している。
添田市議は2期目。昨年の市議選ではトップで再選した。Xのフォロワーは約8万2千人で、動画も配信。22年の沖縄県知事選では、候補者の玉城デニー氏を巡り、「沖縄を中国の属国にしたいデニー候補」「民族浄化されます」などとツイートしたこともある。
李さんが勤務する会社は泉南市の事業を請け負っている。代表は中国出身で、添田市議は週刊誌などで「多額の公金が中国系企業に〝ダダ漏れ〟している」と攻撃。同社は昨年2月、「ヘイトスピーチを受けた」として添田市議と市を相手取り、1100万円の損害賠償などを求め提訴した。
李さんに対する添田市議の差別的投稿が始まったのはこの直後。複数の役員の中で李さんだけが標的になった。
7月10日は第9回期日。本人尋問の山場で、初めて公開で行われた。
…… -
8面~10面 万博パビリオン「GL」日本法人 建ててなぜ違約金?(矢野宏)
大阪・関西万博の海外パビリオン建設に参入した業者のうち、少なくとも8社は発注元から工事代金の支払いを受けておらず、倒産の危機に瀕している。マルタ館の工事を請け負った関西の建設会社は年末年始、昼夜を問わず働き、万博の開幕に間に合わせたが、約1億2000万円が未払い。元請の外資系イベント会社に請求すると、「契約違反がある」と、逆に3000万円を請求された。男性社長(40)は「資金繰りがギリギリで、支援がないと乗り越えることはできない。このままでは参入した業者が連鎖倒産しかねない」と窮状を訴えた。
「万博のパビリオン建設を何とか助けてくれないか」
知り合いから依頼されたのは、昨年10月のこと。Aさんが二の足を踏んだのは「万博には関わらない方がいい」との業界のうわさを耳にしていたから。それでも、再三懇願され、「国家プロジェクトに少しでも貢献できるなら」と引き受けたという。
マルタ館は、自前でパビリオンを建設する「タイプA」。「万博の華」と呼ばれる海外パビリオンの中で建設許可が下りたのは一番遅く、着工したのは昨年12月。年末年始を挟み、万博開幕まで4カ月しかなかった。
元請は、フランス資本のイベント会社「GLイベンツ」(本社・東京都港区)の日本法人。骨組みの設置以外のすべてをAさんの会社が請け負うことになった。契約では、解体費も含めて工事費は約2億3000万円。「それでも利益は出ないと覚悟していた」という。
「工期がない中でリスクの大きい仕事でした。小さなパビリオンだから頑張れば間に合うと思いましたが、図面すらない。元請と現場で確認し、自分たちで図面を引いて作業を始めても、変更は日常茶飯事。進めたくても進められなかった」
GL側とのやり取りはすべて英語。通訳は外国人で、細かな意思疎通ができなかった。何度も投げ出そうと思ったが、すでに下請業者に声をかけ、社員を含め最大50人が働いている。元請と下請け業者との板挟みになりながらも、投げ出すわけにはいかなかった。
開幕が迫るにつれ、万博協会や大阪府からの圧力も強まってきた。現場に泊まり込み、朝から晩まで不眠不休で作業に追われた。Aさん自身、最後の1カ月で7㌔痩せたという。
「夢洲はアクセスが悪く、何もないところですから、一度現場に入ったら出られない。しかも寒い時期でしたから、凍えながらの作業でした」と振り返る。
…… -
11面~13面 沖縄戦フィールドワーク 集落も信仰の場も戦場に(栗原佳子)
「沖縄慰霊の日」前日の6月22日、元沖縄タイムス記者で琉球大学准教授の謝花直美さんの案内で、沖縄本島中部の中城村(現・中城村と北中城村)を起点にフィールドワークを行った。米軍が沖縄本島に上陸後、日米が激しい戦闘が繰り広げた地域。近年まであまり知られていなかった住民被害の実相もわかってきたという。
今回のフィールドワークは日本軍が陣地を構えた宜野湾―中城―西原ラインの東側部分を半日で回るというもの。西側部分をたどった昨年に続く中部のフィールドワークだ。 「第32軍首里撤退後の南部を中心に沖縄戦を考える視点から、近年は地域史編集の深化と戦争遺跡への注目で、中部でも新たな視点による平和学習が可能になってきた」と謝花さんは指摘する。
80年前の1945年4月1日、米軍は現在の北谷町から読谷村にかけての西海岸から沖縄本島へ上陸。約3カ月にわたる日米両軍の激しい地上戦が行われ、多くの住民が犠牲になった。米軍の兵力は後方部隊も含め約55万人。対する日本軍は防衛招集も含めて約10万人と圧倒的な兵力差があった。第32軍の作戦参謀だった八原博道は『敵が嘉手納に上陸する場合は、南上原東西の堅固な陣地壕に拠り、これを迎え撃つ、すなわち戦略持久する方針」を立てた。
日本軍は上陸する米軍にほとんど攻撃せず、米軍は2日午後には中城湾に到達。沖縄本島を南北に分断し、主力は軍司令部がある首里方面を目指した。対する第32軍は首里との間に三つの防衛線を設定した。宜野湾村と中城村を結ぶ第一防衛線は最初の激戦地になった。
那覇からマイクロバスで約30分。中城城跡(なかぐすくじょうあと)へと向かう。中城村の西側は宜野湾市から続く大地で、城はその高台に築かれた。15世紀に尚巴志(第一尚氏)とともに三山を統一した護佐丸(ごさまる)が居城とし、2000年に世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の一つとして知られる。
…… -
14面~15面 再審無罪確定の元看護助手 検察に勝つ難しさ(粟野仁雄)
23歳の女性が刑事に恋し、その刑事がこれを逆手に取った稀有な冤罪事件の「湖東記念病院事件」。西山美香さん(45)が県と国を訴えた4年越しの国賠訴訟の判決が7月17日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は「嘘の自白を強く誘導する違法捜査があった」「西山さんが自発的に話したかのように供述調書を作った」として県に約3100万円の支払いを命じた。しかし、国の責任は「自白は信用できると認めたことは当時の捜査資料から合理性があった」と免責した。
記者会見した西山さんは「県に勝ったのはうれしかったけど、国に勝つのは難しいんだなあと思った」と話した。
原告代理人の井戸謙一弁護士は「鑑定人が男性患者は痰を詰まらせて自然死した可能性を指摘していたのに、県警がそれを隠して検察に送致しなかった違法が認められた。しかし呼吸器が外れた時に鳴るブザーの消音装置の扱い方は他の看護師も知らなかったことを検察はわかっていた。西山さんが音が再び鳴る1分前に押すことを繰り返したとする警察調書がおかしいことはわかっていた。検察に落ち度がないはずはない」と、即刻控訴したことを明らかにした。
原告側は「西山さんは軽度の知的障害などで相手に誘導されやすい供述弱者だった」と主張していた。井戸弁護士は「この冤罪事件は、西山さんが刑事に恋し、それを利用した誘導で自白調書が作られたことが一番の問題だったのに、判決が全く触れなかったことはおかしい。大阪高裁の再審開始決定もそこが大きな理由だったはず。控訴審ではそこを中心に訴えてゆく」と話した。
2003年5月に滋賀県東近江市の湖東記念病院で72歳の男性患者が死亡した。西山さんが呼吸器のチューブを外して殺害したとして起訴された。「職場に不満があり、困らせようと思った」が動機とされた。西山さんは殺人罪による懲役12年が07年5月に確定し、17年まで和歌山刑務所に満期服役した。
…… -
16面~17面 ヤマケンのどないなっとんねん 歴史の事実見つめよう(山本健治)
今回の参院選では、アメリカのトランプ大統領による独裁政治、思いつきとしか言いようのないバカバカしい関税攻勢と外交にどう対応するか、相も変わらず侵略を続けるプーチン大統領とロシアに対し、世界の平和と安定を取り戻すため、いかにして一刻も早く停戦・撤退させるような外交努力を行うか、またパレスチナ人を皆殺しにするようなイスラエル・ネタニヤフ首相の残虐な行為を止めさせるよう働きかける外交をどう展開するか、また自国の核保有を棚上げしながらイラン攻撃をしたトランプ、ネタニヤフに対し、本当の意味での核廃絶を考えさせることも大きなテーマであった。
しかし、いつもそうであるように、選挙は結局、国内や選挙区で大きな問題になっていることが争点になってしまう。米の価格の急騰をはじめとする諸物価の上昇にいかにしてブレーキをかけるか、30年にわたって止まってきた賃金を何とかして毎年上昇するようにし、みんなの所得を増やし、負担を減らし、格差と貧困を解消して、何としてもみんな生活レベルを引き上げ、幸せを実現するようにするといった国内的課題に議論が集中するのが現実である。
今回は、戦前の日本が犯した過ちを認めない人たち、歴史をねじ曲げる政党と候補者がこれまで以上に立ち、堂々と民族排外を主張し、憲法9条を変え、自衛隊を軍隊化し、戦争する国家とし、基本的人権を制限する緊急事態条項の新設=戒厳令の導入を主張するとともに、防衛費を増額させることが当たり前のように語ったことが大きな特徴ではないか。
読売新聞社が行ったアンケート調査では、憲法を変えることに賛成、どちらかといえば賛成は50%を超え、反対、どちらかといえば反対は30%、自衛隊の根拠規定を改めるなどを行うべきだと答えたの81%だった。我々反戦平和を叫び、憲法を守り、根付かせなければならないと考える者にとっては大きな懸念である。 今年は、太平洋戦争末期の沖縄戦で9万人の日本軍人・兵士が亡くなり、13万人を超える沖縄県民が亡くなって80年である。沖縄戦の後、米軍は日本本土を執拗に空襲し、東京、大阪、名古屋など大都市のみならず地方都市も空襲して60万人が亡くなり、1000万人以上が罹災した。そして8月6日に広島、9日に長崎に原爆が投下され、両市は壊滅し、30万人を超える人が亡くなり、それを超える市民が放射能に侵され、全身にやけどしたり、がんや内臓障害で苦しみ、亡くなった。生き残った人も、今なお後遺障害で苦しんでいることは誰もが知っていることだろう。その果てに敗戦したことを忘れてはならない。
…… -
18面~19面 世界で平和を考える アサド政権崩壊の裏側(西谷文和)
4月14日、ダマスカスから北上し、シリア中部のホムスに向かう。シリアは高速道路が整備されていて快適なドライブ。ホムス手前で橋が空爆されて通行不能になっている。これはロシア軍によるもの。シリアの反体制グループがアサド政権打倒を目指してダマスカスに迫ってくるのは確実な状況。アサドを守ろうとしたロシア軍のアシストだ。しかし、ロシアはウクライナ戦争で手いっぱいなので、これ以上のサポートはできなかった。あっけなくダマスカスが陥落してアサド政権が倒れたのは「ロシアが面倒見きれなかった」ことが主な原因だ。
ホムス到着。街は真っ暗、ネットは通じず、湯も出ない。4月のシリアはまだまだ寒い。「暗闇の4つ星ホテル」で凍えながら眠る。
翌朝、「太陽はいいなー、明るいなー」と外へ。ホテルの正面がホムス大学で、戻ってきた学生たち、パンを売る露天商、通勤通学バスなど普通の日常生活があった。何よりも平和が一番だ。
通訳モハンマドとホムス郊外のクサイル市へ。ここはレバノンとの国境の街で、多くの民家が瓦礫になっている。「アサド軍が?」「それもあるけど、主にヒズボラの地上部隊」。この街はレバノンから侵攻してきたヒズボラ地上部隊によって徹底的に破壊されていたのだ。
「あそこで学んでいたよ」。 モハンマドが壊れた学校を指差す。この街は彼の故郷。破壊された商店街の前で車を止める。「この家で叔父が洋装品を売っていた。路地を挟んで奥の家が俺の実家だ」
実家に足を踏み入れる。ガチャ、ガチャ、ガチャ。まだガラスの破片が散らばっているので、歩くたびに音がする。「アサドの空爆で?」「いや、ヒズボラのロケット弾で。ヒュンヒュンとね」。両手にロケット弾の破片を持ったムハンマドが、破片を左右に交差させる。ヒズボラはこの街を取り囲み、前後左右から嵐のように撃ってきたという。屋根がなくなった2階へ。「ここが俺の部屋だった。家具もパソコンもベッドもみんな奪われた。でも今はハッピーだよ、13年ぶりに戻れたんだから」
台所に木が生えている。ロケット弾が台所のタイルに穴を開ける→そこにタネが飛んでくる→誰もいない部屋で成長する。1㍍近く育った樹木を見て、13年の歳月を感じる。
クサイル市の住民が抵抗をあきらめて逃げたのが2013年夏。約5000人が徒歩でトルコ方面へ。三日三晩歩き続けた逃避行。その時約300名がヒズボラに銃殺されたという。アサド政権が崩壊して4カ月、まだこの地域には電気も水道も復旧していないので、住むことはできない。この時点ではまだ欧米による経済制裁が続いていたので、外国の建設会社も入っていない。アサド政権が崩壊したのだから、早く経済制裁を解いて、国際的な支援を集中させて復興させねばならない(1カ月後に経済制裁解除)。
…… -
20面~21面 フクシマ後の原子力 問われる日本国憲法(高橋宏)
6月23日、アメリカがイランの核施設3カ所を空爆した。トランプ大統領によれば、イランの核開発能力を破壊し、核の脅威を取り除くことが目的だったという。事の発端は6月13日、イスラエルが突如イランの核施設や弾道ミサイルの開発拠点などを攻撃したことだった。これに対してイランが報復を開始し、中東の軍事強国同士の紛争がエスカレートしつつあった。
これまで、核開発を「平和利用」と主張してきたイランに対し、欧米各国やイスラエルは核兵器保有を目指すものだと指摘し、経済制裁などで圧力を強めてきた。2015年、欧米など6カ国とイランは「核合意」を結び、制裁解除と引き換えにウランの濃縮度に上限が設けられていた。だが、第1次トランプ政権はこの合意から一方的に離脱し、イラン産原油の全面禁輸など制裁を再開したのだった。
ウランを原発の燃料として使用する場合、3~5%に濃縮する。核兵器として使用するには90%以上に濃縮する必要があるが、20%以上の「高濃縮ウラン」は核兵器の材料になり得るとされる。核合意の際、IAEA(国際原子力機関)の規程より厳しく、濃縮ウランの貯蔵量を300㌔以下、濃縮度は3・67%に制限された。イランは、濃縮施設の遠心分離機の稼働数の削減などを含めて、これを受け入れていた。
アメリカの合意離脱後、イランは核開発を続け濃縮度を60%まで引き上げたとされる。第2次トランプ政権となった今年4月、イランとの核交渉が再開され、6月15日には最初の協議が開かれる予定だった。だが、イスラエルのネタニヤフ首相は対話による解決を望んでおらず、攻撃に踏み切ったとされる。事態を泥沼化させないためにも、アメリカの影響力の行使が期待されたが、トランプ大統領もまた武力によって解決する道を選択したのだった。アメリカの参戦を要請していたネタニヤフ首相が「大胆な決断」と讃えたことは言うまでもない。
…… -
22面 生活保護訴訟 最高裁判決 厚労省から謝罪なし(矢野宏)
国が物価の下落を反映するなどとして、生活保護の支給額を2013年から段階的に引き下げたのは違法だとした6月27日の最高裁判決。厚生労働省が根拠とした物価下落を反映する「デフレ調整」は「裁量の範囲の逸脱、乱用があった」と判断した判決を学び、今後の運動に生かしていく学習会が7月6日、大阪市内で開かれ、原告の受給者や支援者ら50人が出席した。
厚労省は、08年のリーマン・ショック以降に物価が下落したなどとして、13~15年に3回に分け、生活保護のうち日常生活のための「生活扶助」の基準を平均6・5%、最大10%引き下げ、計約670億円を削減した。
背景には受給者バッシングがあった。12年に人気漫才師の母親が生活保護を受けていたことが明らかになり、制度のあり方が問題視された。「受給世帯より苦しい生活を強いられている人もいる」などの主張が広がり、同年12月の総選挙で「生活保護費10%引き下げ」を公約に掲げた自民党が大勝し、政権を奪還する。
…… -
23面 経済ニュースの裏側 「郵政改革」(羽世田鉱四郎) ※全文掲載
歴史 我が国の郵便制度は、1871(明治4)年に前島密が中心となって設立。全国の配達網を確保するため、財源のない政府は地域の名士や地主に土地と建物を提供してもらう。これが小・中規模郵便局の起源。戦後、局長は転勤もなく、世襲が大半を占め、みなし国家公務員となって2007年の郵政民営化まで続きました。
現在は、親会社が日本郵政で、子会社に日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命があります。
全国郵便局長会 郵便局の数は2万4188局(6月3日現在)。大雑把ですが、大規模局1200局、小規模局1万9000局、簡易郵便局4000局。この大規模局と小規模局で全国郵便局長会(以下全特)を構成。全特は任意団体ですが、事実上、日本郵政を支配しています。全特は、参議院に2人(自民党)の組織内議員を送り込み、既得権の保持と選挙対策に大きな力を発揮しています。
郵政民営化の挫折 デジタル化の影響もありますが、郵便事業は不振を極めています。各種手数料を再三の値上げ、土曜日の配達業務の停止(20年11月)、配達期限の遅れも容認し、不祥事もあり小口貨物からの撤退も。変わらないのは郵便局の数だけ。維持費は年間約1兆円で、7割は保険と銀行業務から捻出。
営業現場はノルマを消化するため、年賀状などの自腹購入や生保などの詐欺契約といった不祥事が目立ちます。05年の郵政選挙で当時の小泉内閣が圧勝し、民営化に踏み切り。その後も、非正規雇用を導入。背景には、米国の「対日年次改革要望書」があります。
米国の年次改革要望書 1993年、宮沢首相とクリントン大統領の会合が始まり。日米の相互発展を目的とするが、実態は米国の国益追及から、内政干渉の強い要求です。日本の大手メディアは一切触れず。また当時の竹中平蔵・郵政民営化担当大臣は「そういった要望書は見たことがありません」とシラをきる始末。その結果、300兆円の運用資金が、米ドル債購入や対外債務の補填に充てられました。2009年、民主党の鳩山内閣が、日米規制改革委員会を廃止し、年次改革要望書も取りやめ。余談ですが、独自の資源外交を模索した田中角栄や鳩山由紀夫ら、米国の意向に逆らう政治家は対米重視の勢力(外務省など)や米国により、スキャンダル噴出という形で潰されます。A級戦犯から解き放たれた岸信介とは好対照。
対策(私見) 根本の解決は、郵便局の集約・効率化にあります。コンビニや小規模商店などへの業務委託も必要。ただし、全特の猛烈な抵抗があり、実現は困難を極めるかと。その他、高齢化、過疎、労働市場の流動化など現実に即し、郵便事業のニーズの掘り起こしも不可欠でしょう。①午前10時から午後3時、地域に精通した正社員の主婦が配達を請け負う②シルバー人材が郵便物の回収業務や土曜、日曜、時間外の配達を担当③過疎地域では鉄道やバスなどをフル活用し、小口貨物を中心に、地域の物流ニーズを掘り起こす④営業ノルマで頓挫した「みまもりサービス」も欠かせません。
参考 「ブラック郵便局」(塩田武士)「新潮社」
-
24面 会えてよかった 比嘉博さん⑧沖国大米軍ヘリ墜落事件に対応(上田康平)
沖縄国際大学に米軍ヘリ墜落
2004年8月13日14時18分、米
軍ヘリが沖縄国際大学(以下、沖国
大)に墜落した。このヘリはテスト
飛行を終え、普天間飛行場へ戻ろう
としていたのである。私はこの墜落
を大阪で知り、1カ月後に開かれた
抗議の宜野湾市民大会の後だったが、
沖縄に来て、空港からすぐ沖国大に
向かい、墜落した米軍ヘリに傷つけ
られ、黒く焦げた大学1号館の壁を
見た。(今、壁は撤去されて、一部
〈右の写真〉が保存されている)。
そして毎年8月13日に沖国大で開
かれる集会には沖縄に住みだしてか
ら、何回か参加し、私なりの抗議の
意思表示をしていた。また普天間基
地包囲行動にも一回、参加した。
普天間基地問題や沖国大ヘリ墜落
事件に向き合ってきたお二人に取材
その後、米軍ヘリの部品が保育園
の屋根の上で見つかったり、1週間
もたたないうちに、同型ヘリの窓が
小学校の校庭に落下。これら普天間
基地に由来する問題は新聞で読んで
いたんだけれど、24年
になって、これらに向
き合ってこられたお二
人に直接、お話を聞か
せていただいた。
5月に宜野湾市平和
な空を守る条例制定請
願運動に市民のみなさ
んと取り組まれた憲法
学者の小林武さん。そ
してもうお一人は比嘉
博さんである。
「沖国大ヘリ墜落から20年を振り
返るパネルディスカッション」で
出会う
8月、新聞でこの「パネルディス
カッション」を知り参加。比嘉さん
はパネリストとして参加されていた。
主催は第3次普天間米軍基地から
爆音をなくす訴訟団。比嘉さんは、
「当時、宜野湾市基地政策部長とし
て携わった事」と題して発言。地位
協定の改定と記録の保存を訴えてお
られた。
これから、取材と当日配布された
比嘉さんの資料「各機関のヘリ事故
への対応状況」、新聞記事などで、
この米軍ヘリ墜落事件について、そ
してその後に地位協定改定と記録保
存についての比嘉さんの訴えを書い
ていきたい。
そもそも普天間飛行場とは――
普天間飛行場は住民の土地を
強制接収してつくられた
普天間飛行場は、沖縄戦で沖縄を
占領していった米軍が避難していた
集落の住民の住宅や田畑を強制接収
し建設したのである。
「問われる沖縄アイデンティティ
とは何か」沖縄国際大学沖縄法政研
究所編8、9㌻によると、戦前、宜
野湾村の中心地であった集落を含む
3集落が完全に、さらに3集落も大
部分の土地を奪われた。
そして、この普天間飛行場内外で
墜落・落下事故も起こっている。同
書12、13㌻に1960年から94年に
起こった事故の写真が掲載されてい
る。 (つづく)
-
25面 日本映画興亡史 本気で転向した監督(三谷俊之)
熊谷久虎という映画監督がいた。1904(明治14)年、大分県中津市生まれ。25年、日活(大将軍)撮影所に入社。 田坂具隆の助監督に就いた。30年に監督昇進、青春モードの『恋愛競技場』でデビュー。日活多摩川撮影所に移り、「若き日の石川啄木の自由主義的教育への情熱に拍手した清冽な佳作」(佐藤忠男「日本映画史Ⅱ」)と評される『情熱の詩人啄木』を監督。次に「戦前の社会派リアリズムのひとつの頂点」(前出)といわれる『蒼氓』を発表。 翌年、東宝に移籍した熊谷は森鴎外の『阿部一族』を映画化。封建制度下の殉死をテーマに、武士道の非合理を痛烈に批判した。これらの作品によって、熊谷はリベラルで旺盛な批判精神の持ち主だと思われた。
しかし、日中戦争が始まると、大きく変貌する。29年の『上海陸戦隊』は、上海の日本租界を数倍の兵力の中国軍の猛攻から防衛した上海陸戦隊の戦いを描いた。全くの戦争賛美で、それまで彼の批判精神や自由への意志は姿を消してしまった。その転身ぶりに人々は戸惑うほどだった。佐藤は述べる。
「ある人々は、戦争が始まって戦争協力映画をつくるよう求められると、特に積極的というわけではなく、生活のために止むを得ず、あるいは戦争に反対する特別な信念もないままに参加した。しかし熊谷久虎は本気だった。この映画のあと彼は、元左翼のインテリ兵士が軍隊で鍛えられて、農民出身の批判精神皆無の忠実なもう一人の兵士と同じように愛国的な兵士になっていくという『
指導物語』を残して映画界を離れ」た。
映画界を離れた熊谷は何をしたか。国粋主義団体「すめら学塾」(すめら塾、皇塾とも)を結成、リーダーとして政治活動に没入する。これがトンデモ右翼思想だった。
世界最古の文明を築いたシュメール人が古代日本に来て、神武天皇をいただいて降臨したとか、日本人とユダヤ人は、祖先を同じにする「日本シュメール起源説」。日本人とユダヤ人は祖先が同じでシュメール人の末裔だという「日ユ同祖論」。敗戦時には日本の無条件降伏を不服として、九州に天皇・皇族を招致し独立国家を建て、米軍と徹底抗戦するなどという極愛国思想にのめりこんだ。
それだけではない。「伝説の女優」といわれ、小津安二郎監督の名作などに出演、戦前・戦後の銀幕に燦然と輝いた原節子の生涯にも熊谷の存在があった。彼女の姉の夫、つまり義兄が熊谷だ。彼は原の仕事や恋愛などにも介入したといわれる。
…… -
26面 坂崎優子がつぶやく 「冬でも強い紫外線」
「オーストラリアに行って」の2回目です。旅行準備では、日よけ対策を特に重視しました。オーストラリアの日差しはきついと聞いていたからです。実際シドニーは初冬だったにも関わらず、肌がじりじりする日差しでした。
なぜこうも紫外線が強いのか。オーストラリア大陸の上空は紫外線を吸収するオゾン層が薄いからだそうです。南極のオゾンホール(オゾン層がうすくなり穴が開いたように見える状態)が顕著な例ですが、南半球が特に深刻なのは地形的なことがあるようです。
このためオーストラリアでは、オゾン層を破壊するフロンガスの使用を早くから禁止し、1987年の国際的な条約にも早々に調印しています。日本でもフロン類を使用している家電の回収が義務付けられたこともあって、「フロンは地球環境に良くない」ことが浸透し、ノンフロンの製品開発も進みました。
2023年1月に世界気象機関が、「現在の政策が維持されれば、オゾン層は南極では66年、北極では45年、その他の地域では40年ごろまでに、オゾンホールが出現する前の1980年の値に回復すると予想される」と公表しました。世界的に取り組みが続けられた成果です。地球環境問題というと暗い話題が中心になりますが、こうした希望が持てる話も取り上げ広めていくことが大事です。
オーストラリアでは日々の紫外線対策も国を挙げて行っています。というのも70歳までに3人に2人が皮膚がんと診断されているからです。毎年、2000人以上が皮膚がんで亡くなっています。そこで80年代に「サン・スマート」プログラムが導入されました。合言葉は「スリップ・スロップ・スラップ・ラップ」で、「長そでのシャツを着よう」「日焼け止めを塗ろう」「帽子をかぶろう」「サングラスをかけよう」です。
ただ私が旅行中に見た限りでは、現地の大人でスローガンを守っている人は少なく思えました。日焼け止めは塗っているのでしょうが、帽子やサングラス姿はほとんど見かけなかったからです。もともとこのスローガンは子どもたちを守るために誕生しました。子どもの時に大量の紫外線を浴びることが将来の健康被害リスクを高めるからです。子どもは帽子をかぶらなければ外で遊べません。野外活動で来ていた子どもたちの集団を何度か見かけましたが、みんな帽子をかぶっていました。日焼け止めはもちろんのこと、衣服にも紫外線を防ぐ機能があるものが多く、ラベルにはその指数が明示されています。
…… -
27面~30面 読者からのお手紙&メール(文責 矢野宏)
日本人ファースト
参政党の憲法草案
大阪市 小泉雄一
新聞うずみ火7月号の「うもれ火日誌」で、定岡由紀子弁護士が「来月は参政党の憲法草案についてやりましょうか、かなりひどい内容です」と提案されていたのを拝見しました。6月27日の「憲法BAR」はさぞかし楽しい議論が花咲いたことでしょう。参政党が憲法草案を制作しているとは知らず、私もネットで調べて確認しましたが、「国政に議席を持つ政党が作成した内容か」と失笑してしまいました。
御立派な前文ですが、四つのパラグラフでそれぞれ誤りがあるように思います。「伝統文化を継承し産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた」としていますが、現在そのような調和が皆無となったために参政党のような政党も誕生できた。天皇を中心に公権力として政治の姿を憲法秩序・国体であるならば、この国の主権者は誰なのか。国民の生活確保のために公益を守り強化する。個人の権利よりも公益の権利が優先する周回遅れの観念。最後のパラグラフでは各国の歴史や文化を尊重して共存共栄をし、恒久の平和の実現に貢献する。この崇高な精神のどこから「日本人ファースト」が叫ばれるのか。
文字の使用についても意識して使い方を変えている。公益の権利については「利」を用いながら個人の権利については、一般では使用されない「理」を用いている。個人の理は公益との整合性を十分に考えながら権利を主張することを根底に据えているようだ。
参政党はカラーがオレンジ色で党首は常に朱色のネクタイを締めている。私の勝手な理解であるが、儒教の先鋭的な朱子学が根底にあるのではないのか。儒教は支配者の論理「民は知らしむべからず依らしむべし」が基本である。国民参加と言いながらそのような憲法内容ではないのか。
過去の戦争の総括を曖昧にし、民主主義の重みも理解しないまま、このような憲法草案をつくる政党の出現を見ました。過去の戦争も「日本人ファースト」と、アジアの中で自国だけ幸せになろうとした結果でした。その政党に喝采が集まる現実。百年たってもこの国は成長しない現実を受け入れなければならないことなのか。
(小泉さんがおっしゃるように、6月の「憲法BAR」は参政党の憲法構想案で大いに盛り上がりました。「国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」とか「国民は、子孫のために日本をまもる義務を負う」など、明治憲法の復古版ですね。安倍政権を支持していた「保守岩盤層」が参政党支持に回っている結果だと思いますが、由々しき事態にならねばいいのですが……)
…… -
28面 車いすから思う事 社会を映すトイレ(佐藤京子) ※全文掲載
車いすドライバーや小さな子どもを連れた人などが使う、広めのトイレ。あなたは何と呼んでいますか。「多機能トイレ」「多目的トイレ」「車イス用トイレ」「バリアフリートイレ」などと多種多様。いったい誰が、何のために名付けたのか。
かつては「障害者用トイレ」とか「車いす用トイレ」と呼んでいた。昔はトイレ問題が壁となり、外出できない障害者が多かった。その問題を解決すべく、使いやすいトイレが必要だと考えられるようになった。「車イス用トイレ」は、移動に制約のある人を念頭に置いた名称だったが、必ずしも車イス利用者だけのための空間ではない。実際に、おむつ交換ベッドなどが増えていき、人工肛門やぼうこうをつけている「オストメイト」も利用できる「多目的トイレ」や「多機能トイレ」へと呼び名が変わっていった。背景には2006年に施行されたバリアフリー法があったようだ。
だが、「多目的トイレ」といわれると、誤解する人もあらわれ、「女性が化粧をする目的で使用していた」といった声もあった。多目的という名称のため、本来、必要としない人も使用していたのだ。さらには、トイレの多機能化に伴い、利用者が増え、なかなか入れない人が増えていることもあり、国は21年3月、「多機能」や「多目的」などの名称を使用しない方針を示し、「バリアフリートイレ」との呼び名を推奨している。確かに、これなら高齢者や小さな子どもを連れた人も安心して使えるのではないか。どこまでが利用対象なのか、迷うこともないだろう。
とはいえ、中で食事をしたり、女子高生が身だしなみチェックをしたり。先日も、トイレからなかなか出てこず、ガサゴソと荷物を整理する音が聞こえていた。
順番待ちをしながら、ふと考えた。この空間が必要な人のことを、どれだけの人が考えているだろう。バリアフリーという本来の趣旨を外れた使い方も少なくない。それでも、誰もが少し譲り合う気持ちや配慮を持つことで改善されるはず。トイレの呼び名一つでも、社会の価値観や配慮が映し出されていると思う。
-
29面 絵本の扉「やくそく」(遠田博美) ※全文掲載
児童文学作家の那須正幹さんの遺作『やくそく』の副題は「ぼくらはぜったい戦争しない」です。
表紙には、主人公で語り手でもあるぼく「トオル」と笑顔のおばあちゃん。中学生のトオルが登校する時、おばあちゃんは「にいちゃん、いってらっしゃい」と見送ります。「ぼくは孫のトオル、洋平さんじゃないの」と答えると、悲しそうな顔をします。そして、玄関の方を見て、「にいちゃんはどうしたのかしら。まだかえってこないね」と毎日同じことを繰り返すのです。 トオルは死んだ人に間違われるのは嫌だと思いつつも、知っていました。たった一発の原子爆弾で大勢の人が死んだことを。おばあちゃんの兄洋平さんも両親も死んでしまったことを。
その場面はすべてセピア色。瓦礫を見つめる幼い頃のおばあちゃんの後ろ姿が何とも言えません。トオルの祖母は独りぼっちで大きくなり、おじいちゃんと結婚し、やっとトオルの父を授かるのです。
幼い頃、兄と縄跳びをした広島県産業奨励館が見えた川原で、母親となったおばあちゃんの家族3人が笑顔で遊ぶ姿が描かれています。笑顔はどちらも同じなのに、産業奨励館は原爆ドームに姿を変えているのが印象的です。
トオルが中学生になったころ、おばあちゃんは洋平さんと間違えるようになりました。兄が亡くなったのと同じ年齢になった頃です。「にいちゃんおかえり!」と出迎えるおばあちゃんはきっとあの頃のままなのでしょう。嫌だと思いながらも、トオルは「もしかするとぼくは洋平さんの生まれかわりかも」と考えるようになりました。だったら、ぼくは絶対戦争なんかしないと約束するのです。「ばあちゃんが大好きだからもう、悲しい思いをさせないよ」と。
那須さんは広島出身、3歳で被爆した体験を持ち、『ズッコケ三人組』シリーズをはじめ、子どもたちに支持される人気作品を数多く残しています。2021年に他界した後に「ばあちゃんの詩」が発見され、貴重な遺作として話題を呼びました。
絵を担当したのは武田美穂さん。戦争をテーマにした異色の傑作絵本『ねんどの神様』でもコンビを組んでいます。戦後80年に贈る那須さんの最後のメッセージです。「やくそくしよう にどとあやまちを くりかえさないために」
-
30面 編集後記(栗原佳子) ※全文掲載
参院選投開票日前夜、事務所すぐ近くで参政党の「打ち上げ」街宣があった。おぞましいフレーズに合いの手の拍手が沸き起こる。恐怖を覚えた。
気を取り直し、この日、久しぶりに開いたのが「みんなのために 自分のために」(解放出版社)。黒田清さんが手がけた「窓友新聞」で1990年1月号から始まった長期連載「90年代○社会」の一部を書籍化したもので、「窓友新聞」に転職する前の私は、一読者として毎月、紙面でこの連載を読むのを楽しみにしていた。
◯社会=マル社会とは何なのか。前書きで黒田さんはこう記している。
〈戦争中までのタテ社会に代わって、日本社会の基盤となったはずの民主的ヨコ社会も、一人一人の個人、一つ一つの団体が、お互いに垣根を作り孤立している間は隙間だらけの社会であり、その隙間に差別が入りくんでくるということです。
では、どうすればいいのか。タテは駄目、ヨコでもアカンというのなら、1990年代の生きかたは「マル社会」でなければならないのではないか。 「マル社会」は、生き方も考え方も同じ人たちが手をつないで丸くなって生きることではありません。それぞれが自分の生き方、考え方を大事にしながら、違った生き方、考え方の人たちが手をつないで生きる社会です。それが自分のため、そして同時にみんなのためになるのです〉
黒田さん、「窓友新聞」が活動の柱とした反戦反差別。後継を自認する「新聞うずみ火」もそれを標ぼうしてきた。でも、マル社会はさらに遠ざかってしまった。敗戦80年の節目だというのに。
それでも、地道にやり続けます。読者と共に。まもなく創刊20年。 -
31面 うもれ火日誌(文責 矢野宏) ※全文掲載
6月18日(水)
午後、石田冨美枝さん、竹腰英樹さん、金順玉(キム・スノク)さん、金川正明さんが新聞折込チラシのセット作業。ありがたい。
栗原、長生炭鉱での潜水調査を取材。19日帰阪。
6月21日(土)
矢野 夜、大阪空襲訴訟や「都構想」のブックレット作成でお世話になったせせらぎ出版前社長の山崎亮一さんを偲ぶ会。加納美術館館長の千葉潮さんらと再会。
栗原 午後の便でひと足早く那覇へ。琉球大准教授の謝花直美さんと打ち合わせ。
6月22日(日)
矢野 朝、神戸空港から樋口元義さんと那覇へ。午後、沖縄戦跡をめぐる碑フィールドワーク。謝花さんの案内で激戦地の運玉森などを訪ね、夜、参加者20人と懇親会。
6月23日(月)
新聞うずみ火7月号の発送日。矢野、栗原が沖縄出張のため、金川さん、長谷川伸治さん、大村和子さん、澤田和也さん、康乗真一さん、中園博喜さん、多田一夫さんが発送作業。これまでは新聞が届くのを待ち、セットしたチラシを新聞に折り込んでいたが、金川さんの提案でチラシを先に封筒に入れておく方法で時間短縮。郵便局からの回収前に作業を終えたとのメールが。
沖縄慰霊の日。矢野、栗原は早朝、謝花さんと二神洋二さんと黎明の塔、平和の礎などを回り、沖縄全戦没者追悼式を取材。24日帰阪。
6月25日(水)
午後、事務所で茶話会。小泉雄一さんが参加してくれたが体調が悪く早退。根橋敬子さんと入れ違いに。
6月26日(木)
矢野 午後、来社したJR総連兵庫県協議会の中村敏孝さんらと9月21日の講演打ち合わせ。大阪市教職員組合の中松健一さんと8月23日の講演打ち合わせ。
6月27日(金)
夜、事務所で酒話会。定岡由紀子弁護士が参政党の発表した憲法構想案を解説。「天皇元首」「国民は、子孫のために日本をまもる義務を負う」などと突っ込みどころ満載。
6月28日(土)
矢野 午後、堺市のサンスクエアホールで「能登と堺 心をつなぐつどい」。「地震発生から1年半、能登の再生は…」と題して話す。
6月29日(日)
栗原 埼玉県蕨市の「クルド人と共に」の日本語教室を取材。午後、練馬区で開かれた牛島貞満さんの講演会。
6月30日(月)
矢野 夜、西成区の居酒屋「グランマ号」で新聞うずみ火20周年の企画会議。
7月1日(火)
栗原 夕方、参院議員会館へ。「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の井上洋子さんらによる政府交渉報告を取材。
7月2日(水)
栗原 さいたま地裁であったクルド人ヘイトをめぐる訴訟を傍聴・取材。帰阪。
7月3日(木)
矢野 午後、大阪暁光高校看護専攻科の社会学講義。夜、十三の「風まかせ」での「ノボリンキッチン」で大阪大空襲について話す。
7月4日(金)
矢野 午前、枚方市立楠葉中学校で、1年に大阪大空襲、午後から2年に沖縄戦、3年に世界情勢について連続講演。
7月5日(土)
栗原 東成区民センターで開かれた大阪済州4・3遺族会主催の映画「石が語るまで」の上映会へ。
7月6日(日)
栗原 京都へ。自主講座「認識台湾」主催の映画上映会とアフタートーク。台湾のドキュメンタリー映画「島から島へ」は5時間に及ぶ大作。
7月8日(火)
矢野、栗原 午後、とよなか男女共同参画推進センターへ。26日の「黒田清さんを偲ぶライブ」の会場「すてっぷホール」の下見、打ち合わせ。
7月9日(水)
矢野 午後、大阪暁光高校看護専攻科の社会学講義。「参院選にみる外国人政策」について話す。
栗原 夕方 大阪府庁へ。大阪・関西万博のパビリオン建設費未払い問題の当事者と夢洲カジノを止める会が合同で開いた記者会見と街宣取材。
-
32面 うずみ火講座&矢野編集長の8月講演(文責 矢野宏)
●8月2日(土)千葉孝子さん講演
核の脅威が高まる今だからこそ、被爆について考えてみませんか。次回のうずみ火講座は8月2日(土)、「芦屋市原爆被害者の会」の会長を務める千葉孝子さん(83)を講師に迎え、大阪市北区のPLP会館で開きます。演題は「核兵器廃絶へ 被爆者として生きて80年」
千葉さんは3歳で、爆心地から2・5キロ離れた広島市南千田町(現中区)の自宅で被爆し、生き埋めになりました。幼いころは病弱で、芦屋に移った後も放射能の影響におびえる日々だったそうです。2006年に93歳で亡くなった母、副島まちさんは生前、「兵庫県原爆被害者団体協議会」の理事長として、被爆者の救済に奔走。千葉さんは思いを受け継ぎ、国内外の平和運動に参加しています。
千葉さんは「核兵器が存在する限り、安心安全な地球はない」と話しています。
【日時】8月2日(土)午後2時半~4時半
【会場】大阪市北区のPLP会館4階(最寄り駅はJR環状線「天満駅」、地下鉄堺筋線「扇町駅」)
【資料代】1200円、読者1000円
9月の集いは13日(土)午後2時半からPLP会館4階で開催します。講師、テーマは次号で。
●矢野編集長の8月講演
■大阪市立三凌中学校・平和学習会
・日時 4日(月)午前10時~
・会場 住吉区民センター大ホール
・演題 大阪空襲と模擬原爆
■大阪市立鶴見橋中学校・平和学習会
・日時 6日(水)午前9時~
・会場 同校体育館
・演題 大阪大空襲を知っていますか
■大阪市教組西部支部主催学習会
・日時 23日(土)午後2時半~
・会場 難波市民学習センター
・演題 戦後80年、戦争をどう伝えるか
■東淀川区人権教育講演会
・日時 27日(水)午後3時半~
・会場 東淀川区民ホール
・演題 戦後80年、今を「戦前」にしないために