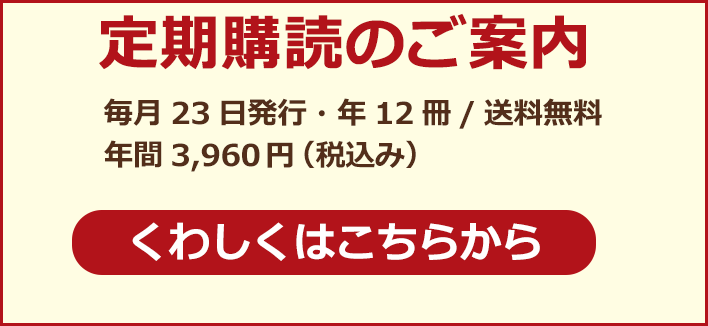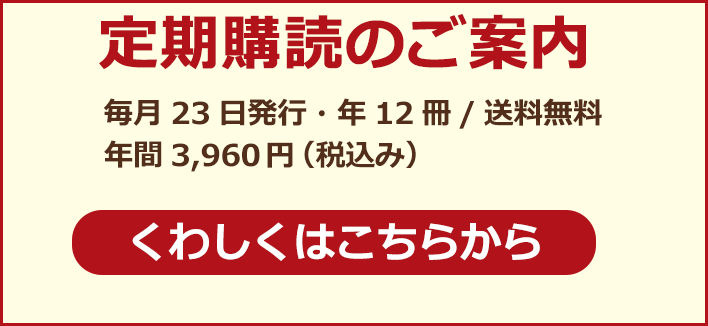新聞うずみ火 最新号

2025年3月号(No.233)
-
1面~4面 大阪万博なお迷走 前売り不振 4月13日開幕(矢野宏、栗原佳子)
開幕まで50日を切った大阪・関西万博。海外パビリオンの建設は遅れ、チケットの売れ行きも低迷。メタンガス爆発事故発生で校外学習にも不安の声が広がる。課題山積の中、注目を集めているのが、このメガイベントを多角的に検証し、「開幕前から失敗」と断じた『大阪・関西万博「失敗」の本質』(ちくま新書)。本の編著者でノンフィクションライターの松本創(はじむ)さん(55)を2月8日、うずみ火講座の講師に招き、「大阪・関西万博はなぜ迷走するのか」解説してもらった。
大阪の中心部、地下鉄梅田駅から乗り換え時間を含めて約30分。万博会場の玄関口「夢洲駅」は中央線の西側の終点だった「コスモスクエア駅」から海底トンネルを通って3・2㌔延伸され、大阪湾の人工島・夢洲(大阪市此花区)に新設された。地下2階のホームからエレベーターで地上に上がると、正面に工事用フェンス。その向こう側が万博会場で、大屋根リングも一部見える。左手は2カ所あるゲートの一つ「東ゲート」。立ち入り禁止の看板の横を工事関係者がせわしなく出入りしていた。
参加国が独自で建設する「タイプA」のパビリオンは47カ国。うち完成したのは6カ国だけ。日本国際博覧会協会(万博協会)が、「3月中に外観だけでも」と要請し、急ピッチで工事が進められている。右手には、造成工事現場のように重機が何台も動いていた。カジノを含む統合型リゾート(IR)の土壌改良工事も行われているのだ。
大阪万博は4月13日から半年間、158か国・地域が参加する。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。万博協会は来場者数を2820万人と試算する。
開催に向けた機運は高まっていない。毎日新聞の世論調査(2月15、16日)によると、「行きたいと思わない」が67%、「行きたいと思う」は16%。万博を推進する日本維新の会支持層に限っても「行きたいと思わない」が39%と、「行きたいと思う」の33%を上回っている。
当然、チケットも売れない。万博協会は前売りだけで1400万枚の販売を見込むが、2月19日時点で787万6174枚と、半分強にとどまる。うち700万枚は企業が購入した分だ。万博協会は運営費1160億円のうち969億円をチケットの売り上げで賄う方針で、採算ラインは1840万枚。いまのペースでは、赤字は必至だ。
…… -
5面~7面 ハンセン病療養所662人 「最後の1人まで」国の責任(矢野宏)
90年にも及ぶ国の誤った強制隔離政策で、ハンセン病の元患者は家族と引き離され、子どもを持つことも許されず、遺骨になっても故郷へ帰れなかった。今も残る差別や偏見を生み出しているのは私たちの無知であり、無関心ではないか。「ハンセン病問題を考える尼崎市民の会」(山本育子代表)が2月9日に行った人権研修日帰りバスツアーに参加し、岡山県瀬戸内市の離島・長島にあるハンセン病国立療養所の「邑久光明園」を訪問した。園の入所者自治会の屋(おく)猛司会長(83)に療養所の現状や課題などを聞いた。
「邑久光明園の入所者は1月末現在で男性24人、女性26人の計50人。平均年齢は89・5歳です。あと3、4年で自治会は閉会せざるを得ないでしょう」
屋さんは32歳の時に入所し、2006年から自治会長。23年8月には「全国ハンセン病療養所入所者協議会」(全療協)会長に就任した。
全国に13カ所ある国立ハンセン病療養所の全国組織で、国を相手に処遇改善に取り組み、「らい予防法」の違憲性を問う国家賠償訴訟を進めるなど、入所者の人権を守る役割を果たしてきた。だが、全入所者数は現在662人で、平均年齢は88歳を超えた。自治会はどこも高齢化で運営が困難になっている。
「人権を取り戻す闘いの先頭に立ってきた全療協の旗を降ろすのは僕の役目。そう長いことではない」と率直に語る。だからこそ、「『しまいどき』を考えている」という。
「国の責任として最後の1人まで療養所で面倒をみること。療養所の統合は認めない。入所者はこれまで苦しめられてきた。だから、『せめて最後くらい安心して逝かせてくれ』というのが入所者の願いです」
ハンセン病は「らい菌」という細菌が皮膚や末梢神経を侵す感染症。病名は1873年にらい菌を発見したノルウェーの医師の名前に由来する。
感染力は非常に弱く、日常生活で感染することはない。しかし、治療法がなかった時代には手や足、顔に後遺症が残るケースがあり、偏見や差別の対象となってきた。明治時代、患者を放置していることを諸外国から非難され、1907年に「癩(らい)予防ニ関スル件」を公布、放浪や路上生活の患者を療養所に収容した。31年には「癩予防法」を制定。家族と暮らす患者にも療養所への入所を強制した。さらに、患者のいない県を目指す「無らい県運動」が官民一体で進められたことで、「恐ろしい伝染病」と誤った認識を助長、本人や家族はいわれのない差別・偏見に苦しめられた。
…… -
8面~9面 長生炭鉱事故83年 「遺骨収集 日韓共同で」(栗原佳子)
山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で1942年に起きた水没事故で、犠牲となった朝鮮半島出身の労働者ら183人を追悼する集会が2月1日、宇部市床波の追悼ひろばで開かれた。遺骨の発掘返還を目指す地元市民団体が昨年秋に坑口を開け、潜水調査が進む中で迎える追悼式。日韓の遺族や市民、両国の国会議員ら450人が参列した。
海から突き出した長生炭鉱の2本のピーヤ(排気・排水筒)を模した追悼碑。冷たい雨が降り続く中、追悼式には例年の倍以上の参加があり、関心の高さをうかがわせた。
事故は1942年2月3日朝に起きた。坑口から約1㌔沖の坑道で落盤が発生し、海水が一気に流れ込んだ。
長生炭鉱は14年に操業を開始。たびたび出水する危険な炭鉱として地元でも知られ、「朝鮮炭鉱」と呼ばれるほど、労働者のうち朝鮮人の占める割合が突出していた。
事故が起きたのは日米開戦2カ月後。戦争遂行のため安全を度外視した増産が求められ、特にその日は厳しい産出量を要請された「大出しの日」」だった。坑道の天井を支えていた炭柱まで採り、落盤の一因となったとされる。
追悼碑は2013年、地元の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会(刻む会)」が市民に募金を呼びかけて建てた。遺族の強い思いに背中を押され、刻む会は遺骨発掘・返還を新たな目標に掲げた。
04年の日韓首脳会談を受け、厚生労働省「人道調査室」は、戦時中の民間徴用者の遺骨について毎年約1000万円の調査予算を計上している。一昨年末の政府交渉で、厚労省は「(寺などに安置されている)見える遺骨だけが調査対象」などと回答。「海底のため遺骨の位置、深度がわからないので現時点では調査は困難」とした。
…… -
10面~11面 「群馬の森」追悼碑撤去1年 「記憶 反省 友好」は不変(栗原佳子)
群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」(高崎市)にあった朝鮮人労働者追悼碑が県の行政代執行で撤去されて1月29日で1年となった。撤去に反対してきた市民らは更地となった跡地に集い、花を手向け、「いつか再建を」と思いを一つにした。
追悼碑は「記憶 反省 そして友好」の碑。全国で初めて県有地に建った、加害の歴史を示すモニュメントだった。
1995年、市民有志が「戦後50年を問う群馬の市民行動委員会(アクション50」を結成。聞き取りや現地調査などを重ね、県内の朝鮮人強制連行・労働の実態に迫った。
鉱山、発電所など少なくとも19カ所で約6000人が強制労働させられ、300人~500人が亡くなっていた。
県内には、捕虜として強制連行され死亡した中国人犠牲者の追悼碑が2カ所ある。しかし、朝鮮人犠牲者を悼む慰霊碑はなかった。98年、アクション50を母体として「朝鮮人・韓国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会」が発足した。
2001年6月、県に用地提供を請願。県議会は全会一致で趣旨採択した。03年11月、当時の小寺弘之知事が設置許可。04年4月の除幕式には、知事の追悼の辞が代読された。
逆風が吹き始めたのは12年。「追悼碑の内容は虚偽」などのメールや電話が県に集中し始めた。東京・両国の横網町公園にある関東大震災時の朝鮮人犠牲者追悼碑の撤去を要求する「そよ風」などのヘイト集団からだった、
…… -
12面~13面 「森友文書不開示は違法」 安倍政権のうみ出し切れ(粟野仁雄)
もう国が「海苔弁当」(黒塗り文書)でごまかすことは絶対に許されない。
森友学園問題で公文書の改ざんを強要され、自殺した赤木俊夫さん(享年54)の妻雅子さん(53)が開示を求めている裁判。大阪高裁は1月30日に「文書の存否も明らかにしないのは違法」とし、雅子さんの請求を棄却した大阪地裁判決を覆す逆転判決を言い渡した。
国側が上告するかどうかが注視されたが、2月6日午後、渡米直前の石破首相は記者団に「強い使命感、責任感を持って仕事にあたってこられた方が自ら命を絶ったことは重く受け止めなければいけない。赤木さん、ご遺族の気持ちを考えた時に判決は真摯に受け止めるべきだと考えて上告しない決断をした」と語った。
常日頃、「僕の雇用主は国民なんだ」と語っていた俊夫さんに対して、最大限の敬意を払った言葉だ。
直後に加藤財務相が「検察に出した文書はすべて財務省に戻っている」と存在を認めた。これで焦点は一挙に開示方法に移ったのだ。
「上告されないかとひやひやしていたので本当にびっくりした」。夫の遺影と愛用眼鏡を机に置き、大阪で緊急の記者会見をした雅子さんは笑顔を見せた。
2016年6月、大阪府豊中市の国有地が小学校建設用地として破格の安価で売られたが、翌年2月に名誉校長は安倍首相の昭恵夫人であることが報じられた。国会で野党に追及された安倍首相は「私や妻が関係していたとなれば総理大臣も国会議員も辞める」とたんかを切った。
…… -
14面~15面 連載 ヤマケンのどないなっとねん「米国より日本に投資を」(山本健治)
石破首相が訪米、トランプ大統領と会談したことに、与党のみならず野党の一部やメディアの大方が評価し支持率も上がったというが、安倍元首相以上にトランプ大統領にへつらい、金の兜、投資を増やすという土産を持っていったから「ナイスガイ、タフガイ」と持ち上げられただけだ。
なぜ、こんなお人好しなのか、不思議でならない。この後、自動車に対する関税引き上げをはじめ特別扱いしてくれるわけではないことがはっきりしたではないか。防衛費などでもNATOに対し「5%にしろ」と言ったように、アメリカ第一主義で次々と要求してくることは明白だ。
ウクライナそっちのけでトランプとプーチンによるボス交渉でレアメタルなど鉱物資源や食糧を自分たちのいいように取ろうとするだけで、侵略をやめさせて世界に平和を取り戻そうなどとはまったく考えていないことは誰の目にも明らかだ。こんな人物にゴマすってどうする。
安倍内閣以降、対米投資をどんどん増やし、岸田内閣が防衛3文書を閣議決定以降は防衛費も引き上げ、トマホークや武器を買ったが、石破首相はさらに増やし、今回は1兆㌦、151兆円にすると言ったが、日本の予算は115兆円、これをはるかに上回る。そんなカネがあるのなら日本のみんなのために投資し、貧困と格差をなくせ。
いま日本の最大の問題は貧困と格差、そして、とんでもない物価上昇だ。米は倍以上になっているにもかかわらず対策を取らず、今になって備蓄米を3月に放出すると言っているが遅すぎる。高止まりのままになることは明白。ロシアのウクライナ侵略で世界的に食糧危機やエネルギー危機が生じたが、それに便乗して時代劇の悪徳商人のように価格を引き上げてボロ儲けしているのだ。国会は何をしている。与党を少数に追い込んでも何にもなっていない。
…… -
16面~17面 連載 世界で平和を考える「ウクライナ停戦とトランプ」(西谷文和)
トランプ政権になって世界は激動期を迎えているが、大きな転換点を迎えそうなのがウクライナ戦争である。戦争勃発後2度ウクライナを取材したので、ここではその取材内容と、今後のウクライナについて私見を述べたい。
2023年5月、首都キーウから夜行列車で東部の激戦地ハルキウに入った。早朝のハルキウ駅前広場は無人で、ビルの窓ガラスは爆風で吹き飛ばされていてベニア板。マクドナルドの傾いたMの看板が印象に残っている。驚いたことに地下鉄が営業を再開していて、電気もかろうじて通っていた。ロシア軍が火力発電所を空爆したので、エネルギー不足ではあったが、なんとかライフラインはギリギリ保たれていた。
ハルキウ市は戦争勃発直後にロシア軍に占領されてしまったが、22年9月電撃的な奪還作戦でウクライナが取り戻し、空襲警報が鳴り響く中、市民がポツリポツリと帰還し始めていたのだった。
市の中心部から地下鉄とタクシーを乗り継ぎ、ロシア国境からわずか20㌔まで迫ってみた。国道沿いのガソリンスタンドやドライブインはロケット弾で全壊、ほぼ無人のゴーストタウンからロシアへと伸びる国道に一本の破壊された橋があった。戦争初期、ウクライナ軍がこの橋を破壊、東から攻め上がってくるロシア軍をここで足止めして、森に隠れていたウクライナ兵士がロシア兵を狙い撃ちした場所だった。橋は修復工事中だった。この時点では「ウクライナが有利」とされており、「もうロシアは攻めて来ない」という自信の表れでもあった。通訳のアントンは、「俺たちが勝つ。勝利は目前だ」と述べた。
…… -
18面~19面 連載 フクシマ後の原子力「原発に囲まれた小浜」(高橋宏)
2月13日、関西電力は福井県内の原発にたまる使用済み核燃料の県外搬出に向けた、新たなロードマップ(工程表)を同県に示した。新たな工程表では、青森県六ケ所村の再処理工場への搬出時期を2028~30年度にずらし、計198㌧と数値を明記した。また、フランスへの搬出量が400㌧に倍増されている。それを受けて杉本知事は「実効性について厳しく判断する」とした。
使用済み核燃料の県外搬出は1997年、栗田幸雄知事(当時)が「中間貯蔵施設」を県外で建設するよう関電に求めたことに端を発する。県外搬出の方針は、その後西川一誠知事、そして現職の杉本達治知事と受け継がれてきた。
98年に秋山喜久社長(当時)が、2000年度末までに建設地を決め、10年の操業を目指すとしたものの、候補地の提示すらできぬまま時間だけが経過していた。動きがあったのは23年で、関電が一部をフランスに搬出する計画を公表した。電気事業連合会の実証実験で、使用済みプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を含む高浜原発の使用済み燃料約200㌧を、フランスに運ぶという計画だ。
森望社長は「県外搬出という意味で、中間貯蔵と同等の意義がある」と強調した。そして同年、日本原燃が六ケ所村に建設中の再処理工場への搬出、30年頃の操業を目途とした中間貯蔵施設への搬出、そしてフランスへの搬出を三つの柱とした工程表を示す。
実は森本孝前社長は21年、中間貯蔵施設の候補地提示の期限を23年末に先送りした際、「最終年限」として確定できない場合、運転開始から40年を超える美浜原発3号機と高浜原発1、2号機を運転しないと表明していたのだった。
…… -
20面~21面 立花氏への情報流出 維新の3県議関与(矢野宏)
兵庫県の斎藤元彦知事への内部告発文書を調べる県議会調査特別委員会(百条委員会)のメンバーが、今もSNS上で誹謗中傷を受けている。知事を追及する委員を「知事失職の黒幕」と名指しした文書や百条委秘密会での音声データが「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏に渡り、拡散されたことがその一因。ネット上で脅迫的な抗議を受けた竹内英明元県議が死に追い込まれて1カ月。尼崎市で「『デマと脅迫から民主主義を守る』集い」が開かれ、市民ら200人がネットの暴力から百条委を支えていくことを確認した。
昨年11月の県知事選では、内部告発した元西播磨県民局長(昨年7月死去)を中傷するデマが拡散。「知事は陥れられた」との同情論を広げ、百条委のメンバーへの攻撃を呼び、斎藤氏再選につながった。誹謗中傷の一因となった立花氏への情報提供に日本維新の会所属の岸口実、増山誠、白井孝明(たかひろ)の3県議が関与していた。岸口氏は百条委の副委員長であり、増山氏は委員だった。
デマ文書拡散をめぐっては、立花氏が「岸口氏から提供された」と主張。否定していた岸口氏は2月23日の者会見で、昨年11月1日、神戸市内のホテルで民間人とともに立花氏と面会し、真偽不明の文書を手渡す場に立ち会ったことを認めた。
増山氏は昨年10月31日、神戸市内のカラオケボックスで立花氏と会い、百条委が非公開で行った証人尋問の音声データに加え、元県民局長の私的情報に触れた自作のメモ(備忘録)も手渡したことを明らかにした。
…… -
22面 関東大震災・検見川事件 島袋さん 研究の集大成(栗原佳子) ※全文紹介
1923年の関東大震災では地方出身者が虐殺される事件も頻発、千葉県千葉郡検見川町(現・千葉市花見川区検見川)では秋田、三重、沖縄の男性3人が自警団に殺された。事件を調査してきた島袋和幸さん(71)=葛飾区=が「関東大震災・検見川事件」を出版した。長年の研究の集大成。島袋さんは沖縄出身で、「沖縄と震災」についても多くを割いた。
検見川事件は1923年9月5日、東京から千葉方面への主要街道・千葉街道(現国道14号線)上で発生した。
大地震から4日後。東京から避難民が流入する一方、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」などの官製デマが流布されていた。午後1時頃、秋田県出身の藤井金蔵さん(22)、三重県出身の真弓二郎さん(23)、沖縄県出身の儀間次助さん(22)が自警団に拘束された。
誰何され、服装や言葉が怪しいと疑われたとみられている。
針金で後ろ手に縛られた3人は2、300人の群衆に取り巻かれ、数百㍍先の派出所に引っ立てられた。巡査は3人が所有していた身元証明書を示したが、群衆は「朝鮮人に味方するニセ巡査」呼ばわりし、派出所のガラスを叩き割って3人を引きずりだし、日本刀やとび口などで殺害。遺体を川に突き落とした。
島袋さんは沖縄・伊江島出身。朝鮮人虐殺現場近くに職場があり、フィールドワークにも参加するようになった。その中で、同郷の青年が犠牲になった事件のことも知った。
せめて墓に花を手向けたいと、それぞれの出身地に足を運んだが、歳月が壁となった。儀間さんの場合、沖縄戦で住民基本台帳も焼失していた。
当時の新聞などを丹念に調べ、事件の真相に迫ろうとした。2013年、22年と資料集を発行、今回で3作目。各地で起きた日本人殺害事件や知的障害者や聴覚障害者が殺された事件なども示し、「朝鮮人」や「中国人」が標的とされた102年前の憎悪犯罪を浮かび上がらせた。
サブタイトルは「沖縄県人の震災体験」。A5判150㌻の半分を充てた。
歴史家の比嘉春潮、詩人の山之内獏ら知識人12人の体験記録も収録。流言が飛び交う中、自警団に襲われかけたりした生々しい証言を紹介した。
出稼ぎ中に被災した沖縄の人々は多数いたとみられる。だが記録や資料が残るケースはまれ。「そもそも、多くの県人は文字を持たない労働者だった。大正期から戦前の昭和期にかけての沖縄本島の新聞はほとんど残っていない。震災関連記事もほとんど見当たらない」と島袋さん。厳しい条件の中、粘り強く資料を探した。地域誌などには、検見川事件の儀間さん以外にも、沖縄人と推測される犠牲者の存在が複数浮かび上がった。
川﨑や横浜の集住地域は多くの家屋が倒壊。川﨑の富士瓦斯紡績の工場では63人の沖縄出身の女工が圧死。同社保土ヶ谷工場では沖縄出身の女工ら453人人が圧死した。被災者の引き揚げ、遺骨送還の苦難も記した。
「陸続きではない沖縄の人は内地とは違う震災体験をしている。特に沖縄の人にこの歴史を知ってほしい」。故郷を離れて暮らす沖縄人の聞き書きが島袋さんのもう一つのライフワーク。その蓄積あってこその労作だ。
-
23面 経済ニュースの裏側「エネルギー考」(羽世田鉱四郎) ※全文紹介
2040年を目標に第7次エネルギー基本計画が発表されました。再生エネが半分を占めますが、「原発も最大限活用」して現在の14基から36基をフル稼働して2割を占めるとのこと。言葉を失いましたが、エネルギー問題を考えてみます。
地震大国と原発 日本列島は、海洋プレート(太平洋P、フィリピンP)が大陸プレート(ユーラシアP、北米P)の下に沈み込む地域です。活断層(将来活動する可能性のある断層など)が2000本近く存在し、周辺では1日に数百個の地震が発生、活火山も111個存在します。2011年の東日本大震災を機に、全原発を再点検しましたが、敷地内の活断層や、周辺海域の海底活断層の見過ごし、過小評価が目立ちます。多くの原発や関連施設は、冷却水の必要性もあり、若狭湾や下北半島などの過疎地域に集中。電力会社などには地震や活断層の専門家はいません。立地場所が決まってから活断層調査をするので否定しがちで、軌道修正は難しいのが現実です。福島第一原発のデブリの取り出しも困難を極め、六ケ所村核廃棄物処理場も頓挫。「二酸化炭素を出さないから原発はクリーン」という詭弁もしらじらしい限りです。ミサイルはもちろん、ドローンなど防空対策も皆無。
発電 水力、風力、地熱など再エネのトピックスと火力の方向性を探ってみます。全般に小型化へシフトしており、異業種参入も目立ちます。小水力発電は河川や農業用水、砂防ダム、上下水道などに適用され、1万㌔㍗以下の発電です。事業主体は自治体、土地改良区、NPO、民間、個人など。環境に優しく、安定した発電力があり、経済性が高いのが特徴。技術的な問題はないのですが、規制が多く、法的手続きの複雑さなどが難点です。またミニ風力発電や家庭や事業者向けの小型太陽光発電も増えました。
コンバインドサイクル発電 ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせ、排気ガスを活用して蒸気を作り、発電機を回します。天然ガスなどを使い、有害排出物がゼロに近く、通常の火力発電より多くの電力が得られます。東電・川崎発電所や千葉・富津火力発電所など、全国の電力会社が積極的に採用。工業地帯が主体で、大容量の発電。送電ロスが少ない利点もあります。
電気を貯める 電力は地産地消が基本かと。電力の安定供給に蓄電池は欠かせません。産業用では鉛、ニッケル、リチウムイオン電池、ナトリウム・硫黄電池、レドックスフローなど。それぞれ長所短所がありますが、鉛蓄電池は低コストで助燃性がなく、安全性が高く、大容量に向いています。材料工学分野で優れる日本では「軽量で柔軟性に富み、曲げられる太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)」の考案(桐蔭横浜大の宮坂力特任教授)、「赤外線から電気エネルギーに変換できる材料開発に成功」した阪大の坂本雅典教授、「次世代のEV用電池でリチウム電池より高容量」の全個体電池の研究で、世界をリードする東京科学大の菅野了次教授、「エネルギー密度はリチウム電池の数倍から10倍」の空気電池を研究する筑波大、将来性の豊かな燃料電池や水素などの研究に期待がかかります。
-
24面 連載 会えてよかった 比嘉博さん(上田康平) ※全文紹介
大田昌秀さんは1990年、知事に当選(8年在任)。企画調整室にいた比嘉さんは大田知事のもとで仕事をすることになった。
比嘉さんは「沖縄『平和の礎』はいかにして創られたか」(以下、共著)の10頁に、大田氏の選挙公約、「アジア諸国及び国際平和に貢献する県政」には、非常に新鮮な印象をもったと書いている。91年から担当する「国際平和創造の杜(仮称)構想」も公約にあったという。
大田知事の考えに共鳴していたのですねとお聞きすると−−−−
「そうでないとあそこまで仕事を続けることはできなかった」。大田さんが戦後50年に完成をめざした沖縄戦を風化させることなく、世界に平和を発信する平和の礎。やめたいと思うこともあったけれど、いくつもの難題を乗り越えながら建設、除幕にこぎつけた。刻銘名簿の整備で、特に戦没した名もない子どもを家族に含める作業はたいへんだった。
私が比嘉さんたち職員はすごいなと思ったのは、共著の14頁−−−−
平和という名の仕事が県政の中で定着していく中で感じたのが、大田知事がこれまでに 執筆した図書の数々で示された、凄まじい体験や思いであった。我々は、その図書・出版 物を読みこなすことから出発した。指示する側とされる側で同じ認識を共有しないと仕事は進まないので、各自それぞれ必死だった。
国際平和創造の杜(仮称)構想平和行政を県政の最重要施策として掲げた大田県政は、その具体化として−−−−
世界的に平和の発信拠点となる場の形成を目指し、検討を重ね、大規模な「国際平和創造の杜構想」を創出した。この構想は本島南部海岸一帯を「全戦没者の追悼と平和祈念ゾーン」など5ゾーンに分け、「平和の礎」、平和祈念資料館の移転・改築、国際平和研究所等の施設展開、平和基金の創設などであった。(共著、16頁より)
この構想は企画調整室から平和推進課に業務移管されたが、いずれの部署でも、比嘉さんは担当した。
しかし50周年事業として、「平和の礎」事業、平和祈念資料館移転改築事業などが優先されて構想の計画づくりは後回しにされ、計画づくりの機運は薄れ、構想が予定していた国際平和研究所は実現できなかった。
比嘉さんは共著(18頁)にこう書いている−−−−
国際平和研究所設置はそもそも、「平和の礎」との一体的な事業であったので、我々としては、大きな反省の一つである。
大田昌秀さんは師範鉄血勤皇隊として沖縄戦に動員された
大田さんは沖縄戦当時、沖縄師範学校の生徒で軍に動員された学徒隊の一員だった。
-
25面 連載 日本絵映画興亡史 「永田ラッパ」人生の絶頂(三谷俊之) ※全文紹介
あらゆる面で統制が進められた時代、永田雅一は政府当局に猛烈な運動を繰り広げた。「情報局の指令に従って動く半官半民会社を持つべきだ」と力説し「大日本映画株式会社」通称「大映」創立にいたった。この件が怪しまれ、贈賄の疑いで巣鴨刑務所に拘留されたが、すぐ不起訴となった。
1943(昭和18)年、永田は松竹の大谷竹次郎に頼み、作家で文藝春秋社をつくった菊池寛を社長に招き、自らは理事となった。菊池が社長となったことで映画の社会的地位が高まり大映に〝箔〟をつけた。
永田はほとんど台本を読まないが、菊池はストーリー第一主義で、シナリオを重視し、企画はもちろん、自ら本読みにも参加した。戯曲作家で小説でも『鶴八鶴次郎』で第1回直木賞をとった川口松太郎も加わった。
設立間もない大映だが、脚本優先の作品で業績を上げた。脚本・伊丹万作、監督・稲垣浩で、阪東妻三郎の主演『無法松の一生』や伊藤大輔による『宮本武蔵』シリーズなど名作を生んだ。
そして、敗戦−−−−。菊池は勇退し、永田が社長に就いた。しかし戦犯指定で公職追放となる。この時もGHQを口説き落としてすぐに解除とした。戦後の大映はヒットがなかった。そこに「軍艦以外はすべてきた」といわれた195日間に及ぶ東宝大争議のため映画を撮れなかった黒澤明が『羅生門』の企画を持ち込んだ。完成した映画を見た永田は理解できず、「担当者を首にしろ!」と激昂したという。
だが『羅生門』が第12回ベネチア映画祭(1951年)のグランプリ(金獅子賞)を受賞した。永田は、「グランプリって何や?」と聞き返したという。
映画祭出品にも無関心だったが、受賞後は手のひら返しの絶賛だ。以降、永田はグランプリ・プロデューサーとして映画製作に邁進する。52年には吉村公三郎監督『源氏物語』がカンヌ映画祭撮影賞、53年には溝口健二監督『雨月物語』がベネチア銀獅子賞、54年は衣笠貞之助監督『地獄門』がカンヌ・グランプリ、55年に溝口監督の『山椒太夫』がベネチア銀獅子賞、さらにアメリカで『地獄門』がアカデミー賞外国映画特別賞と色彩映画衣装デザイン賞と次々受賞する。
「興業の東宝」は主要都市の一等地に映画館を次々と建てた。阪急資本の東宝に対して、東急も映画に進出してきた。永田とは少年期からの「ガリコ」仲間であったマキノ満男が、終戦後、根岸寛一とともに満映の残党を引き連れ東横映画に入った。これが東急資本の東映となる。
永田は海外に目を向けハリウッド、香港、タイなどと組んで合作を製作、フランスとアラン・レネ監督の名作『二十四時間の情事』も合作する。それだけではない。プロ野球球団オーナー、馬主、そして河野一郎、大野伴睦、次に岸信介ら有力政治家たちの黒幕として政界に影響を与え「永田ラッパ」の異名を世に響かせた。その頃が彼の人生の頂点だった。
-
26面 連載 坂崎優子がつぶやく 「見えない」は「ない」のか ※全文紹介
中居正広氏と女性のトラブルに端を発して、フジテレビのガバナンス欠如が明らかになりました。日々最新のニュースや社会の今を報じながら、自社内は旧態依然のまま。内実と外に向けた顔がダブルスタンダードにあったようです。1回目の会見時にテレビ局でありながらカメラを入れなかったことなどは、まさにそのことを象徴しています。
日本の、特に国内中心に事業を行う企業の人権意識の低さが目立ちます。その中でもフジテレビは、コンプライアンスが叫ばれて久しい現代で、まるで逆行するかのようです。
私が若かった頃ですから30年以上前の話ですが、関西の放送業界でも女性が性的に軽く扱われ、それを受け入れるのも仕事のうちという風潮はありました。私自身は所属していた事務所が経営者もスタッフも女性で、現場に目を光らせていることで有名だったせいか、全くこうしたこととは無縁に仕事をすることができました。
事務所に入ってすぐのこと。ある有名番組のアシスタントオーディションがありました。その帰りのこと。社長から「あのパーソナリティーはアシスタントに手を出すことで有名なのよ。でも安心してね。担当することになってもしっかりガードするから」と言われて驚いたことがありました。不合格と聞いて安堵したものでした。
ただ、別の事務所の友人は、あるパーソナリティーにホテルに誘われ断ったところ、その後からことあるごとに暴言をはかれ、長らく心療内科に通って苦しんだと言います。そのことをほんの数年前に聞き、ショックを受けました。今でも思い出すと吐き気がするそうです。
ほとんどの加害者は自分の行為で相手がどれほど傷を負ったかなど想像すらしません。彼女の件も相手は「何もしていない」くらいに思っているかもしれません。逆らえない立場の人間から「性の対象とされる」「暴言を浴び続ける」ことは大きなストレスで、弱い立場の人間は長く自己嫌悪や自己否定にさいなまれます。またそのダメージはこれまで人知れず密かに存在し、表に出てくることがほとんどありませんでした。多くの被害者はそうした暗いものをしまい込んで生きてきたからです。
長く、「見えないからないもの」であった性加害が、被害者の勇気によって「あったこと」として表面化してきました。私たちの世代が「うまくかわそう」で済ませてきたことで、今の若い人たちの代まで残してしまったことを申し訳なく思います。ただ、一方で仕事をもらう弱い立場で何ができたかとも思うのです。
企業として機能不全を起こしているフジテレビは単にトップが交代するだけでは変わることはできないでしょう。誰が指揮を取ろうと、トラブルが起きれば同じように対処できるシステム作りが不可欠です。立場に関わらず被害を訴えることができ、かつ仕事も続けられる仕組みが確立されなければ、これからも繰り返される問題です。フジテレビがそこまでできるのか、一視聴者として注視していこうと思います。
(フリーアナアウンサー)
-
27面~29面 読者からのお手紙&メール(文責 矢野宏)
原発再稼働・新設
福島事故忘れたか
大阪府 水垣良成
資源エネルギー庁が第7次エネルギー基本計画(案)をまとめ、原発の再稼働・新設の方針を打ち出しました。まるで東京電力福島第1原発事故による多大な犠牲がなかったかのようです。
政府は、地球温暖化対策として二酸化炭素の発生が原発稼働時にはないことを根拠にしていますが、本当でしょうか。以前、福井県の小浜湾へ行った時、船長が「この湾の海水温度は他と比べて2度高く、それでタイの成長が早い」と言っていました。原発は発電効率が悪く、約7割が熱エネルギーのロスとなり、海水に排出されます。
原発をめぐっての問題、政権側の不都合、歴史的背景など、市民科学者の山本義隆さんが数多くの文献や知見をもとに「核燃料サイクルという迷宮~核ナショナリズムがもたらしたもの」をみすず書房から2024年5月に発刊した本で解明しています。読むと、今までの断片的な知識がつながり一つにまとまったような印象を持ちました。労作です。皆さんもぜひ目を通していただければと思います。
(地球温暖化の原因が二酸化炭素にあり、政府と電力会社は「原子力は発電時には二酸化炭素を出さない」と主張していますが、小出裕章さんは「原発建設にも運転にもぼう大な資材や化石燃料を必要とするので、その宣伝も虚偽だ」と語っていました)
…… -
28面 車イスから思う事 自転車と歩行者(佐藤京子)) ※全文紹介
1995年の阪神・淡路大震災以後増えてきたもの。そして、2011年に発生した東日本大震災をきっかけにして、さらに増えてきたものとは何でしょうか。それは、自転車です。
車道を走ることが原則だが、けっこうな数の自転車が歩道を走っている。寒い時期は自転車のスピードも自然と上がる。危ないなぁとのんきに思っている場合ではない。うっかりしていると、前から突っ込んでくる。後ろから来た自転車が急ブレーキをかける音がする。
先日、当て逃げされた時はぶつけられたと思ったら、逃げ足が速い速い。口の悪い自分は「地獄へ堕ちろ」とつぶやいていた。車イスでは追いかけることもできず、悪態をつくしかないのだ。
迷惑なのは自転車だけではない。狭い歩道で、2人の世界に入って手をつないでのんびりと歩くカップルのなんと多いことか。仲の良いことはけっこうだが、周りに迷惑をかけていることに気がついてほしいものだ(決してやきもちではない)。
迷惑な歩行者はまだいる。電動車イスの自分を追い越して行くのは別に気にしないが、前に出た途端に歩みが遅くなる人がいるのだ。その多くがスマートフォンを見ながら歩く人たちで、ゲームをしたり、LINEしたりしながらもたもたと歩くものだから、こちらはいらいらする。歩くことにもっと集中してもらいたいものだ。
電動車イスは、道路交通法で歩行者と位置付けられており、時速は4㌔~6㌔に設定されている。一般の人の速足ぐらいだろうか。それでも、実際に乗っていると決して速くは感じない。目の前をもたもた歩く人を抜けそうで抜けないジレンマも少なくない。
しかも、電動車イスは一定の速度で走ることは得意だが、瞬間的にスピードを上げることはできない。歩行者に衝突しても「逃げ足」は速くないので、素直に謝るしかないのだ。
道が狭くても、人も自転車も車イスもそれぞれが気持ちよく歩くのは簡単なことなのだ。周りをよく見て歩くことをお勧めします。
(アテネパラリンピック銀メダリスト 佐藤京子)
-
29面 絵本の扉「どんなかんじかなあ」(遠田博美) ※全文紹介
歌手、俳優、それに政治家とマルチな才人・中山千夏さんは2004年に絵本作家としてデビューし、この作品で「日本絵本賞」を受賞しました。
主人公は表紙に描かれた男の子、ひろくん。友達のまりちゃんは目が見えません。「見えない」ってどんな感じかなあと、ひろくんは目をつぶってみると……。そして、ひろくんは、まりちゃんにこういうのです。「見えないってすごいんだね。あんなにたくさん聞こえるんだね。見えるってそんだね。ちょっとしか聞こえてないんだもの」
ひろくんは見えないことを実体験して、視覚が閉ざされると聴覚が敏感になることを悟ります。
友達のさのくんは耳が聞こえません。ひろくんは、耳栓をして「聞こえないってどんな感じかなあ」と想像します。
すると、聞こえている時より、目にするものがより色鮮やかに見えることに驚くのです。
いろんな友達の立場を想像めぐらせて経験していくひろくん。でも、次に出会うきみちゃんとは同じ立場を経験できません。彼女は震災で両親を亡くしていたのです。
「それってどんな感じかなあ」。ひろくんは一生懸命に考えますが、わかりません。実際に両親を亡くすことは体験できないからです。で、ひろくんは「きっとさみしいんだろうなあ」と想像します。すると、きみちゃんは泣きもせず、「そうでもないよ」。
意外な答えに戸惑うひろくん。きみちゃんはこう語りかけるのです。
「わたしね、一日じいっと動かないでいてみたの」
「どんな感じだった?」と尋ねると、「動けないって、すごいんだね。いつもの百倍くらいいろんなことを考えたよ。わかったこともたくさんあったよ」ときみちゃんは答えるのです。
学者みたいに常にじっと考えているひろくんって、どんな子でしょう。最後に、彼がどうして「どんなかんじかなあ」と考えるようになったかがわかります。
自分が体験できないことを想像して相手を思いやることの大切さが伝わります。簡単に「相手の気持ちになって考えましょう」と言ってすませるのではなく、お互いに足らない部分を思いやる大切さを考えさせてくれる一冊です。
(元小学校教諭 遠田博美)
-
30面 うずみ火掲示板「3月の講演」(矢野宏) ※全文紹介
花団治さんと語る
大阪大空襲の伝承
真宗大谷派大阪教区教化委員会主催「戦争展実行委員会公開講座−−−−戦後80年 次の世代に『あの日の大阪』を伝えていくために」が3月10日午後2時~、大阪市中央区の難波別院同朋会館で開かれる。落語家の桂花団治さんが伝戦落語「じいじの桜」を披露し、矢野が「大阪大空襲の実像」と題して講演する。
伝戦落語は、花団治さんが大阪大空襲で亡くなった先代(2代目)に思いをはせ、戦争を次の世代に伝えていくために創作した落語。大阪城公園には、かつて東洋一の軍需工場と言われた大阪砲兵工廠があった。敗戦前日、最後の大空襲を受けて壊滅した。近年植樹された桜を題材にして大阪城公園の姿をたどる。
「戦争体験のない僕たちができること」と題して花団治さんと対談もある。入場無料。
大阪損保革新懇講演会
「能登半島地震の現状」
大阪損保革新懇主催の講演会が3月14日午後6時半~、大阪市中央区の「アイクルの部屋」で開かれ、矢野が「能登半島の現状と日本の病巣」と題して講演する。
大阪損保革新懇は、損害保険業界の民主的な発展を目指し、1998年10月に発足。講演会は立場の違いを超えて損保の仲間が広く結集する場と考え、取り組んできたという。
会場は、地下鉄「堺筋本町駅」⑫番から徒歩3分、堺筋を北へ230㍍。参加協力費1000円。
-
30面 編集後記(矢野宏) ※全文紹介
日本維新の会の岸口実、増山誠氏、白井孝明の兵庫県議3人が2月23日に神戸市内で記者会見し、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏に情報提供したことを事実上認めた。▼斎藤元彦知事の疑惑を追及する百条委員会の委員だった竹内英明元県議がSNS上での誹謗中傷を受け、自殺に追い込まれて1カ月。その一因とみられるデマ情報を漏らした罪は深いが、音声データと元西播磨県民局長(故人)の真偽不明の私的情報が書かれた文書を手渡した増山氏は「立花氏がデマを言っていたとは認識していない」と語るなど、悪びれた様子はない。▼立花氏に頼ってまで斎藤氏再選を目指したのはなぜか。元県民局長が告発した七つの疑惑の中で気になるのが、2023年11月の阪神・オリックスの優勝パレード資金について「必要経費を補うため、信用金庫への補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせた」との告発。県の金融機関向け補助金を当初の1億~4億円に増額。引き換えにパレードへの寄付を信用金庫に要求したのではないかというのだ。▼パレードは、県と大阪府がクラウドファンディングで費用を賄うことにしたが、目標額の5分の1にも届かなかった。というのも、大阪万博のPRにとの思惑が透けて見えたからだ。▼この還流疑惑を百条委で調べられたら困る輩がうごめいた。3県議のほか、県信用保証協会の理事長だった片山前副知事も。▼そういえば、斎藤氏再選を受けて、大阪府の吉村知事はこう語っていた。「知事に不信任決議を出した議会が、百条委を継続する正当性はあるのか」。目的を達成するためには手段を選ばない維新の卑劣さ、モラルのなさが垣間見えた事件。もうだまされたらあかん。 (矢)
-
31面 うもれ火日誌(矢野宏)
1月13日(月・祝)
矢野 午後、大阪市東淀川区の大阪コロナホテルで日本貨物鉄道労働組合関西地方本部の新春旗開きに招かれ、来賓あいさつ。
1月14日(火)
毎週火曜日に大阪府庁前で朝鮮学校への補助金復活を訴え続けている「火曜日行動」が600回を迎え、矢野は午後、大阪市中央区の大阪城公園・教育塔前で開かれた集会、その後のデモを取材。
1月15日(水)
発送予定の23日の前週の水曜日と金曜日は新聞に挟み込むチラシのセット作業日。午後、金順玉(キム・スノク)さんが初めてお手伝いに。ありがたい。
…… -
32面 うずみ火講座(矢野宏) ※全文紹介
3月8日(土)午後2時半~
PLP会館で桜田照雄さん
開幕まで2カ月を切った大阪・関西万博。パビリオン建設の遅れ、数十億円という「気運醸成費」を投じたのにチケット販売は目標の半分ほど。ついには当日券発行を首相に泣きつくありさま。すべては夢洲を会場としたため。夢洲カジノ万博の闇について、阪南大教授の桜田照雄さんが語ります。
【日時】3月8日(土)午後2時半~4時半 ※懇親会あり
【会場】大阪市北区のPLP会館4階(JR「天満駅」から南へ徒歩4分、地下鉄「扇町駅」から徒歩3分)
【資料代】1200円(読者1000円)、オンライン視聴600円
希望者にはいつでも視聴できるURLをお伝えします。