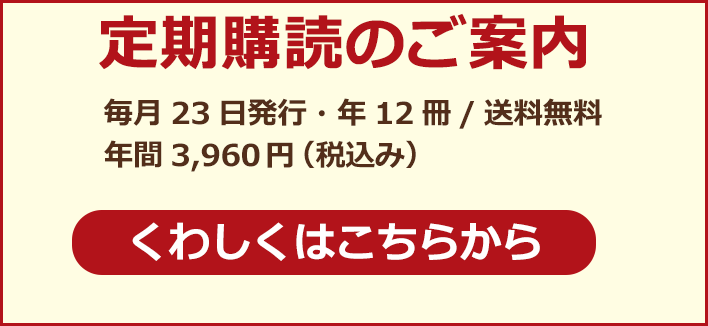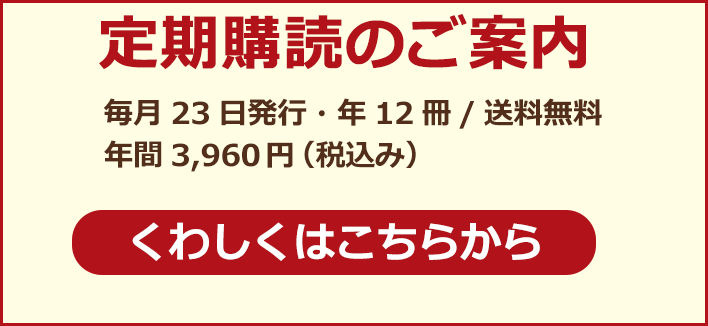新聞うずみ火 最新号

2025年5月号(No.235)
-
1面~5面 本土と沖縄結ぶ奄美大島 基地増強 続く6年(矢野宏、栗原佳子)
豊かな自然に恵まれ、「東洋のガラパゴス」とも称される鹿児島県の奄美大島。世界自然遺産に登録された風光明媚な島は今、「陸海空の自衛隊基地の島」にもなりつつある。陸上自衛隊のミサイル基地が2カ所開設され今年で6年。この間、巨大弾薬庫の建設が着々と進み、電子戦部隊も配備された。海上自衛隊の新たな輸送拠点の整備計画も始まっている。防衛力の名の下で加速度的に増強が進む島を、前奄美市議で「奄美ブロック護憲平和フォーラム」代表の関誠之さん(73)に案内してもらった。
九州本土と沖縄本島のほぼ中間に位置する奄美大島。面積約720平方㌔・㍍と、沖縄本島、佐渡島に次ぐ大きな島で、奄美市、龍郷町、瀬戸内町、大和村、宇検村の5市町村がある。人口は計約6万人。北部はなだらかな地形だが、南部は山岳部が大半を占める。
亜熱帯多雨林、広大なマングローブ林、河口部に広がる干潟などの多様な環境に、アマミノクロウサギやルリカケスなど数多くの固有種が生息、2021年7月に徳之島、沖縄県北部と西表島とともに世界自然遺産に登録された。
4月上旬、芽吹いた樹木がふわふわと山々を覆う新緑の季節。「ブロッコリーみたいでしょう」と関さん。しかし奄美大島では、希少な野生動物が生息する山林を破壊しながら、基地や弾薬庫が、住民に説明もないまま進められてきた。
「奄美・宮古・石垣に新部隊」。関さんら奄美大島の住民は14年5月19日付の読売新聞の記事で突然、自衛隊が来る可能性があることを知らされた。
概要はこうだ。政府は、海洋進出を活発化している中国を念頭に、南西諸島防衛を強化するとして複数の島に陸上自衛隊の駐屯地を新設、離島への攻撃や大規模災害に対応する警備部隊を新設する。奄美大島(奄美市など)、宮古島(沖縄県宮古島市)、石垣島(同県石垣市)などを想定。国境離島の警備にあたっている長崎県の対馬警備隊を参考にそれぞれ350人規模。18年度までに配備予定だとした。
関さんは「奄美大島の陸自配備は水面下で進められ、13年度に配備に向けた候補地調査に5000万円、14年度には候補地調査と施設配置図に6000万円が予算化され、既成事実が積み重ねられていたのです」と振り返る。政府は13年末に閣議決定した防衛大綱、中期防衛力整備計画で、中国を念頭に南西諸島への部隊配備を明記した。
防衛省の対応は素早かった。「報道の2日後には当時の武田良太防衛副大臣が奄美入りし、当時の朝山毅・奄美市長と房克臣・瀬戸内町長を訪問しました。6月7、8日には小野寺五典防衛相が奄美入り。朝山市長、房町長に警備部隊の配備計画への協力を要請したのです。両首長とも歓迎の意向を示しました」
昨年、引退するまで奄美市議(社民~立民)を4期務めた関さん。朝山市長が陸自配備に歓迎の意向を示したことで、市民有志らと「戦争のための自衛隊誘致に反対する奄美郡民会議」を結成し、「首長が議会や市民を超えて前向きな姿勢を示すべきではない」と申し入れた。しかし、6月議会では、誘致賛成派の市議たちが「配備を求める意見書」を提出、賛成15人、反対4人、退席4人(公明党)で意見書は可決された。
「誘致の主な理由は、『自衛隊を誘致することで人口が増え、活性化する』『災害時に迅速な部隊展開が図れる』というものでしたが、そもそも自衛隊の本務は地域おこしではない。抑止力の強化は他国との緊張を高め、偶発的な武力衝突の可能性を高めて戦争につながる。有事になれば、自衛隊基地がある地域は標的となる。それに今や奄美は国防の最前線。基地は戦争に備えるものであり、平和のためではないと反論したのですが……」
…… -
6面~8面 教科書問題で国に抵抗 慶田盛さん 戦争マラリアの記憶が原点(栗原佳子)
80年前の沖縄戦で、八重山諸島では軍の命令によって住民はマラリアの有病地域に強制疎開させられ、3647人が犠牲になった。もう一つの沖縄戦といわれる「戦争マラリア」だ。慶田盛安三(けだもり・あんぞう)さん(84)=石垣市=は住民の3分の1が命を落とした波照間島の出身。竹富町教育長時代、育鵬社の中学公民教科書の使用を迫る国に抗った原点には、戦争体験があるという。住民を強制的に危険な場所に追いやった80年前を、慶田盛さんは今と重ね合わせている。
石垣島から高速船で約1時間。波照間島(八重山郡竹富町)はサンゴ礁に囲まれた日本最南端の島だ。周囲約15㌔。標高約60㍍。現在の人口は500人あまりだが、かつてはカツオ漁やりん鉱石の採掘で賑わい、80年前は1590人が暮らしていた。慶田盛さんはこの島で生まれ育った。
強制疎開の命令は突然だった。沖縄県史などによると、米軍が沖縄・慶良間諸島に上陸した直後の1945年3月下旬、石垣島に駐屯する第45旅団(八重山守備軍)本部から、波照間島の住民に「西表島の南風見(はえみ)地区に疎開せよ」と命令が出た。米軍が波照間島に上陸する可能性があるという理由だった。
南風見はマラリアの有病地域。八重山のマラリアは重症化しやすい熱帯性で、古くから人々の生存を脅かしてきた。その恐ろしさを知る人々は、マラリアを媒介するハマダラ蚊が生息する「有病地」を熟知していた。南風見はマラリアのため廃村になった歴史もある土地だった。
命令を知らされた住民たちは猛反対。すると突然、同席していた青年学校の指導員が抜刀した。「旅団長の命令は天皇陛下の命令だ」「命令を聞けないやつは叩き切るぞ」。豹変した指導員は山下虎雄の偽名で大本営が送り込んだ工作員。特務機関・陸軍中野学校出身の軍曹で、住民を組織しゲリラ戦を敢行するための「離島残置諜者」だった。
…… -
9面~11面 岩手県大船渡の山火事 飛び火続発 被害拡大(粟野仁雄)
焼失面積3370㌶と、平成以降、最大の山火事が2月末に岩手県大船渡市で起きた。鎮火宣言(4月7日)に至っていなかった現場からリポートする。
3月31日、仙台空港でレンタカーを借り、東北道一ノ関ICから大船渡市へ。大船渡消防署ではアポなしの飛び込み取材に、荻野渉消防司令が応じてくれた。
「2月19日に末崎、22日に陸前高田市から火が広がった。私は末崎町の碁石海岸の近くで火災鎮圧に携わった。26日に鎮圧宣言が出たが、現場にいたら赤崎町合足地区で出火し、現場から現場へ。最後にこれが大規模火災になった」
山の一番上から煙が高く上がっていた。「最初見た時、何日もかかると思った」
民家も危なく、綾里地区と赤崎地区で避難誘導し、県道9号から越喜来の公民館などに行かせた。消防署や仙台などからの防災ヘリと自衛隊ヘリが空を舞った。地上部隊も一部、海水を使った。「海水はポンプには悪いがそんなことは言ってられません」
火災原因は調査中だが「自然出火ではなく失火では」と荻野さん。「乾燥して温度の上がる春先が危ないけど、まさか平成以降の最大の山火事になるとは」と信じられない表情。この時期に多い西風が強く、一気には鎮圧できない。「急斜面や崖の消火は大変でした。山の奥には入れず、地上部隊は民家に延焼させないことに集中、火が迫りそうな家に放水しました」
今後について「燃えたり海水の塩害で木が枯れると、夏場の集中豪雨は怖いですね」と懸念する。山の保水力が減るからだ。荻野さんは県立大船渡高校の野球部OBだ。
赤崎地区を少し走ると車や小屋、資材倉庫などが丸焼けだ。火勢が連続して広がったというより、散発的に燃えている。飛び火のなせる業だ。最大の被害地の綾里地区に到着したが、消防団長の取材のため、消防署に戻る。
太田昌広団長は「2月26日の朝は末崎で火災現場を見て、分団を激励してから会社に戻った。昼過ぎもサイレンが鳴っていた。風が強くて危ないとは思った。18㍍でしたから」。
「合足(あったり)地区で建物への延焼を食い止めているうち、綾里地区が大変と聞いて、大半がそっちへ向かったのが26日の夕方でした」
山に近い住宅に燃えないうちから放水したが、消火栓は少なく防火水槽が中心、合足では海水を引いた。
同席した田中貴之当直司令は「1本20㍍のホースを4、500㍍つないで合足は建物を守れた。でも綾里地区は守れなかった」と悔しがる。
…… -
12面~13面 大阪万博開幕から1週間 「泥縄式」運営と安全対策(矢野宏、栗原佳子)
大阪・関西万博は4月13日、多くの課題を抱えたまま幕を開けた。開幕から1週間の一般来場者は52万4937人。初日こそ約11万9000人だったが、平日は4万~7万人で推移しており、日本国際博覧会協会(万博協会)が掲げる来場目標2820万人の1日平均15万人には遠く及ばない。直前には着火すれば爆発する濃度のメタンガスが検知され、大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲(大阪市此花区)での開催を不安視する声は後を絶たない。開幕から1週間を迎えた4月20日、会場を訪れた。
まずは入場券。電子チケットを購入するには「万博ID」を登録しなければならない。入力する個人情報が広範囲で、利用目的も不明瞭。できれば避けたい。「EXPO Quick」にアクセスすれば、万博IDは不要。来場日・入場時間・入場ゲート・購入枚数を選択して決済すればいい。大人7500円の一日券ではなく、午後5時からの夜間券(3700円)を購入した。
主なアクセスは、東ゲート前の大阪メトロ中央線の夢洲駅、西ゲート前に到着するシャトルバスの二つ。開幕初日、東ゲート前では入場待ちの長い列ができたため、西ゲートを選んだ。
午後4時、「大阪駅(南)マルビル大阪・関西万博バスターミナル」(大人1000円)から乗車。30分ほどで西ゲート前の第1交通ターミナルに到着した。開通前の阪神高速「淀川左岸線」2期区間を万博の間だけ利用できる仮設道路をノンストップで走行したからだ。
淀川左岸線2期区間は豊崎インターチェンジ(IC)ー海老江ジャンクション(JCT)の4・4㌔で、大部分は地下トンネル。万博会場へのアクセス向上のため2018年に着工したが、地盤改良工法の変更が必要となった。総工事費は当初の約2・5倍となる約2957億円に膨れ上がり、国が55%、市が45%負担する。全面開通は32年度以降で万博には間に合わない。市は建設中の淀川左岸線(2期)の一部区間を利用してシャトルバス専用の仮設道路を建設。事業費50億円は、ほぼ市の負担だという。
…… -
14面~15面 ヤマケンのどないなっとんねん お祭りで貧困解消しない(山本健治)
多くの人が開催に反対してきた「2025年大阪・関西万博」が4月13日、いよいよ始まった。記さねばならない問題は多々あるが、まずは万博協会が共産党機関紙『しんぶん赤旗』『大阪民報』さらにはフリージャーナリストの取材を拒否していることが明らかになったことである。これは共産党だけの問題ではなく、報道の自由を否定する民主主義の根幹に関わるもので、断じて許してはならない。
100年前の1925年4月22日、治安維持法が公布、5月22日に施行されて以降、敗戦に至るまで報道・言論、集会・結社のみならず活動の自由が奪われ、徹底弾圧されて「いのち」まで奪われた。初めは共産党だからと遠巻きに見ていた結果、いつの間にかすべてが弾圧されて暗黒の時代になったことを忘れてはならないし、繰り返させてはならない。
問題は共産党に対してだけではない。報道の不自由については記者クラブ制度を含め外国人記者たちが指摘、国際的にも低い評価しか与えられていないことを恥じ、改めなければならない。万博誘致を進めてきた大阪維新の吉村大阪府知事や所属地方議員たちが、万博に反対したり疑問を呈したりした議員に対し、権限もないのに「万博出禁」などと言ったことと通じる。吉村知事たちは厳しい批判に謝罪し撤回したが、万博協会は18日になってようやく取材を認めることにしたが遅い。万博協会だけではなく国際万博協会の姿勢も問われるが反応は鈍い。世界に開かれた万博が聞いてあきれる。
そもそもゴミを埋め立てた人工島で開催するのだから、可燃性ガスや有毒有害物質が噴出したり、地盤沈下や高潮で水浸しになっても、何の不思議もない。それらをすべて明らかにし、報道提供するのは安全の前提ではないか。万博テーマについては後でもふれるが、『いのち輝く未来社会のデザイン』をメインテーマに『いのちをすくう』などがサブタイトルなのだから、『いのち』に関わるすべてを公開するのは当然ではないか。
…… -
16面~17面 世界で平和を考える ヒズボラのポケベル爆発を追う(西谷文和)
4月13日、大阪万博の開幕日に私は「レバノン館」と「シリア館」にいた。レバノンは岐阜県くらいの広さに約550万人が住む小国だったが、そこに大量のシリア難民約120万人が流れ込み、人口が急増している。首都ベイルートの幹線道路はいつも車であふれ、朝夕のラッシュ時は歩いた方が早い状況になる。
レバノンは中東では例外的にキリスト教徒が多く住み、イスラム教スンニ派、シーア派に加えて、ドルゥーズ派やトルコマンなどモザイク国家として有名である。ベイルートは一見すると平和だが、市内中心部、特にシーア派居住区に入ると破壊されたビルが多数。各ブロックのあちこちにがれきになったビルとヒズボラのナスララの写真。車で5分も走れば、あそこにも、ここにも、という感じ。イスラエルは空爆の2時間前に通告したから犠牲者は出ていないと言う。
「そのビルにヒズボラがいるから」「ビルの倉庫に武器が隠されているから」などと言い訳をするが、地元民は「ノー、ノー、ヒズボラなんかいないよ。ここは単なるレストランだ」と口をそろえて抗議する。百歩譲って、犠牲者が出なかったとしても(実際はかなり殺されているが)、家を奪われた人々は他国に逃げて難民になるか、ホームレスになるか、いずれにしても貧困生活に突き落とされる。
私は2005年、06年、12年、13年と4回、レバノンを取材している。当時のベイルートは「中東のパリ」と呼ばれるだけあって、おしゃれな街で、カフェで堂々とワインが飲めるし、欧米からの旅行者もたくさん。そしてフィリピン人やインドネシア人をメイドとして雇う家庭も多く、基本的に裕福な国だと感じていた。日産のカルロス・ゴーンはベイルートに逃げたが、基本的には「富裕層が好む街」だと思う。
ところが、そんなベイルートに物乞い女性や窓拭きの子どもたちが出現していた。原因は色々とありそうだ。特に20年、ベイルート大爆発事件が起きて、レバノン政府の信用が失墜し、金融資産価値が暴落、ハイパーインフレになったことが大きい。1500リラ=1米ドルが10万リラ=1米ドルと、100分の1ほどの通貨大暴落があった。想像してほしい。例えば爪に火を灯しながらためた100万円の貯金があったとして、それが一夜のうちに1万円になるのだ。ただでさえシリア難民が押し寄せて、家賃高騰&働き手過剰で賃金が上がらないのに、貯金まで奪われてしまう。そして追い打ちをかけたのが、昨年からのイスラエルVSヒズボラ戦争である。「泣きっ面に蜂」状態のレバノンで、本来何を取材したかったかというと、ポケベル爆弾のその後、である。
24年9月、ベイルートやレバノン南部のシーア派地区、つまりヒズボラ支配地域で、ポケベルとトランシーバーが次々と同時爆発、3000人以上が死傷するという悲惨な事件が起きた。犯人はイスラエルだ。なぜこのようなことが可能なのか? それは①ナスララが部下たちに「携帯電話は危ない、ポケベルで連絡を取り合うように」と指示した。②この情報をおそらくヒズボラに潜入していたモサド(イスラエル諜報機関)のスパイがキャッチし本国に報告する③イスラエルは何らかの方法でレバノンに輸入される大量のポケベルに爆弾を仕込んだ。④その爆弾は特別な指令が流れると一斉に爆発するようになっていて、それが昨年9月だった。
…… -
18面~19面 フクシマ後の原子力 原発マネーに依存体質(高橋宏)
福井県の杉本達治知事は3月24日、関西電力が2月に示した県内の原発にたまる使用済み核燃料の県外搬出に向けたロードマップ(工程表・本紙3月号に詳報)を容認する意向を表明した。
これに先立つ3月15日、名古屋地裁が40年超の美浜原発3号機と高浜原発1・2号機について、住民が運転期間の延長認可取り消しなどを求めた二つの行政訴訟について、「原子力規制委員会の審査や判断に不合理な点は認められない」として請求を棄却している。いよいよ福井県内で「老朽原発」の運転が継続される見通しだ。
老朽原発の運転は、金属疲労や中性子照射劣化など、数多くの危険性が指摘されている。中嶌哲演さんが憂えたように、原発現地では「身の丈を越えるような巨額の資金の投入で、住民はリスクのあることを持ちかけられても、カネと引き換えに沈黙してしまう」のか。
話を私が代表理事を務める和歌山県平和委員会の「福井原発学習バスツアー」に戻そう。中嶌さんに話を伺った翌日、私たちはおおい町の猿橋功町議の案内で、大飯原発と高浜原発の現地を視察した。待ち合わせ場所の「うみんぴあ大飯」は、海に面した広大な敷地に道の駅やホテル、ホームセンターなどが建ち並ぶ複合施設だった。前面ガラス張りの奇抜な建物「SEE SEA PARK」と、関西電力の広報施設「エルガイアおおい」がひと際目を引く。
猿橋町議は「おおい町は多い時には年間150億円ぐらいの財政がありました。同じ規模の地方公共団体の年間予算は40億円弱のはず。特別会計を含めると4倍ぐらいのお金があったわけです」と、原発関連交付金などで町財政が潤ってきたことを説明した。 敷地内にある「こども家族館」は県の施設だが、坂井市にある同様の施設(福井県児童科学館)は県教育委員会から人を出すなどしているのに対し、おおい町は交付金で裕福ということで、同館の年間約8000万円の管理運営費を町が出しているという。
「うみんぴあ大飯」を出発してしばらく走ると、道路沿いに延々と続く金網柵が目に入ってきた。シカやイノシシなどの有害鳥獣対策で設けられたもので、町内の山林と耕作地・集落との境界を全て網羅し、総延長は150㌔に及ぶという。総工費10億円は、農林水産省と経済産業省が半分ずつ出していた。
猿橋町議は「本来なら農水省の予算で作るんでしょうが、原発があるおおい町なので経産省も出しましょうと。縦割り行政の中で、国が半々に出すなんてことは珍しい」と苦笑いした。
さらに走っていくと、のどかな田園風景の中に突然、ホテルと見まがうモダンな建物が姿を現した。町立佐分利小学校だ。1990年に建設され、建設費の70%にあたる22億円は経産省の交付金で賄われている。
「文部科学省からは出ていません。学校施設としての最低限の条件を満たせば、あとは自治体の裁量でいくらでも豪華にできるのです」と猿橋町議は説明した。校舎の壁には「原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金施設」のプレートが埋め込まれていた。「学校の校舎にこんなプレートが付いているのは異常に見えると思いますが、おおい町では当たり前になっています」
…… -
20面 長生炭鉱 日韓で潜水調査 遺骨収容 一歩ずつ前へ(栗原佳子) ※全文掲載
山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で戦時中に起きた水没事故で、犠牲者の遺骨収容を目指す地元の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会(刻む会)」が4月1日から4日間、3度目の潜水調査を行った。2日間は初の日韓共同調査。7日の参議院決算委員会では石破茂首相が「国はいかなる責任を果たすべきか、政府として判断していく」と答弁した。
刻む会は昨年9月、床波海岸近くの地中から炭鉱の入り口(坑口)を掘削。昨年10月
と今年2月、水中探検家、伊左治佳孝さん(36)が坑口から潜水調査した。遺骨は坑口から約300㍍沖付近にあると見られるが、手前の250㍍付近で落盤。3回目となる今回は、韓国のダイバー、金京洙(キム・ギョンス)さん(42)、金秀恩さん(キム・スウン)さん(41)も加わり、その先のルートなどを探った。
水没事故は1942年2月3日朝に起きた。沖から約1㌔の坑道の天井が崩落。坑口は183人を残したままふさがれた。138人が朝鮮半島出身だった。長生炭鉱は法律で禁止された浅い層で操業。戦争遂行のため増産が要求され、天井を支える炭柱まで払って落盤を招いたとされる。
戦時中の民間徴用者の遺骨については2004年の日韓首脳会談を受け、毎年約1000万円の調査予算が計上されているが、一昨年12月の政府交渉で、厚生労働省は「(寺などに安置されている)見える遺骨だけが調査対象」と回答、海底の遺骨発掘は困難との立場を崩さなかった。刻む会は「高齢の遺族には時間がない」と、自ら坑口を開けると決断。日韓両国でクラウドファンディングを実施し、重機で地中に埋もれた坑口を掘り当てた。
遺骨収容の道筋は、伊左治さんの協力で大きく開けた。閉鎖環境の潜水調査などに取り組む世界屈指のダイバー。韓国の2人も同様で、伊左治さんと何度も活動している。3人は崩落地点の奥へ抜ける可能性などを探したが、発見には到らなかった。金京洙さんは「心残りはあるが、2、3回では成果は出ない。次も呼んでもらえたら最善を尽くしたい」。金秀恩さんも「とても視界が悪く手探りだった。機会があればいつでも力になりたい」と話した。
3日は伊左治さんが単独で坑口から、最終日の4日は排気・排水筒「沖のピーヤ」から調査した。遺骨があるとされる地点に近く、伊左治さんは「遺骨に至る可能性と安全性、確実性がある」として6月、ピーヤから潜水調査を行う。刻む会はピーヤ内部などの撤去作業のため700万円を目標にクラウドファンディングも始めた(刻む会サイトに掲載したQRコードから)。
一方、遺骨収容について7日の参院決算委員会で大椿ゆうこ議員(社民)が石破茂首相に質問。首相は刻む会の取り組みを「尊いこと」とし、「必要があれば現場に赴くことも選択肢」「国としてどういう支援を行うべきか政府の中で検討したい」と答弁した。刻む会は22日、厚労省と外務省との意見交換会に臨む。
-
21面 読者近況 寮美千子さん、丁章さん(矢野宏) ※全文掲載
詩集「水の時」「星の時」
【奈良】小説家であり、絵本やエッセイ、脚本などさまざまな文芸で活躍している寮美千子さんが1991〜97年に衛星放送ラジオ局「セント・ギガ」に書き下ろした詩が2冊の詩集「水の時」「星の時」として、ロクリン社から出版された(各2750円)。
寮さんは2005年、長編小説『楽園の鳥』で泉鏡花文学賞を受賞。07~16年、奈良少年刑務所で受刑者を対象に絵本と詩の教室を担当。少年たちの詩集『空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑務所詩集』は大きな反響を呼んだ。
セント・ギガは24時間途切れなく音楽と自然音を発信する画期的な放送局で、番組は日の出から日の入りまでの「水の時」と、日の入りから日の出までの「星の時」の二つだけ。人の声が流れるのは、日の出と日の入り、月の満ち欠け、潮の満ち引きの告知と、「詩の言葉」のみだったという。
寮さんは開局当初から「声になることを前提とした詩」600編あまりを提供、「いつか詩集にと四半世紀が経ってしまいました」。セント・ギガは03年に終了したが、「水の時」に124編、「星の時」には117編が収められている。
寮さんはこうも綴っている。 「宇宙から地球を見つめ、地球の音に耳を傾けようとしたそのスピリッツは、世界が混乱を極める今日、一層必要とされているものだと思います」
在日サラム詩人講演会
【札幌】北海道美瑛町に父がオープンした美術館「新星館」の2代目館長となった「在日サラム詩人」丁章(チャン・ヂャン)さんが、6月21日から札幌市教育会館で全4回の連続講演会を開催する。
新星館はパノラマを楽しめる美瑛の丘に、新潟県から築200年の3階建て古民家を移築し、2001年に開館した。須田剋太、司馬遼太郎の絵画や書など100点、人間国宝・島岡達三の陶芸作品100点が展示されている。
丁さんは、半世紀暮らしてきた東大阪から大阪府柏原市に引っ越した。自宅の一角を喫茶美術館に改装するが、完成は来春になるため、「今年は新星館の立て直しから始め、カフェコーナー『喫茶美術館』を開設する予定です」
母親に留守を頼み、連続講演会を企画したという。
①6月21日「私が詩人になるまで」 ②7月12日「無国籍サラムを生きる」 ③8月9日「住む民として」④9月13日「私が詩人になってからのこと」
講演はいずれも午後1時半~3時半、参加費1000円。
丁さんは「私が大阪を留守にしている間も『オール東大阪』のみなさんが頑張ってくれています。新たに結成した『東大阪でヘイト問題を考える会』へのご支援もよろしくお願いします」と話している。
問い合わせは、和寧文化社(0166・95・2888)まで。
-
22面 経済ニュースの裏側 アメリカ考(羽世田鉱四郎) ※全文掲載
トランプ政権が復活し、世界の政治経済は混沌としています。その実情を、米国、中国、EUと3回に分けて触れてみます。まず米国……。
米国の社会構造 外務省の資料(2023年)から。面積は日本の約26倍(983万平方㌔・㍍)、人口は日本の3倍(3億3650万人)。名目GDP(国内総生産)は27兆3609億㌦で、1人当たり8万1624㌦。
国の成立ち 先住民を駆逐、奴隷制を廃し、1776年に独立宣言。プロテスタントが中心のキリスト教福音派が主流で、人口の4分の1を占めます。銃規制、同性婚、妊娠中絶に強固に反対し、人口より多い3億9000万丁の銃を所持。人種の割合は、2024年で白人が65・9%を占めますが、45年に過半数を割り、60年には43・6%に下がるとの予測も。ヒスパニックは17・4→28・6%、アジア系は5・2→9・1%に上昇とのこと。製造業の海外移転と衰退で、地方は人口流出が顕著。都市部は金融・保険・不動産など第3次産業が隆盛で、多様な人種を受け入れる。地方は保守的で高齢化し、共和党の基盤に。都市部は民主党が優位。根深い人種差別が横たわり、白人優位の社会構造。トランプ大統領は就任直後、制服組トップで黒人のブラウン統合参謀本部議長を解任しました。
保護貿易政策 貿易額は輸出2兆527億㌦、輸入3兆1123億㌦と、1兆596億㌦の赤字。対GDP比で、1次産業(農業など)は1%、2次(製造業など)は20%、8割が3次産業(金融、保険、不動産など)です。労働人口もサービス業を中心に85%を占め、製造業は14%。保護貿易政策の狙いは、貿易赤字削減と国内産業の保護。高関税と輸入制限措置で、米国に有利な形での貿易交渉に持ち込むのが目的。「米国の貿易赤字は、相手国の不公正な貿易慣行が原因」との認識。4月3日に自動車及び部品の関税を現行の2・5%から25%に引き上げ、年1000億㌦(約15兆円)の税収増を期待。その他も高関税を適用。
財政構造 財政赤字が拡大し続けています。①高齢化で医療や年金の負担が増大。国民皆保険がありません②債務残高の増大で利払いが増加。軍事や海外援助などの支出を削減し、NATO(北大西洋条約機構)や日本などへの負担増を迫る。第1次トランプ政権は、コロナ対策に失敗し、2000万人が感染、死者35万人と世界最多でした。その対応もあり、歳出はさらに拡大。53年度までに米国と中国の債務残高は倍増との見方も。28年には利払いが1兆㌦(約150兆円)を超え、国防費を上回る見込み。
今後の展望 「私腹を肥やし、人品卑しい」大統領の経済政策は、近視眼的で場当たり。ポピュリスト(大衆扇動主義者)は、常に危機をあおり、仮想敵を作ります。私見ですが、有色人種で女性のカマラ・ハリス氏は当選しないだろうと思っていました。「米国第一主義」の保護貿易政策は、他国の反発を招き、世界経済は混乱し、米国の孤立を深めます。米国内も、物価高を招き、景気停滞と物価高(スタグフレーション)を招くでしょう。状況が悪化すれば、手の平を返すような対応になるかと予想されます。 -
23面 会えてよかった 比嘉博さん⑤(上田康平) ※全文掲載
全戦没者調査はこう進んだ
共著28~30頁をまとめると−−−−
県内全戦没者調査は刻銘に間に合
わせるため実質4カ月間と短期間の
実施となった。県は全市町村に協力
を依頼。最終的に調査員1107名、
戦争体験者等の協力員(聞き取り対
象者)1万名ほどが参画する県民総
出の一大事業となった。
全戦没者調査の実施が決まり、そ
の必要性は職員一同認識していたの
で、あとはまっしぐらに実施するの
みと各自覚悟を決めて、業務をこな
していった。各市町村の取り組みに
全面応援体制を組んで、市町村に出
向いて、全戦没者調査実施方法を説
明しながらの毎日だった。
この調査で一家全滅家族の名簿や、
生まれて間もなく名前も付けられな
い状況の中で亡くなった子どもも家
族の中に含まれるなど、一覧名簿が
53市町村のご協力で何とか作成する
ことができた。
この名簿は精査作業の後、県庁、
各市町村で縦覧。さらに地元紙に全
面広告で掲載、県民の
目で確認してもらい、
修正作業を経て戦没者
名簿はできあがった。
全戦没者調査に
課題があった
共著の119頁、沖
縄戦にかかわる全戦没
者調査票を見ると、氏
名だけでなく、生年月
日や戦没の状況など詳
しい調査票となっている。
比嘉さんは−−−−
調査票は埋めきれてない。沖縄戦
の実相を解明するため、中身の点検、
深掘り、掘り起こしが必要だった。
朝鮮半島や台湾出身戦没者の名簿、
多くが刻銘できないままに
共著によると−−−−
県外、米国出身戦没者については
各都道府県知事、米国国防長官あて
に協力依頼。
朝鮮半島や台湾出身戦没者の名簿
については当時の厚生省にあったが、
閲覧であればとようやく許可され、
比嘉さんたち職員が厚生省で名簿を
閲覧して、朝鮮半島や台湾出身の一
人ひとりの沖縄戦戦没者の名簿を書
き写す作業を行った。その数は4百
数十人程度だった。
しかも日本の植民地時代に実施さ
れた創氏改名で日本名になっており、
それぞれの関係機関に母国語名に戻
す作業を依頼したが、困難な作業で
朝鮮半島出身者133人、台湾出身
者28人と不十分な刻銘名簿となった。
それで多くの戦没者の氏名が刻銘
できない状況のまま、戦没者名簿が
保管されている。今後に大きな課題
を残している。
共著31頁に比嘉さんはこう書いて
おられる−−−−
朝鮮半島出身の戦没者名簿は、そ
の実相が問われている気がする。刻
銘人数も少ないうえ、強制連行の実
態、「慰安婦」としての実情など何
ら解明されない中で、両政府の了解
のもと1995年の刻銘は進んだ。
(つづく)
-
24面 日本映画興亡史「戦時下の映画」 治安維持法で唯一検挙(三谷俊之) ※全文掲載
1937(昭和12年)年7月7日夜、日中両軍は北京郊外の盧溝橋で衝突した。日中戦争の始まりであった。政府は満州事変や上海事変と同じように、小競り合い程度と高をくくっていた。しかし、陸軍にひきずられ戦火は拡大、戦争はその後8年にわたる長期戦となった。国内では連戦連勝と報じられたが、実態は個々の戦闘に敗れ、後退戦が続いた。
この時代、日本映画は内務省と陸軍報道部の統制下にあった。39(昭和14)年10月、帝国議会で「映画法」が通過する。映画はより国家の完全なる統制下におかれる。でき上がった映画の検閲のみならず、脚本の審査があって、ようやく撮影が許可される。配給も許可が必要となった。もっと怖いのは監督や撮影者らスタッフはもとより、俳優も試験を受けて政府に登録し、鑑札が必要となった。
これらの施策に対して、映画界からの反対はほとんどなかった。大手の映画会社経営者は、許可制になれば新たな競争相手がなくなり、既得権が守られるからだ。監督や俳優たちも同じだった。逆に映画人の地位向上にもなると考えた。
「マジメ」な映画だけが生き残る。国家にとっては恋愛映画も、エノケン主演のドタバタ喜劇も「マジメ」ではなかった。恋愛映画は兵士たちに死にたくないと未練をもたらすという。文部省が推薦映画を選び、全国の小中学生が団体で映画館に行くというシステムは戦後も続いた。
もちろん少数の反対者はいた。映画批評家の岩崎昶は、映画法はナチスドイツを手本としているが、ナチスの統制以後は英仏のはるか風下に甘んじている。そしてこの「映画法によって日本映画は衰退する」と批判した。そのため特高に逮捕され、1年間監獄に囚われた。
もう一人、亀井文夫という映画人がいた。08年4月福島県生まれ。文化学院大学部を中退し、29年にソビエトへ留学。レニングラード映画技術専門学校で受講する。ちなみにこの2年前にエイゼンシュティンの『戦艦ポチョムキン』が完成している。当時のソビエトは映画の先進国であった。
33年に帰国、写真化学研究所(P・C・L=後の東宝映画)に入社。第2製作部(文化映画部)に属し、海軍の新鋭巡洋艦「足柄」の記録映画『怒濤を蹴って』でデビュー。その後、『上海』(38年)をつくった。この映画で有名なのは日本軍の行軍を眺める中国人民衆への長い長い移動撮影である。民衆の表情は何よりも日本軍への恐怖と敵意をあらわにしている。そして、無残な戦場跡の映像が繰り返される。
次作は陸軍後援の『戦ふ兵隊』だ。中国戦線の従軍映画だが、勇壮なシーンなどまったくない。日本人兵士のおびただしい墓標と、破壊された家々のカット。戦いと行軍に疲れ切った兵士たちと、戦火に追われる民衆。この映画は上映禁止となる。亀井は、治安維持法違反容疑で検挙・投獄される。映画人としてはただ一人の検挙となった。 -
25面 坂崎優子がつぶやく モンスター化した兵庫県知事 ※全文掲載
兵庫県の内部告発問題で、百条委員会と第三者委員会がほぼ同じ結論を出しました。本来なら決着がついたと見るべきが、肝心の斉藤知事が結果を認めないという異常事態が続いています。
第三者委の結果を受けて開いた会見。どの記事もパワハラだけは認めたような見出しでしたが、実際はあいまいな表現を繰り返す知事に、記者が質問に質問を重ねた結果、ようやく認めたというものでした。
まるで芸能人への推し活のように応援する支持者は別として、あのわかりやすい第三者委の会見内容を見れば、知事の見方を変える人も増えるだろうと思っていましたが、こちらもそう単純にはいかないようです。
知事を支持した人たちに意見を聞いてみると、いろいろなことがありすぎて、結局「何がどうだったのかよくわからない」という人が案外いるからです。そもそも百条委や第三者委などさまざまな調査があってわかりにくい。また維新の議員による情報漏洩が議会全体の問題としてイメージされている、などです。全会一致の不信任決議から選挙でのデマの拡散。そして二つの調査結果。今はもう一つの第三者委が、週刊誌への情報提供者探しを行っていた問題まで浮上しています。よほど経緯を追っていなければ、何がなんだかわからなくなってしまうのも当然です。
情報過多の時代。興味を持ったニュース以外はスルーする人がほとんどだと思います。問題が長引く今回のようなケースでは、途中で興味を失う人も増えていると思います。そうした空気に乗じて、パワハラ認定された知事が、何の処分もなくそのままやり過ごすことになれば、悪しき前例を作ってしまいます。
すでに国政では開き直った者勝ちになりつつあるだけに、自治体にまでこれを広げてしまうのは危険です。
そのためにも「これは許してはいけない」という県民を増やさなければいけないのですが、それがとても難しいと実感します。テレビや新聞を見る人が減り、きちんと取材し精査された情報とは何かがわからない人が増えています。これまでのメディアの伝え方では、もはや大事な情報が届かないのが現状です。
今や多くの人がユーチューブから情報を得て、それを簡単に信じています。デマかどうかは置いておいて、その伝え方には大いに学ぶべきところがあります。兵庫県の問題も、これまでの流れを短くわかりやすく伝える動画を作り、それを広げていくことも、新しいメディアの伝え方として必要ではないかと思うのです。
法律や倫理や道徳などは度外視し、センセーショナルな情報で人々を誘導していこうとする人たちに対抗するには、私たちもスキルを持たなければなりません。
「結局どういうこと?」に対して「そういうことだったのか」と納得、支持してもらえる言葉や伝え方。私自身も次の選挙に向けて、少なくとも自分の周りにいる人たちくらい巻き込めるよう、トライ&エラーを繰り返していきたいです。
(消費生活アドバイザー) -
26面~29面 読者からのお手紙&いいメール(文責 矢野宏)
斎藤知事「続投を」
TV調査にびっくり
兵庫県 谷野勉
兵庫県の斎藤元彦知事は、内部告発文書をめぐり、県の委託を受けた第三者委員会が認定したパワハラ行為を認めて職員に謝罪しましたが、自身への処分はしない姿勢を続けています。告発者さがしを行ったことなど、県の対応が公益通報者保護法に違反すると指摘されたことについても、見解が異なると受け入れず、対応は適切だったとの考えを重ねて示しました。
この件に関しては、3人の命が失われているのですよ。知事には人としての倫理観を持ちあわせているとは思えません。このような知事の態度に対して、県議会の対応は煮え切らない。もう一度、不信任案を提出するのが議会としての筋ではないでしょうか。
県民はどう思っているのでしょうか。3月28日に放送された関西テレビの情報番組「旬感LIVE とれたてっ!」が、10代から80代の県民100人の意見を緊急調査したところ、「続投すべき」が68人、「辞任すべき」が32人となり、斎藤知事の実績を評価する声も多数聞かれたそうです。これには憮然とするばかりでした。さらに、未だに百条委メンバーに対し、SNSでの嫌がらせが続いています。
暗黒の兵庫が4年間続くのですか。私は嫌です。
(兵庫県が新年度の採用過程で、総合事務職の合格者150人のうち69人が辞退し、辞退率は46%だったことが判明しました。昨年度の辞退率は25・5%で20ポイント超増えたとか。パワハラ知事の自分勝手な姿勢をみて嫌気がさしたとしても不思議ではありませんよね)
…… -
27面 車イスから思う事 介助犬の理解広がれ(佐藤京子) ※全文掲載
介助犬イムア君と一緒に車いすで外出していると、数人の小学生が走ってきた。その中の1人が言った。「盲導犬だぜ、触ったりしたらいけないんだよ」。惜しい、ちょっと違うんだなあ。それを聞いた別の児童が「だってかむんだよ」。訂正したいところだが、道の真ん中で説明し始めると、変なおばさんにからまれたと言われかねないと我慢した。
スーパーでも然り。買い物客の一人が「可愛いわね」と近寄ってきたかと思うと、「触ったりしたらいけないんですよね」と言いながら、イムア君をなでなでしている。「この介助犬はいま仕事中なので触らないでください」と言うと角が立つだろうとな、また我慢した。
介助犬と暮らすようになって、早いもので10年になる。介助犬に対する街の人たちの対応も少し変わってきた。先代ニコル君の時は何度か入店拒否にあったし、必要以上に「犬だ犬だ」と騒がれたりもしたが、今ではまれだ。とはいえ、まだまだ知らない人が多く、介助犬の存在を一人でも多くの人に知ってもらうことが大切だと痛感している。
そのなかで、子どもたちとの交流は介助犬の普及活動にとっても重要だ。小中学校での講演やデモンストレーションを通じて、介助犬の役割や訓練方法などを教えることがある。こうした活動を通して、子どもたちが介助犬に対する理解を深め、いくら犬が好きでも仕事中は触らずに見守ってほしい。
親世代にも普及活動は欠かせない。子どもに影響を与える存在ゆえ、親に理解してもらうことが必要だ。講演会やイベントで親世代に介助犬の説明を行うことで、家庭でも認識を広めてもらいたい。
普及活動は、介助犬を連れてのデモンストレーションが効果的だ。イムア君のような介助犬がどのように働くのかを見てもらうことで、その信頼性や必要性を実感してもらえる。介助犬が理解され、協力的な態度になるかもしれない。実際に介助犬と暮らす者の声を届けることで、親近感を持ち、理解を深めることができる。こうした活動を通じて、介助犬が社会に不可欠であることを広く伝えたいと思う。
(アテネパラリンピック銀メダリスト 佐藤京子)
-
28面 絵本の扉「なまえのないねこ」(遠田博美 ) ※全文掲載
絵本にはたくさんの動物が登場しますが、なかでも犬と猫は太古の昔からの付き合いからか、擬人化されたり、人間のパートナーとして数多く登場しています。今回の主人公は猫です。
表紙に描かれているのは、透き通るようなエメラルドグリーンの大きな瞳の猫。吸い込まれそうな目に見つめられ、本屋で思わず手に取りました。
表紙を開くと見開き2ページにたくさんの猫たちが描かれています。1ページ目には表紙のキジトラ模様の猫が、倉庫のような中から外を眺めています。
「ぼくはねこ。なまえのないねこ。だれにもなまえをつけてもらったことがない」。小さいときはただの「こねこ」で、大きくなってからは、ただの「ねこ」だと自己紹介する目は少し寂しそう。
靴屋の猫は「レオ」。本屋の猫は「げんた」。八百屋の猫は大きくなったけど「チビ」。おそば屋さん、パン屋さんの猫たちにもいわれのあるユニークな名前がつけられており、喫茶店の猫には名前が二つもあります。
お寺の猫の「じゅげむ」に、「じぶんでつければいいじゃない。じぶんのすきななまえをさ」と言われて、町を歩きながら自分に合う名前を探し始めます。「かんばん」「じてんしゃ」「ちゅうしゃきんし」……なかなかいい名前が見つかりません。
犬や花にも名前があるのに、「のらねこ! きたないねこ!」と雨の中を邪険にされ、ベンチの下で心の中も悲しい雨が降ってきます。
その時、優しい声といい匂いがして可愛い顔がのぞきました。真っ赤な傘をさした少女が雨宿りしている猫を見つめて「きみ、きれいなメロンいろのめをしているね」。猫はそこで気づくのです。「そうだ。わかった。ほしかったのはなまえじゃないんだ」
見開き1ページいっぱいに少女を見上げる大きな瞳の横顔があふれています。この猫が欲しかったものは何だったと思いますか。そして、ラスト3ページで読み手には安堵の微笑みが浮かんできます。
絵を担当した町田さんと文を書かれた竹下さんは大の猫好き。猫の視点で店の中や猫たちを繊細な描写で描いていきます。町田さんは猫の作品も多く、『ネコヅメのよる』、『ねこはるすばん』もお薦め。猫好きの方もそうでない方も、町田ワールドをのぞいてみてはいかがでしょうか。
(元小学校教諭 遠田博美)
-
29面 空襲証言DVDにご協力を(矢野宏) ※全文掲載
新聞うずみ火は平和学習を支える証言DVD「模擬原爆」を制作中ですが、児童文学「パンプキン~模擬原爆の夏」の著者、令丈ヒロ子さんにインタビューしました=写真。
制作にご支援頂ける方は、ゆうちょ銀行口座への振り込み、郵便振替をお願いします。
支援コースとそれぞれ返礼は次の通り。
▽3000円(お礼状、憲法ファイル)
▽5000円(お礼状、憲法ファイル、視聴券または上
映会参加券)
▽1万円(お礼状、上映会参加券、DVD進呈)
①ゆうちょ銀行
店名(店番)四〇八
普通 記号14030
番号 22963181
②郵便振替口座
00920・9・173051
加入者はいずれも「平和学習を支える会」です。
-
29面 編集後記(矢野宏、栗原佳子)
慶田盛(けだもり)安三さんについにお会いすることができた。八重山教科書問題を取材した頃から、いつかお話を聞きたいと思っていた。理不尽な政治介入にどれほど心身をすり減らしたことだろうか。ご自身も「よく持ちこたえたと思う」と。平和を作り出すこと、「不戦」。慶田盛さんが何度も強調したその言葉をしっかり受け止めたい。なお、先月号で紹介した与那国の水牛は、石垣駐屯地の拡張計画で住処を追われた一頭。別の機会に紹介したい。 (栗)
IRカジノのための大阪万博が開幕した。維新による万博の取り組みは2014年にさかのぼる。当時の橋下徹・大阪市長が夢洲をIRカジノの候補地とする基本計画を決めた後、松井一郎・大阪府知事が万博誘致を表明。当初、開催候補地6カ所の中に夢洲は含まれていなかったが、16年に松井氏が夢洲を想定した「試案」を突然公表。維新と蜜月関係にあった安倍政権をバックに、万博誘致の動きは加速した▼万博の成否は維新の党勢に直結する。それを判断するものさしの一つが入場券の売り上げ。運営費1160億円の8割を賄う。損益分岐点は1800万枚だが、現状は半分ほど。開幕直前、吉村洋文知事は万博の成功についてこう答えていた。「予定通り行われば約3兆円の経済効果があり、それだけで成功と言える」▼今年は戦後80年。当時、敗戦を見抜いた人たちがいた。近衛文麿首相直轄の調査研究機関「総力戦研究所」。官民各層から抜擢された36人が出した結論は「日本必敗」。それを否定したのが当時の東条英機陸相で「机上の演習であり、実際の戦争というものは、君達が考えているようなものではない」。データよりも「空気」が重視された▼万博もやってよかったという空気に流され、そのツケを回されることがないよう注視しなけば。
鎌田慧さんが寄稿してくれた。2月に再会した時の約束を覚えてくれていたことに感謝。 (矢)
-
30面 うもれ火日誌(矢野宏)
3月13日(木)
第1次大阪大空襲から80年。犠牲になった朝鮮半島出身者167人のほか、強制連行された中国人8人、捕虜となった米兵3人を追悼する集会が大阪国際平和センターで開かれ、矢野が取材。
栗原 早朝の便で石垣空港へ。15日には与那国島に移動し、取材。17日に帰阪。
3月14日(金)
矢野 夜、大阪市中央区で開かれた「大阪損保革新懇」主催の講演会で「能登半島の現状と日本の病巣」について話す。懇親会で飲みながらの質疑応答となり、兵庫県知事選や大阪万博などの質問にも答える。「新聞うずみ火を購読します」との声も。
3月15日(土)
矢野 夜、来阪した千葉県柏市の岡田敬さん夫妻と季節料理「川上」で合流。岡本丞史さんも同席。
3月18日(火)
矢野 午後、大阪市天王寺区の府立高等学校教職員組合で志摩毅委員長に高校無償化の拡充について話を聞く。
3月20日(祝・木)
うずみ火事務所の経理と名簿を管理するパソコン画面がピンクに。栗原が悪戦苦闘するも改善されず、頭を抱える。
3月21日(金)
午後、新聞折り込みチラシのセット作業。竹腰英樹さん、金順玉(キム・スノク)さんがお手伝いに。
3月25日(火)
午後、柳田充啓さん、長谷川伸治さん、大村和子さんが残りチラシのセット作業。夕方、新聞うずみ火4月号が届き、金川正明さん、澤田和也さん、康乗真一さん、多田一夫さんも加わり、発送作業。
栗原 発送作業の途中で神戸空港から那覇へ。80年前米軍が上陸し、住民の「集団自決」の悲劇が起きた座間味島、渡嘉敷島で取材。28日に帰阪。
3月26日(水)
午後、うずみ火事務所で茶話会。2023年10月にすい臓がんが見つかり、治療中の小泉雄一さんが1年ぶりに参加。埼玉から根橋敬子さんも駆けつけて握手。夕方、うずみ火講座の撮影でお世話になっている「大阪コミュニティ通信社」代表の石田肇さんと山口達也さんが駆けつけ、パソコン修理。3分で完了。
3月28日(金)
矢野 滋賀県人権センターの機関誌「じんけん」の連載「矢野宏の現場主義」を出稿。夜、事務所で定岡由紀子弁護士を囲んで憲法BAR。
3月29日(土)
プリツカー賞建築家の山本理顕さんを講師に招いた日本ジャーナリスト会議関西支部主催の講演会「大阪・関西万博と人間の尊厳」がエル・おおさかで開かれ、新聞うずみ火も協賛。矢野があいさつ。
3月30日(日)
矢野 午前、JR東海労新幹線関西地本のお花見に誘われ、定岡弁護士と参加。
4月1日(火)
栗原 山口県宇部市の長生炭鉱での潜水調査取材へ。3日に帰阪。
4月4日(金)
矢野、栗原 午前、浪速産業社長で、「大阪都構想」反対やIRカジノ反対の市民運動を担った中野雅司さんの「お別れの会」に出席。
4月5日(土)
正午から大阪城公園教育塔前でうずみ火のお花見集い。珍しく快晴、満開の桜の下で大いに食べて飲んで語り合ってお腹も心も満腹。矢野の高校時代の友人で「奈良経済産業協会」専務の二神洋二さん、松岡義之さん、萩原真理子さん、河原和子さんらが初参加。
4月6日(日)
矢野 栗原 午後、関空から空路奄美大島へ。8日まで「奄美ブロック護憲平和フォーラム」代表の関誠之さんが陸自奄美駐屯地・瀬戸内分屯地、空自奄美通信基地などを案内してくれる。
4月9日(水)
午後、「会えてよかった」を連載している上田康平さんと大矢和枝さんが来社。続いて、堀越おかんこと堀越由美子さんが事務所に。
4月10日(木)
矢野 午後、大阪暁光高校看護専攻科の特別非常勤講師として社会学を初講義。絵本「二番目の悪者」を使い、真実と事実などについて話す。
-
31面 うずみ火講座のお知らせ(矢野宏)
■7月26日、黒田清さんを偲ぶライブ
コント集団「ザ・ニュースペーパー」結成時のメンバーで戯作者の松崎菊也さんと石倉直樹さんを招いての「黒田清さんを偲び、平和を考えるライブ」が7月26日(土)、大阪府豊中市の「すてっぷホール」で開催します。二人の風刺トーク&コントを心ゆくまでお楽しみ下さい。
なお、今年も当日会場でお配りするパンフレットの「一言広告」(1マス3000円~)、カンパを募集します。物価高の時代に心苦しいのですが、お力添えをよろしくお願いします。
【日時】7月26日午後2時開場、2時半開演
【会場】豊中市立とよなか男女共同参画推進センター「すてっぷホール」
【交通】阪急宝塚線「豊中駅」南口改札出て右手、エトレ豊中5階
【資料代】2200円(読者2000円)
■5月10日、大阪城内戦跡めぐり
在日朝鮮人研究家の塚﨑昌之さんが主宰した学習会「塚﨑塾」最後のフィールドワークだった大阪城戦跡探訪を5月10日(土)に行います。
大阪城公園やビジネスパーク、UR森之宮団地、地下鉄森ノ宮車庫はかつて巨大な兵器工場が建ち並ぶ大阪砲兵工廠でしたが、1945年8月14日の大空襲で壊滅しました。塚﨑さんの教えをもとに矢野が解説します。午後1時にJR環状線「京橋駅」南口に集合してください。資料代500円。
■6月22日、沖縄戦跡巡り
沖縄戦跡をめぐるフィールドワークを6月22日(日)に開催します。案内役は沖縄戦・戦後史研究者で琉球大准教授の謝花直美さん。日米両軍が死闘を繰り広げた西原町の運玉森などを回ります。現地集合、現地解散。フィールドワーク終了後に懇親会も予定しています。
-
32面 鎌田慧「世相を斬る」 司法が「凶悪犯」をつくる
まったく身に覚えのない事件なのに、容疑者として捕えられる。留置場に入れられ、来る日も来る日もお前がやったんだろうと責め立てられる。本人にとって悪夢のような日が続く。人質司法。いったん逮捕されると、自供するまで釈放されない。冤罪の「冤」は「兎」が「門」の外に出られない字義である。兎が自由を表しているのだろうか。
袴田巌さんは、1966年8月、30歳で一家4人殺害、放火の疑いで逮捕され、44歳で死刑確定。78歳で再審が決まって死刑と拘置が執行停止、そして、ようやく釈放された。
獄中48年だった。最高裁で死刑が確定した後、精神的に変調をきたし、現実から乖離するようになった。2024年9月、88歳で無罪が確定した。が、精神は元にもどっていない。
袴田さんが無罪判決を得てから、およそ半年後。25年3月、石川一雄さんが誤嚥性肺炎で死亡した。86歳。1963年5月、女子高校生誘拐、殺人の疑いで逮捕。24歳だった。一審死刑判決。二審無期懲役。94年、31年7カ月ぶりに仮釈放。それから30年がたって、第3次再審請求中に死亡。妻の早智子さんが、第4次再審請求人となった。
石川さんは「見えない手錠をはめられている」と訴えていた。それをついに外せなかった。
……