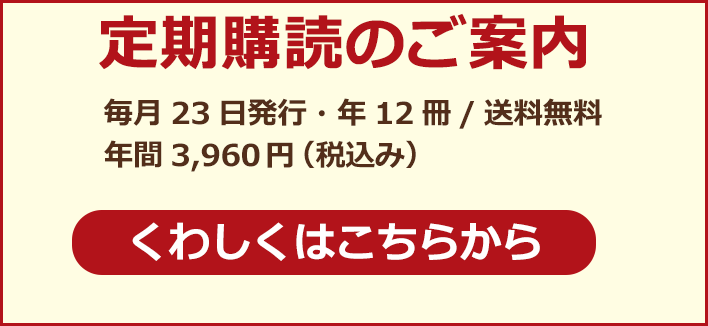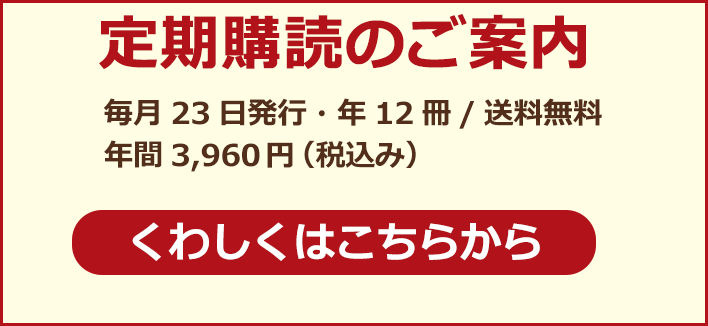新聞うずみ火 最新号

2024年7月号(No.225)
-
1面~3面 輪島塗の輝き消さぬ 老舗漆器店 全壊から再開(矢野宏)
能登半島地震の発生からまもなく半年。特に被害の大きかった石川県珠洲市や輪島市では倒壊した建物が今も手つかずのまま放置されている。復興を支える産業や観光資源も大きな打撃を受けた。国の重要無形文化財に指定されている輪島塗は工房のほとんどが被災し、これまでにない危機に瀕している。それでもなお、一人の塗師が伝統工芸の再建に向けて一歩を踏み出した。
「輪島塗がこのままなくなったら、日本の漆文化がダメになりますよ」
そう話すのは、江戸時代から続く老舗の塗師屋「大崎漆器店」4代目の大崎四郎さん(81)。輪島塗の「命」ともいうべき漆にこだわる。今では貴重な国産物を20年も30年も寝かせて使うことで「100年使える」堅牢優美な漆器を手がけてきた。
「輪島塗の漆器は美術品ではなく、暮らしの道具」と、百貨店での販売を嫌い、「自作自売」に徹する。
輪島塗の由来は諸説あるが、鎌倉時代後期から室町時代初期に紀州の根来寺の僧侶が根来塗の技法を伝えたのが始まりだという。1977年には漆器産地で初めて国の重要無形文化財に指定された。
輪島塗の最大の特徴である堅牢さは、輪島でしか取れない珪藻土(けいそうど)「地の粉(じのこ)」の存在が大きいという。「粒子はガラスのように固く、漆に混ぜて下塗りを繰り返すうちに丈夫な層ができるのです」
輪島塗の優美さは「専門職人による高度な『分業制』から生まれる」と大崎さんは説明する。
完成まで120を超える工程があり、制作にかかる日数は1年ほど。主な工程は大きく分けて、木材から器を削り出す「木地(きじ)」、地の粉を混ぜた漆を塗り重ねて補強する「下地塗」、仕上げの「上塗」、漆で絵柄を描いた漆器の表面に金粉などを蒔きつける「加飾」がある。
…… -
4面~5面 牡丹社事件150年激戦地で追悼 台湾出兵の発端 友好誓う(栗原佳子)
台湾に漂着した琉球人54人が先住民族のパイワン族に殺害された報復を口実に、明治政府が1974年、台湾に出兵して今年で150年。総称して「牡丹社事件」と呼ぶ台湾の激戦地・石門古戦場跡で5月22日、150周年の追悼式があった。沖縄からも宮古島の遺族ら多数が参列、悲劇を互いに克服し、平和と友好へと手を携えることを誓った。
切り立つ岩山が連なる独特の地形。台湾最南端の屏東県牡丹郷石門で150年前の5月22日、軍事侵攻した日本軍とパイワン族との激しい戦いが展開された。日本軍は重火器で圧倒。頭目(リーダー)父子ら多くの死者が出た。
150年の節目となる今年の追悼式では、屏東県の周春米県長(知事)、牡丹郷の藩壮志郷長らと共に、宮古島市の大城裕子教育長、犠牲者の玄孫にあたる宮古島市議の上里樹(たつる)さん(66)が献花した。戦いに赴く人々を描いたパイワン語の劇も披露された。
屏東県は昨年、石門古戦場を県史跡に指定。建立された石碑の除幕式に大城教育長や上里さんらも臨んだ。
1871(明治4)年10月、琉球国首里王府に年貢を運んだ帰りの宮古島の貢納船が台風に遭遇。台湾南東部の八瑤湾に漂着した。乗っていた69人のうち3人は溺死、残る66人は山間のパイワン族集落に迷い込んだ。水や食事も提供されたが、言葉が通じず、誤解が重なり、54人が殺され首を切られた。12人は近くの漢人に保護され、福州の琉球館を経由して翌72年、帰国した。
…… -
6面~7面 足尾銅山鉱毒事件の現地を歩く 郊外無責任体制の原点(栗原佳子)
近代日本初の公害事件といわれる「足尾銅山鉱毒事件」を学ぶフィールドワークに参加した(「ヒロシマ講座」主催)。渡良瀬川研究会顧問で「田中正造とその周辺」(随想社)の著書もある赤上剛さんの案内で6月1日、2日の2日間、足尾や栃木・群馬の渡良瀬川流域を回った。解決のため奔走した田中正造の没後111年、閉山51年という歳月が流れたが、赤上さんが繰り返し強調したのは「足尾銅山鉱毒事件は今も続いている」だった。
栃木県の旧足尾町(現・日光市)の足尾銅山は江戸時代、幕府直轄の銅山として発展。1877(明治10)年、実業家の古河市兵衛が買収した。大鉱床を発見し、「富国強兵」「殖産産業」の国策のもと増産を続け、「東洋一の銅山」とも呼ばれるようになった。
しかし精錬工場から排出される亜硫酸、亜ヒ酸ガスで山の木々は枯死、製錬過程などで出た硫酸銅やカドミウムなどを含んだ毒水が渡良瀬川や周辺土壌を汚染した。「鉱毒被害は栃木、群馬、埼玉、茨城、千葉の5県、田畑10万ヘクタールに及びました。動植物は死滅、人々は胃腸病や眼病に苦しみ、早産や死産なども続出しました」と赤上さん。
栃木、群馬、茨城、埼玉の4県にまたがる渡良瀬遊水地。面積3300ヘクタール、東京ドーム700個分に相当する。遊水地沿いの展望台からハート型の谷中湖が見える。1906年まで、ここには栃木県の谷中村があった。
1890年の大洪水で栃木・群馬の流域に農作物が全滅する深刻な被害が出た。被害農民は大挙して政府に請願する「押し出し」を繰り返した。栃木選出の衆院議員、正造も操業停止を訴え続けたが受け入れられず、1901年に議員を辞職。天皇直訴に及んだ。
…… -
8面~9面 入管法改正 取り消し制度も 永住資格 さらに壁厚く(矢野宏)
外国人技能実習に代わる「育成就労」制度を創設する出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案が6月14日に成立した。永住資格の新たな取り消し制度も盛り込まれており、日本で暮らす外国人は強制送還におびえながら暮らすことになる。日本弁護士連合会「外国人人権法連絡会」共同代表の丹羽雅雄弁護士は「永住資格を持つ外国人の生活と人権を脅かす究極の悪法だ」と批判する。
永住資格は、原則10年以上日本に在留する人や、日本人と結婚した配偶者、高度な技術や知識を持つ人などが取得でき、在留期間や就労分野に制限はない。
資格取得には「10年以上日本に在留し、就労期間が5年以上」「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」「納税などの公的義務を履行していること」などの厳しい条件をクリアする必要がある。2023年末時点で永住資格を持つ外国人は約89万人。国別では中国籍が最多で33万人を超えており、次いでフィリピン籍(約13万人)、ブラジル籍(約11万人)、韓国籍(約7万人)と続く。
旧植民地である朝鮮半島と台湾の出身で、1945年9月以前から日本に住む人と子孫が取得できる「特別永住資格」(約28万人)は、今回の永住許可取り消しの対象外となる。
永住許可の審査は年々厳しくなっており、過去5年分の収入や納税に関する資料と、直近2年分の社会保険料の納付状況に関する資料を提出しなければならない。手続きも煩雑で、長年日本に住みながらも永住許可を受けられない人は多い。
今回の入管法改正の柱は「技能実習制度」を廃止し、2019年4月に在留資格を認めた「特定技能制度」に移行するための人材を育成する「育成就労制度」を創設すること。特定技能には1号(5年間)と2号(制限なし)があり、熟練した技能と日本語能力が移行条件となる2号になると、永住や家族の帯同を認められるという。
…… -
10面~11面 大阪万博に子ども100万人 無料招待に学校困惑(矢野宏)
2025大阪・関西万博の開幕まで300日を切った。大阪府内の4歳~高校生の子ども102万人の無料招待事業に、学校関係者の多くが頭を抱えている。会場予定地の夢洲について、交通の便の悪さや土壌汚染、メタンガスによる爆発事故も発生した。児童・生徒を連れて行って大丈夫なのか。安全に対する不信感は日増しに高まっている。
府教育庁は準備を進めるためとして、各学校に参加を希望するかどうかアンケートを行った。7割超が学校単位での来場を希望したとする最終結果を発表したが、回答の選択肢に「希望しない」とか「不参加」はない。
「未定・検討中」と回答した私立高校に理由を尋ねると、「『不参加』の選択肢がありませんでしたので『未定』を選択しています。高校は年間計画を立てることが大変なんです。危険性をさしおいても、万博に合わせて日程を組むなど無理です。維新政治の本質が見えてきており、府民の意識が相当変化していると思います」
また、「希望する」と答えた堺市の中学校は、「役人用語ですが『後ろ向きの全力疾走』です」と前置きし、懸念となっていることを寄せてくれた。「昼食をとる団体休憩所が2000人分、うちは生徒だけで1000人なので、場所を確保できるかどうか確認中です」
府立高等学校教職員組合は4月に続いて6月15日、大阪教職員組合とともに「万博への子ども招待事業の中止」を吉村洋文知事と府教育長に申し入れた。
…… -
12面~13面 プレサンス元社長国賠訴訟 冤罪体質変わらぬ特捜(粟野仁雄)
6月11日朝、大阪地裁に傍聴希望者が殺到した。大阪地検特捜部の4人もの検察官が証人尋問される。さらに特捜の取り調べ映像が法廷で公開されるのは初めてだからだ。
巨額横領事件で大阪市の不動産会社「プレサンス・コーポレーション」の社長だった山岸忍さん(61)が2019年に大阪地検特捜部に逮捕された冤罪。山岸さんが国を訴えた国賠訴訟での一幕である。
まず、事件の概要から。
大阪市天王寺区の学校法人「名浄学院」の土地取引をめぐり、理事になろうと画策した女がプレサンス社から18億円を借り入れて就任する。その上で、学校の土地を売却して全額返済した。学校の土地を勝手に売却した業務上横領となる。この際、プレサンスの社員A氏は、理事が横領することを知りながら、社長に18億円融資させた。
理事とA氏はすでに横領罪で有罪が確定している。
一方、山岸さんは「貸付なら」と融資を認めたが、横領目的は知らなかった。ところが特捜は「社長は横領を知りながら、マンション建設の土地が欲しくて金を貸した」と見立て、構図を作り上げる。そして、A氏から「見立て通り」の供述を取ろうとする。
「社長には横領計画を伝えていなかった」と主張していたA氏は脅しに屈し、「社長は知っていた」と供述する。
山岸さんは横領罪で起訴されたが、21年、大阪地裁は不当捜査を糾弾、山岸さんの無罪が確定した。検察は控訴すらできなかった。
…… -
14面~15面 ヤマケンのどないなっとんねん 「裏金」次々目くらまし(山本健治)
本紙が編集作業中の19日に岸田内閣発足後初めての党首討論が開催されたが、首相がダラダラ言い訳するだけで、まったく時間のムダ遣いだった。その前に今国会最大の問題である政治資金規正法改正案が自民提案に公明と維新が修正させたものが参院でも通過した。旧文書交通費の改正について首相が約束を破ったと言って維新が参院では反対するすったもんだがあったが、最終的には自公で通した。不信任決議、問責決議となったが、こんな改「正」で政治がきれいになるとは誰も思っていないまま、国会は閉会し、報道の中心は東京都知事選に移ってしまっている。
すでにそうなっていて始まる前から食傷気味であるが、都民も、国民も、誰が都知事になろうが、東京一極集中にブレーキがかかって地方が元気になるわけでもなければ、東京が牽引車になって低迷混迷から衰退退廃の急坂を転がり落ち始めている日本が元気になるなどとは思っていない。オーバーではなく虚無と絶望が日本全体を覆っているのが実態ではないか。こうした現状に対する危機感が首相をはじめとする政治家たちにないのが危機を一層深刻にしている。
何度も同じことを書いて申し訳ないが、岸田首相の支持率がもはやどうしようもないことは当人を含め誰もが知っているとおりである。どんな鈍感な人物でも、ここまでくれば出処進退を明確にするはずであるが、恥というものを知らない、あるいは知ろうともしないへらへらへーの首相は、外国訪問や外交課題で何かすると支持率が上がり、延命できるかのように思って、日米首脳会談、日韓首脳会談などを重ね、G7にも出席して勝手な約束ばかりしている。そのツケはいずれ国民に回されてくるのだから、ふざけるのもいいかげんにしろである。
…… -
16面~17面 世界で平和を考える ユダヤ社会分断した戦争(西谷文和)
3月15日、ドバイからのフライトでエルサレムへ。ドバイでチーズバーガー2000円、エルサレムで小さいピザが1500円。もうどこへ行っても「日本だけが安い」状態。日銀に国債を買い取らせた結果、利上げができずに円安。日銀に不動産投資(REIT)や株式の上場投資信託(ETF)を買い取らせて、株価だけを釣り上げて賃金は据え置き。すべてはアベノミクスの失敗で、「(中産階級以下の)日本人だけが貧しくなっている」状態なのだ。
「アベのおかげで大損や」。グチを言いながら、東エルサレムのホテルにチェックイン。通訳メイルの車に乗り込み「オリーブ山」の展望台へ。ここからエルサレム旧市街が一望できる。預言者ムハンマドが昇天したとされる黄金のドーム、その隣にユダヤの聖地「嘆きの壁」があり、その隣にはイエス・キリストが眠る聖墳墓教会がある。オリーブ山から1本の細道が旧市街に伸びていて、これはイエスが十字架を背負ってゴルゴタの丘まで歩いて行ったと言われる道。両サイドのオリーブは樹齢2000年、つまりイエスが処刑された時に植えられたものだ。悠久の歴史、学生時代に「教科書でしか知らなかった」風景を目の当たりにする。
オリーブ山から旧市街のアル・アクサーモスクへ。東エルサレムはパレスチナの土地なので通行人はすべてアラブ人。主要な交差点はイスラエル軍がブロックして、車は通行止め。メイルに尋ねる。なぜ大通りをブロックするの?
「今日はラマダンに入って初めての金曜日。アラブ人がモスクに行けないようにしているのさ」。イスラム教徒にとって大切な金曜礼拝。普段から虐げられているアラブ人たちが礼拝後に怒りを爆発させ、金曜午後に暴動が頻発する。アラブ人がモスクにたどり着けないようにしているのだ。仕方なく引き返し裏道に入る。やはりイスラエル兵がアラブ人を止めている。「通せ」「通さない」。兵士とドライバーが口論になる。すると銃を担いだ兵士が車の窓からドライバーにパンチ。殴られたアラブの若者が車を急発進させて逃げて行く。この国では普通に兵士が住民を殴る。殴った兵士は捕まらない。
…… -
18面~19面 フクシマ後の原子力 ゴジラ誕生70周年の世界(高橋宏)
第五福竜丸をはじめ多くの漁船が被ばくしたビキニ事件、そして、その影響を強く受けて制作された映画『ゴジラ』の公開から今年は70周年になる。70周年の記念作品として、昨年11月3日(第1作公開日)に公開された山崎貴監督の『ゴジラ-1・0(マイナス・ワン)』は、実写版の30作目。国内外で大ヒットし、アカデミー賞の視覚効果賞を受賞したことは記憶に新しい。
広島・長崎への原爆投下から9年、そしてビキニ事件発生直後に制作された第1作『ゴジラ』は、強烈な反核のメッセージが込められた作品だった。登場人物のせりふにも、核に対する怒りや警鐘が随所に登場したし、何よりもゴジラ自身が被爆者のイメージを体現していた。ところが、その後に続くシリーズでは徐々に反核のメッセージは薄れ、核兵器使用に対するハードルも下がっていく。
特に、アメリカで制作されたGodzillaシリーズにおいては、全5作品のうち、モンスターヴァースシリーズの2作品で実際に核兵器が使用されているのである。私は、アメリカのGodzillaは、日本のゴジラとは全くの別物という認識だ。しかし、仮にも「ゴジラ」と名のついた怪獣が登場する映画で、何のためらいもなく核兵器が使用されたことに、強い怒りを禁じ得ない。
一方、『ゴジラ-1・0』は敗戦直後の日本が舞台で、特攻から逃げ、怪物からも逃げた主人公が抱えるトラウマを軸に物語が展開する。「国のために死んでこい」という命令の理不尽さなど、戦争の愚かしさが全編に描かれている一方で、核についての具体的なせりふはほとんど出てこない。
…… -
20面 大阪大空襲79年 「命ある限り語りたい」(矢野宏)
太平洋戦争末期の1945年6月、大阪は1、7、15日とほぼ毎週のように大空襲に見舞われ、街は焼け野原となった。計8回を数える大阪大空襲の中でも最も凄惨な無差別空襲の一つが7日の第3次大阪大空襲だった。来襲したB29爆撃機は409機。目標は大阪市北東部で、当時「東洋一の軍需工場」と言われた大阪砲兵工廠に初めて1㌧爆弾が投下され、無差別焼夷弾爆撃に続いて、戦闘機P51ムスタング138機が逃げ惑う住民を機銃で狙い撃ちにした。
7日午前11時9分から1時間20分あまり、東淀川区や旭区など大阪市北東部、さらには大阪府豊中市や吹田市などにも1㌧爆弾や焼夷弾が投下され、焼け出された市民の多くが機銃掃射に倒れた。この日の犠牲者は2759人、重傷者は6682人を数えた。
城北公園に放置された身元不明の遺体千数百体あまりが淀川堤防に運ばれて荼毘に付された。惨状を目の当たりにした「千人塚慰霊法要協賛会」会長の東浦栄一さん(95)の父・栄次郎さんが自宅庭の岩に「千人つか」と刻み、敗戦の翌年から慰霊法要を営んできた。
父親の死後、遺志を受け継いだ東浦さんが私財を投じて続けてきたが、2020年から新型コロナの感染防止のため中止に。79年目を迎えたこの日、東浦さんは子や孫ら5人で慰霊碑に手を合わせた。
…… -
21面 関東大震災 検見川事件 三重の犠牲者 過去帳遭った(栗原佳子)
多くの朝鮮人、中国人が官憲や自警団に虐殺された1923年の関東大震災。地方出身者が犠牲になる事件も頻発し、千葉県千葉郡検見川町(現在の千葉市花見川区検見川)では秋田、三重、沖縄の出身者3人が自警団に殺された。この「検見川事件」を調査してきた東京都葛飾区の島袋和幸さん(70)が6月17日、三重県の犠牲者の出身地を訪ね、ゆかりの寺で、初めて過去帳などを確認した。
…… -
22面 映画「アディクトを待ちながら」 依存症からの回復描く(栗原佳子)
ギャンブル、アルコール、薬物、買い物、ゲーム……。さまざまな依存症からの回復をテーマにした劇映画「アディクトを待ちながら」が7月5日からアップリンク京都、6日から大阪・第七藝術劇場で上映される。アディクトとは依存症者のこと。俳優の高知東生さんら当事者や家族が多数出演。ナカムラサヤカ監督にオンラインで作品に込めた思いを聞いた。
物語は、数々のヒット曲を持つ大物ミュージシャン、大和遼逮捕のニュースからはじまる。覚せい剤と大麻の所持容疑だった。
2年後。依存症患者らで結成されたゴスペルグループ「リカバリー」のコンサートの日が近づいていた。大和もメンバーの一人。沈黙を守ってきた大和のカムバックを待ちわび、当日、会場の音楽ホール前には熱心なファンが続々と集まってくる。
互いに支え合いながら、依存症の再発=スリップをすることなく本番の日を迎えた「リカバリー」の面々。しかし開始時間を過ぎても大和が来ない。いったい何がーー。
…… -
23面 会えてよかった 小底京子さん④(上田康平)
全国13療養所自治会でも
将来構想、入園者が安心して暮ら
していけるように、どう園を残すか
が一番大きい課題だという。
愛楽園自治会独自の取り組み
現在、入園者(自治会員)は93名、
平均年齢は85歳。「入園者のおじい、
おばあの悩みを聞いたり」、園の職
員との意見交換をしている。
「(入園者は)偏見差別の中、つ
らい目にあってきた。せめて最後は
安心して、生きていてよかったと人
生を終えることができたらと思う。
看護、介護、そのほかの職員の方々
には常に心やさしく入園者に寄り添
い仕事をしてほしい」
※※※
…… -
24面 日本映画興亡史 末三郎の「たまり場」(三谷俊之)
笹井末三郎に戻ってみたい。関東大震災直後の1923(大正12)年11月、末三郎の長兄静一の元に、日活大将軍撮影所長だった池永浩久が訪れた。震災で東京の日活向島撮影所もつぶれた。向島の所員や俳優たちを京都に呼び、撮影を再開したいのだが、大将軍撮影所は狭く、役者たちの宿舎もなかった。当時、映画界は新興の松竹の台頭著しかった。
京都出身の大竹竹次郎と、双子の兄で母方の姓(白井)を継いだ松次郎は、新京極の芝居小屋経営から身を起こし、京都と大阪の興行界を一手にした。竹次郎は関東の芝居興業も手に入れようと、歌舞伎界や新劇や新派の興業に関わる。やがて映画に目を向けた2人は、末弟の白井信太郎にハリウッドの撮影所を視察させるなど周到に準備し、松竹キネマ合名社を設立、大正9年に東京蒲田撮影所を開いた。初代撮影所長は信太郎だった。
日活は旧態依然として女形を使っていたが、松竹は当初から栗原すみ子、川田芳子ら美人女優を使って人気を得ていた。日活からはマキノ省三がすでに去り、重役の尾上松之助は東京の現代劇が来ることを喜ばない。社長の横田永之助は責任をすべて池永に押しつけていた。悩んだ池永は静一の力を頼んだのだ。静一は自分の経営する旅館、天龍寺にある笹井家の借家などを快く提供した。この時から、笹井家=千本組は映画を本格的に事業として取り組んでいった。
…… -
25面 坂崎優子がつぶやく 「虎に翼」百年経てど…
NHKの朝ドラ「虎に翼」がおもしろい。こんなに毎朝わくわくするドラマは久しぶりです。脚本、演出、そして演者。全ての質が高いからだと思います。
主人公は日本初の女性弁護士となった三淵嘉子(みぶちよしこ)さんがモデルです。女性に門戸が開いた法学部で、自分も学びたいと訴える娘に、母は「地獄を見る覚悟があるか」と問います。そしてその言葉通り、主人公・寅子の地獄の日々が始まります。
司法試験は男性と並ぶ程度では合格できず、圧倒的な力を要求されるし、弁護士になると「担当は女性ではなく男性を」と言われてしまう。心身をすり減らした寅子は出産とともに弁護士をやめ、終戦を迎えます。
戦争で兄と夫、さらに病気で父親も亡くし、ただ毎日食べることだけを考えて生きていたある日、新しい憲法、その第14条を目にします。「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。それは彼女が再び法の世界に戻ろうと動き出す原動力となります。
この原稿を書いている6月の2週目は、新憲法に合わせて民法の「親族」「相続」の部分も改正する作業に寅子が関わるという内容です。保守の重鎮である学者とGHQとのせめぎ合いの中に放り込まれた寅子は、徐々に本来の自分を取り戻します。
学者の「このまま改正すると日本の古き良き伝統である家族観を崩壊させる」という主張に対し、婦人代議士たちが笑いながら放った「古き良きなんて明治時代から始まったばかりじゃない」も辛辣です。
…… -
26面~29面 読者からのお手紙&メール(文責 矢野宏)
大阪市の発掘調査
軽んじる協会解散
大阪市東住吉区 吉村直樹
大阪は古代、中世、近世、近代と日本の歴史の中で重要な位置を占めていました。まだまだ未発掘の遺跡や埋蔵物が地中に眠っています。特に大阪市域に集中しています。その発掘調査をこまめに担ってきた一般財団法人「大阪市文化財協会」が今年度をもって解散させられることが明るみに出てきました。理由は府市統合と博物館の独立行政法人化によるものです。
大阪歴史学会発行の「ヒストリア」第304号によると、前身の市文化財研究所は、市内各地域の発掘調査を実施し、その保存と活用を図ることを目的に、難波宮址顕彰会などの三つの調査団体を統合して1979年に設立されました。
これまでの発掘物の保存やその業績はどうなるのか分かりません。市文化財協会の機能は大阪府文化財センター(堺市)や「民間活力の導入」でカバーするとされていますが、府文化財センターでは多数の発掘ポイントが予想される大阪市域の発掘をこまめにできません。
また、民間活力の導入では発掘調査が営利性、採算に合うかどうかで判断され、学術性や必要性がないがしろにされます。
大阪市域は発掘すればまだまだ大阪人がどういう生活をし、どういう文化を作り出してきたかが解明される場所です。市の文化行政の機関が市民の知らないままに解体されようとしています。文化を軽視する行政の姿勢が残念です。
(維新政治の弊害がまた一つ明るみに出ました。目の前の儲けが第一、文化にはまったく興味を示さない。市民の財産がまた一つ消えようとしています)
……
-
27面 車イスから思う事 夏の適温 人それぞれ(佐藤京子)
東京では梅雨入りもしていないのに、夏を思わすような天候が続いている。蒸し暑さが体の芯からふつふつと湧いてくるようになると、空調の温度に敏感になる。電車には「弱冷房車」が少なからずある。バスは冷房しているのだろうが、ほとんど冷えていない。最近は公共の交通機関を利用することが増えてきたこともあり、車内温度には過敏だ。暑い暑いと言っているだけではなく、いかに暑さを気にしないで過ごすか、考えるようにしている。その方がイライラすることが減るからだ。
先日、電車で移動していると、汗びっしょりの人が乗りこんできた。汗を拭く姿に、見る方も暑くなってくる。一方で、ベビーカーの子どもに若い女性がタオルをかけている。この差はいったい何なのだろうか。そういえば、通勤電車の冷房が効きすぎていると、毎朝地下鉄の駅に会社から電話で苦情を言っている人がいると聞いたことがある。ここまでやると苦情というより、嫌がらせとしか思えない。
ここ数年、町の中に「携帯扇風機」を手にする人が目立つようになった。あれで少しは涼しくなるのだろうか。試してみたいと思うが、この年になると、なかなかきっかけがない。この年になると、多少のためらいもあるが、年々使用している人が増えているのをみると、やはり、試す価値はあるかな。
一人で家にいるときは部屋を閉め切って冷房をつける。自分と介助犬イムア君が涼しければいいからだが、イムア君の方が暑がりかもしれない。床に寝ていても体が温まるらしく、何回か場所を変えてハアハアしている。そんな時は水分を取らせるようにしているが、イムア君は中から冷やすのが効果的だ。自分も見習って飲み物で中から冷やす。家にいる時には、トイレを探す心配がないので気が楽だ。何だかこう書いているとだんだんと夏がくる気がしてきた。暑さで辛いことが多いが、どう過ごすかを考えるとき、少しだけ楽しいと感じた。
夏の暑さ対策、結局は自分で納得のいくように考えた方がいいのだろう。
(アテネパラリンピック
銀メダリスト 佐藤京子)
-
29面 絵本の扉「ロバのシルベスターとまほうの小石」(遠田博美)
作者であるウィリアム・スタイグは20世紀初頭生まれで、漫画家としてスタートしました。児童文学作家として活動し始めたのは1968年。本作品はその翌年出版されました。
表紙は、ロバの夫婦がブタや鶏に何か尋ねている様子が描かれています。何があったのでしょうか。主人公であるロバのシルベスター・ダンカンの楽しみは、変わった色や形の小石を集めること。夏休みのある雨の日、遊びに出かけて奇妙な石を見つけます。 燃えるように赤く光っており、ビー玉のようにまん丸です。思わず「雨がやんでくれたらなあ」と石を持ったまま思うと、雨がピタリと止みました。こんなにすぐに望みがかなうのを不思議に思った彼は、次々に天気の願いごとをして小石の力を確認します。そして、大好きなお父さんとお母さんの待つ家に小石のことを伝えようとした帰り、彼は失敗をします。森で怖いライオンを見かけてあわててしまい、見つからないように「岩になりたい」と考え、望み通り岩になったのです。ロバの姿に戻るためには、小石を手に取って願わねばなりません。岩になってしまった彼は何もできなくなりました。
一方、かわいい息子がいつまでも帰って来ない両親の気持ちはいかほどであったでしょう。悲しみにくれながらも町中を訪ね歩き、森にも仲間と一緒に入り、探し回ります。岩になったシルベスター。両親が探しているのに彼の匂いもせず、もう息子には二度と会えないと絶望します。
その間も季節は流れ、岩の周りにも秋が過ぎ、寒い冬が来ます。諦め始めたシルベスターは、もう自分を岩と思おうと絶望的になります。そして、再び春が巡ってきます。 春が巡って来た場面は、岩のシルベスターとその横にある赤い小石。周りは花と緑にあふれています。そこへ、少しは元気を出そうと両親がやって来たのです。岩に腰を掛け、ピクニックの用意をします。お父さんがふと下を見ると、赤い石が……。さて。この後どうなると思いますか。
作者のスタイグは幼い頃、児童文学の「ピノキオ」に深く心を動かされたそうです。今回の話は、ピノキオのラストに寄り添っています。彼は、「芸術を通して子ども達に手渡すものに大きな意味がある」とも言っています。子どもを大切にし、子どもの未来の幸せを大人が願うことが大切だと言っています。
聞き手の子ども達はシルベスターが岩から戻れるかとドキドキするようですが、読み手の私はついつい両親の目線で話に入り込んでしまいます。
-
30面 大阪市「木を切る改革」 扇町公園で伐採強行(矢野宏)
大阪市が公園樹や街路樹の安全対策として、倒木の危機のある樹木約1万9000本の伐採を進めているが、市民は「切る必要のない健全な木も切っている」と選定基準のあいまいさを指摘。北区の扇町公園事務所に再三にわたって説明を求めてきたが、6月17日に伐採が強行された。
市民団体「大阪市の街路樹撤去を考える会」の求めに応じ、5月24日に団体協議の場を設けたが、説明は伐採ありきで平行線。「協議の必要はない」とのメールを送りつけ、公園内の56本の伐採に踏み切った。 -
31面 うもれ火日誌(矢野宏)
5月11日(土)
矢野 午後、京都府精華町で開かれた陸上自衛隊祝園(ほうその)分屯地の増強について考える「祝園ミサイル弾薬庫問題大学習会~ガザ・沖縄そして祝園」を取材。
5月15日(水)
能登半島地震の発生から4カ月半。矢野、栗原は朝、JR大阪駅から特急サンダーバードで敦賀に向かい、北陸新幹線に乗り換えて金沢市へ。レンタカーで石川県輪島市を再訪。支援団体「のと復耕ラボ」代表の山本亮さんに、元MBSアナの水野晶子さんの被災地支援ライブの収益金を手渡す。155人が避難生活を送っている輪島中学校で、被災した料理人4人が行っている炊き出しのお手伝い。
5月16日(木)
曇り空のなか、「のと復耕ラボ」現場リーダーの尾垣吉彦さんに従い、災害ゴミの搬出ボランティア。午後から雨になり終了。輪島朝市などを回ると手つかずのまま。「県と被災現場との温度差が埋まらない」との尾垣さんの言葉を胸に帰阪。
5月18日(土)
矢野 午後、大阪府茨木市内で開かれた「教科書問題を考える北摂市民ネットワーク」の学習会「ゆがめられてきた大阪の教育を考える」で講演。 栗原 元教師の相可文代さんの講演を聞いたあと取材。
5月20日(月)
栗原 午前 関空から台北、台東へ。牡丹社事件150年を知る旅へ。24日帰国。
5月22日(水)
新聞発送を翌日に控え、折込チラシのセット作業に追われる。矢野のフェイスブックでの悲鳴を聞き、石田冨美枝さん、川那辺康一さん、金川正明さんがお手伝いに。ありがたい。
5月23日(木)
夕方、新聞うずみ火6月号が届き、発送作業。川那辺さんと金川さんが前日に続き、残りのチラシセット、柳田充啓さん、JR東海労の多田一夫さんと高岡肇さん、康乗真一さん、工藤孝志さんのほか、長谷川伸治さん、大村和子さん、澤田和也さんの手を借り、郵便局の回収までに間に合う。
5月24日(金)
維新政治の身を切る改革ならぬ「木を切る改革」。「大阪市の街路樹撤去を考える会」の呼びかけで市民が伐採見直しの声を上げ、保留となってきた扇町公園の56本の樹木について、扇町公園事務所が現地説明会と協議。矢野も取材。
5月29日(水)
午後、事務所で茶話会。竹島恭子さんから「6月にひざの手術をします」との報告が。夜、矢野は十三の「風まかせ」で大田季子さんらと再会。
5月30日(木)
矢野 午後、名古屋市名東区の戦争と平和の資料館「ピースあいち」へ。運営委員の金子力さんに名古屋空襲と模擬原爆について話を聞く。
5月31日(金)
矢野 大阪暁光高校の嵯峨山聖教諭とオンラインで6月10日の平和学習の打ち合わせ。夜、定岡由紀子弁護士を囲んでの「憲法BAR」。中野万里さんが初参加。
6月1日(土)
午後、大阪市此花区のクレオ大阪西で「うずみ火講座」。落語家の三代目桂花団治さんが大阪大空襲を題材にした創作落語「じいじの桜」を披露。矢野が「大阪空襲訴訟敗訴から10年」と題して講演。
栗原 立川市の読者、竹内良男さんが主宰するヒロシマ連続講座の企画「足尾鉱毒事件と田中正造」を学ぶ1泊2日のフィールドワークに参加。
6月2日(日)
矢野 午後、元NHKカメラマンの小山帥人さんが『我が家に来た脱走兵~1968年のある日から』(東方出版)を出版を祝う会に。
6月4日(火)
矢野 翌朝から学校法人駿河学院が運営する三つの高等専修学校での「沖縄修学旅行の事前指導」のため、午後、新幹線で静岡入り。
6月5日(水)
矢野 朝、迎えに来た駿河学院理事長の杉下俊雄さんの案内で清水学院、駿河学院、藤枝学院を回り、「沖縄戦、そして今」と題して講演。夕方、帰阪。
-
32面 うずみ火講座(矢野宏)
戦後間もない日本で新憲法草案作りに参加したベアテ・シロタ・ゴードンのドキュメンタリー映画「私は男女平等を憲法に書いた」(ドキュメンタリー工房)の上映会とトークを7月13日(土)午後2時半から大阪市此花区のクレオ大阪西(JR環状線、阪神「西九条駅から徒歩4分)で開きます。
この企画の提案者である水田隆三さんが「ベアテ・シロタ・ゴードンのしごと」と題して語るほか、新聞うずみ火の矢野が「日本国憲法は押しつけ憲法なのか」についての取材報告も。
【資料代】読者500円、一般700円
8月3日(土)開催の「黒田清さんを偲び、平和を考えるライブ」が近づいてきました。黒田さんが好きだったコント集団「ザ・ニュースペーパー」結成時のメンバーである松崎菊也さんと石倉直樹さんによる風刺トーク&コントライブ。心行くまでお楽しみください。
なお、当日会場でお配りするパンフレットの「ひと声広告」(メッセージを入れて1口3000円~)を募集しています。 ご協力いただいた方には招待券をお贈りします。
今月号に郵便振込用紙を同封させていただきました。物価高騰の折、何かと大変だとは思いますが、ご無理のない範囲でご協力いただけると幸いです。
【日時】8月3日(土)午後2時開場、2時半開演
【会場】豊中市立とよなか男女共同参画推進センターすてっぷホール
【交通】阪急宝塚線「豊中駅」南口改札から右手、エトレ豊中5階
【資料代】読者2000円、一般2200円(1口3000円~の「ひと声広告」、またはカンパをいただいた方は無料)