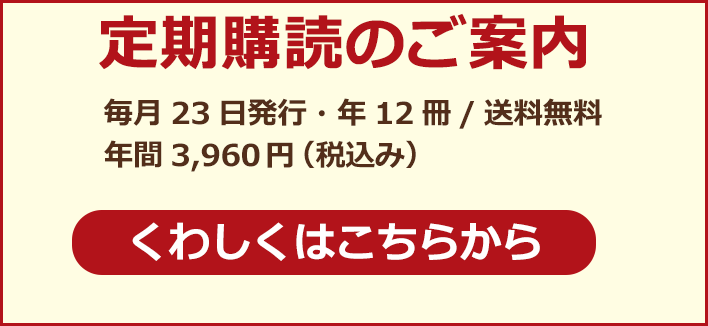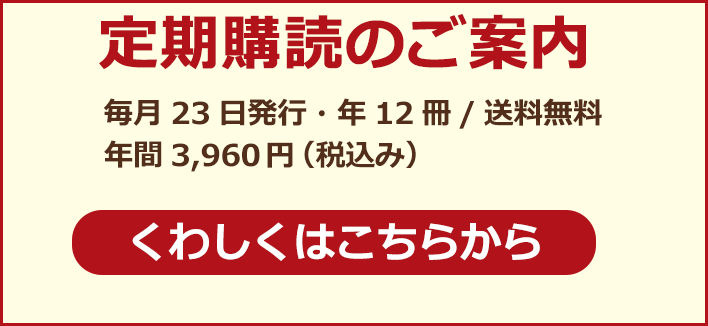前回の「大阪都構想」をめぐる住民投票の時、自民党選出の堺市議に「維新のどこが嫌いか」尋ねたことがある。その市議は「平気でうそをつくところ」と即答し、こう説明した。「うそをつかれると議論にならない。民主主義の崩壊につながります」
高市早苗首相は「物価高の中で2026年度予算と税制改正関連法を早期に成立させる」と説明していたのに一転、通常国会の冒頭で解散総選挙に踏み切った。「高市早苗が首相で良いのか、国民に決めていただく」と訴えていたが、騙されてはいけない。自らの不用意発言による中国との関係悪化、旧統一教会との関係や裏金問題にも決着がついていない。内閣支持率が高いうちに衆院選に踏み切れば自民党の議席が増やせるという計算があったのは間違いない。この自己都合解散で、26年度予算の3月末までの成立は困難になった。
自分勝手なうそつき政治家は大阪にもいる。任期途中で知事を辞任し、市長も伴って大阪出直しダブル選を仕掛けた維新の吉村洋文氏。都にもならないのに、2度も否決された「都構想」実現に向けて民意を問うと1月22日に第一声をあげた。6年前、2度目の住民投票が否決された後、「僕たちが掲げてきた大阪都構想は間違っていた」「政治家として大阪都構想に挑戦することはもうない」と明言したのは誰やねん。
立憲民主党も新党「中道」に衣替えするや、これまで掲げてきた「安保法制の違憲部分の廃止」「原発ゼロ社会を一日も早く実現」の方針を投げ捨ててしまった。有権者は見ている。
「三代目は身上をつぶす」とのことわざがある。創業者や先代が苦労して成長させた会社を、その苦労も知らない3代目が十分な経営能力もないままに社長になり、会社を傾けさせてしまうこと。かつて明治維新から3代目の世代が国家権力の中枢を握り、無謀な太平洋戦争へ突入し日本を滅ぼした。戦争を知らない3代目世代が選挙をもて遊び、再びこの国を滅ぼそうとしている。2月8日、うそをつかない政治家を選びたいものだ。 (矢)