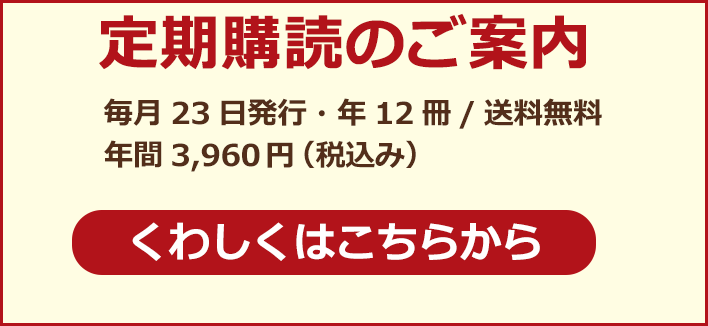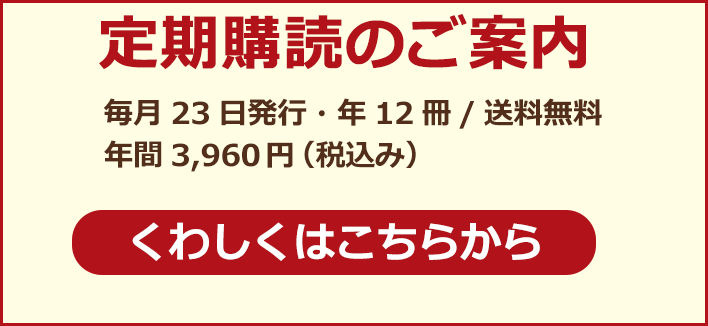10月27日、「電力労働運動近畿センター20周年記念集会」が大阪市内であり、乾杯の挨拶をした。
電力労働運動近畿センターとは、関西電力の労働者、OB、支援者らで組織する労働団体で、その母体となったのが「関西電力争議団」だ。
争議団とは、会社内で経営者と労働者との間で紛争、つまり「労働争議」が起きた時、経営者などに対抗して一時的に組織される労働者の団体のこと。
1960年の安保闘争のあと、関西電力は共産党やその支援者、いわゆる「左派」の労働者を職場から排除するか、考え方を改めさせる「反共労務管理」を進めていく。
当時、「左派」の労働者たちは関西電力労働組合の本部や支部の中で役職についていた。職場での選挙で選ばれるのだが、各職場で「この人に入れなさい」と上司から命じられるなどの組合選挙への干渉が行われ、組合での役職を取り上げられていく。
次に彼らを待っていたのは、転向強要、不当配転、職場でのいじめだった。新たな職場では一日中、机の前に座らされたまま、ろくな仕事も与えられなかった。トイレに行くにも上司の監視の目が光り、職場でのレクリエーションやサークル活動からも仲間外れ。昇格もなく、同期との賃金格差も広がっていく。なかには、会社側が警察と連絡を取り合って監視や尾行されるものもいた。
こうした人権無視の労務管理の中で、退職に追い込まれる者も多く、中には自殺者も出た。労働組合から締め出され、職場でも孤立させられた「左派」の労働者にとって、自分たちの考えを訴える最後の手段はビラを配って、思いを訴えること。だが、それすらも許されず、懲戒処分にされてしまう。
こうした人権侵害、賃金差別の是正を訴え、101人の労働者が提訴した。
提訴から25年後の95年、最高裁が「現実には企業秩序を破壊し、混乱させる恐れがあるとは認められないにもかかわらず、共産党員またはその同調者であることのみを理由にして行われた関電の反共労務管理について、異常で非人間的な不法行為だ」と述べ、「職場での自由な人兼関係を形成する自由を侵してはならない」という判断を下した。
この判決から4年後の99年12月、関電は憲法に従って他の従業員と公平に取り扱うことなどを約束、解決金として12億円を支払って和解した。
30年以上にわたる闘いを取材して、一冊の本にまとめたのが「関西電力の誤算」だった。
そのタイトルには当初、「埋み火」を予定していた。灰の中に埋めた炭火のことで、消えることなく翌朝、新たな火種となる。決して自分の信念を曲げることなく、仲間を裏切ることなく闘い抜いた関電争議団一人ひとりを思い描いて考えたタイトルだった。
だが、文学的で分かりにくいため、お蔵入りとなった。
「うすみ火」という名前をつけた新聞を出すことにしたのは、本を出して3年後のこと。新聞うずみ火も来年は創刊15年を迎える。(矢野)