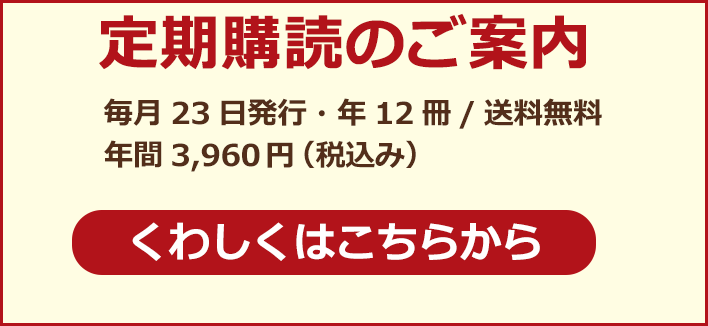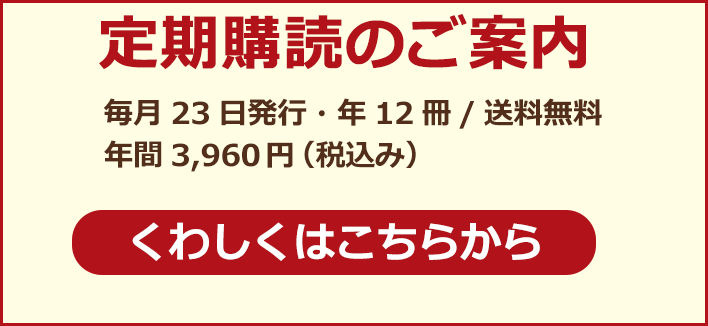参院選投開票日前夜、事務所すぐ近くで参政党の「打ち上げ」街宣があった。おぞましいフレーズに合いの手の拍手が沸き起こる。恐怖を覚えた。
気を取り直し、この日、久しぶりに開いたのが「みんなのために 自分のために」(解放出版社)。黒田清さんが手がけた「窓友新聞」で1990年1月号から始まった長期連載「90年代○社会」の一部を書籍化したもので、「窓友新聞」に転職する前の私は、一読者として毎月、紙面でこの連載を読むのを楽しみにしていた。
◯社会=マル社会とは何なのか。前書きで黒田さんはこう記している。
〈戦争中までのタテ社会に代わって、日本社会の基盤となったはずの民主的ヨコ社会も、一人一人の個人、一つ一つの団体が、お互いに垣根を作り孤立している間は隙間だらけの社会であり、その隙間に差別が入りくんでくるということです。
では、どうすればいいのか。タテは駄目、ヨコでもアカンというのなら、1990年代の生きかたは「マル社会」でなければならないのではないか。 「マル社会」は、生き方も考え方も同じ人たちが手をつないで丸くなって生きることではありません。それぞれが自分の生き方、考え方を大事にしながら、違った生き方、考え方の人たちが手をつないで生きる社会です。それが自分のため、そして同時にみんなのためになるのです〉
黒田さん、「窓友新聞」が活動の柱とした反戦反差別。後継を自認する「新聞うずみ火」もそれを標ぼうしてきた。でも、マル社会はさらに遠ざかってしまった。敗戦80年の節目だというのに。
それでも、地道にやり続けます。読者と共に。まもなく創刊20年。